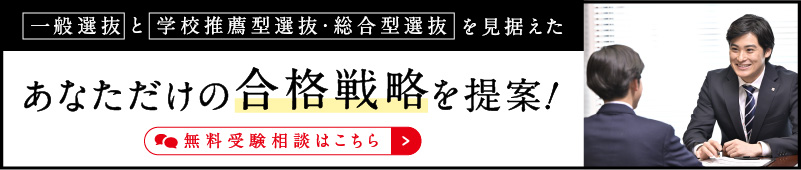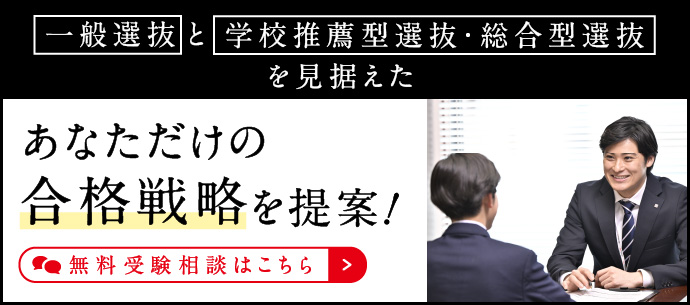TOMASによる学校推薦型選抜・
総合型選抜対策
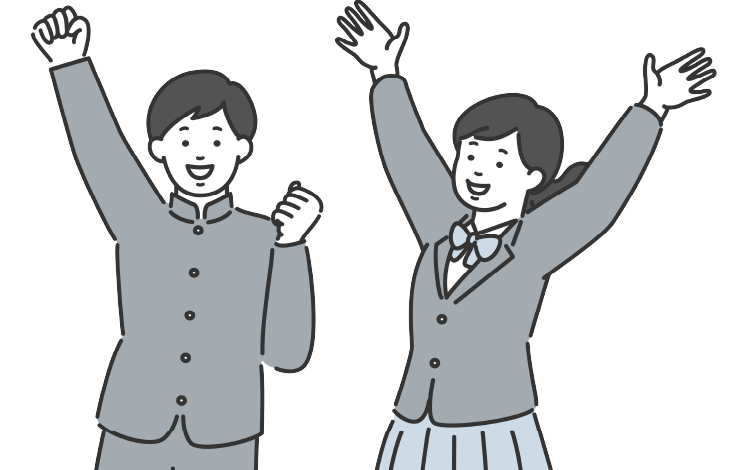
TOMASにおける推薦・総合型対策の大前提について
大学側の要求を反映した指導
TOMASが推薦・総合型対策として掲げる大前提は、「各大学が求める受験生像」に沿った指導です。
一般選抜であれば、「各大学が求める受験生像」は、とにかく「学力のある受験生」です。その思想はアドミッション・ポリシーとして入試問題に反映されています。みなさんが志望校の過去問を見ても、たとえば「基礎学力が重視されている」とか「基礎学力を踏まえた運用能力が試されている」など、自分に求められている受験生像は比較的簡単に把握できるはずです。
一方、推薦・総合型には、学力試験のようなわかりやすい指標は存在しませんし、たとえあるにしても公表されていません。また、推薦・総合型の採点基準は、大学の数だけ存在すると言っても過言ではないくらい多種多様です。
しかし、私たちのようなプロ指導者は、推薦・総合型によって求められる受験生像=入学後の学生像のポイントを把握しています。それは、「勤勉な学生」「基礎学力を有する学生」です。
推薦・総合型によって、大学側は、たとえば講義が開かれる教室で最前列に座って熱心にノートをとるようなまじめな学生を求めています。また、現段階ではたとえ高度な運用能力や思考力を必ずしももっていなくても、それらの前提となる知識・技能などがある学生に高い将来性を期待しています。このように、推薦・総合型は、一般選抜とはまったく異なる思想にもとづいて実施される試験だと考えてください。
「プレゼン能力」を高める指導
では、勤勉な受験生、基礎学力がある受験生であればだれでも推薦・総合型をパスできるのかというと、もちろんそのようなことはありません。試験で課される志望理由書・面接・小論文を通じ、自分がその志望校にふさわしい受験生であることをアピールできなければならないからです。
アピールすべきポイントには、「特技」「資格取得」「検定合格もしくは取得スコア」「英語能力」「留学経験」などがあります。難関校を志望する受験生の中には、たとえば数学オリンピックや化学オリンピックのような「難関資格ホルダー」がごろごろいます。しかし、たとえこれらの華々しい活動実績をあなたが備えているとしても、試験官にうまく伝えることができなければ合格を勝ち取ることはできません。TOMASでは、その対策として、生徒に「プレゼン能力」を身につけさせる指導を重視しています。
「受験戦略」にもとづく指導
仮に、あなたが大学側の要求を正確に把握し、プレゼン能力も高めることができたとしましょう。では、推薦・総合型での合格はもう確実かというと、そう甘くはありません。あなたがもっている能力や実績と、大学側が掲げるアドミッション・ポリシーが一致せずミスマッチが起きている場合には、合格が遠のいてしまうからです。
TOMASでは、合格可能性を高めるために、「受験戦略」の指導を重視しています。すなわち、「自分がもつ能力や実績を最大限に評価してくれる大学はどこか」「志望理由書・面接・小論文のうち、どの対策に力点を置くか」という受験の戦い方を生徒とともに考え、指導に落とし込んでいくのです。
TOMASにおける志望理由書対策について
複眼的な指導
TOMASでは、1人の生徒につき2人の指導者がマンツーマンで志望理由書対策を行ないます。
1人目の指導者は、「教務社員」と呼ばれる各担任です。それぞれの担任は、生徒が書いた志望理由書原稿をしっかり読み込んだうえで添削します。
2人目の指導者は、小論文対策を専門的に指導する講師です。このような立場にいる講師は、添削だけでなく授業も行ないます。
担任による指導および講師による指導は、生徒のレベルや性格に応じ、しっかりと時間をかけて柔軟に組み立てられます。担任も講師という指導の専門家がそれぞれの視線から生徒にかかわり、「各大学が求める受験生像」にアプローチしていくのです。
「志望理由」の必然性を高める指導
きわめて当たり前のことですが、志望理由書で最大限にアピールすべきなのは「志望理由」です。しかし、その志望理由は、どこの大学にでも該当するような内容ではなく、「貴学に絶対入りたい」という必然性を含む内容でなければなりません。
TOMASでは、志望理由書を練り上げるために必要なモチベーション高揚、ならびに志望理由をまとめ上げるために必要な素材集めをうながすため、生徒に「オープンキャンパス」「学園祭」への積極的な参加を推奨しています。さらには、このような場への参加で高まったモチベーションと集まった素材を志望理由書に反映させるためのフォローアップも入念に実施しています。
TOMASにおける面接対策について
「人物評価」を高める指導
推薦・総合型の面接には「人物評価」という側面があります。そういう意味では、就職試験が職場で同僚としてともに仕事をしたい人物を選ぶ場であるのと同様、推薦・総合型も、大学側が「採用」したい人物を選ぶ試験だと言えるでしょう。このことを受け、TOMASでは「大学に選ばれる人物を育てるための指導」を展開しています。
就職試験が何度かに分けて実施されるのと同様、推薦・総合型も、一発勝負ではなく何種類かの試験に分けて行なわれます。もっとも、試験の種類に違いはあるものの、その根底には、「受験生が、本学の学生としてふさわしい人物であるかどうかを見きわめたい」という方針があります。
「本学の学生としてふさわしい人物であるかどうか」を測るために重要な指標は、おもに2つあります。1つは先述のとおり「学力」、もう1つは「性格・気質」です。
「性格・気質」は、受験生の立ち居振る舞い、たとえば、「あいさつが返せるかどうか」「相手との受け答えができるかどうか」などの点から評価されます。TOMASでは、このように面接の場で評価の対象となる礼儀作法を徹底的に指導しています。
TOMASにおける小論文対策について
「書き方」と「知識」の両面を指導
ほとんどの高校生は、「小論文を書いてください」と指示されると、およそ小論文とは似ても似つかない答案を提出してきます。その答案はいわゆる「作文」であり、小論文としての内容・体裁をまったく備えていません。
「作文」は、ただ感情に任せて書かれた文章です。一方、「小論文」は、感情に流されることなく客観的に書かれた文章です。
こう説明されると、小論文を書くことはさほど難しそうには思えないかもしれません。しかし、実際には、小論文答案の作成に対してほとんどの受験生が強い苦手意識をもっています。
たとえば、医学部医学科で「脳死について述べよ」という「テーマ型」小論文が出題されたとしましょう。この場合、受験生の多くが、たとえ高学力層であっても、「賛成」か「反対」かという意見を自分の感情の赴くままに書いてしまうのです。
出題者が小論文を通じて見ようとしているのは、受験生自身の「立場」ではありません。小論文で測られるのは、「~という賛成意見がある」「…という反対意見がある」というように、受験生が両論を併記するバランス感覚を備えているかどうか、または、それぞれの論のメリットやデメリットを示しつつ議論を組み立てることができるかどうかという点です。つまり、「客観性」の有無なのです。
TOMASの指導では、生徒が出題者の意図に沿い、客観性にもとづいて小論文答案が作成できるようになることをめざしています。
また、小論文答案を作成するためには、このような「書き方」以外に、たとえば先述した「脳死」のような、特定のテーマに関する背景知識も必要です。そこで、TOMASは、小論文答案作成に不可欠なキーワード・専門用語を教えるとともに、トレーニングを通じて定着させることもめざしています。
志望系統への興味・関心をアピールするための指導
では、推薦・総合型の小論文に客観性、正しい書き方、背景知識などを反映すれば合格レベルの答案が仕上がるのでしょうか。残念ながら、まだ要素が足りません。それは、「志望系統への興味・関心のアピール」です。
一般選抜で課される小論文では、先述のような客観性、正しい書き方、背景知識が盛り込めていれば十分で、受験生自身がもつ志望系統への興味・関心の有無はさほど重視されません。
一方、推薦・総合型の小論文には、面接と同様、「人物評価」の側面があります。そこで、TOMASでは、「本学の学生としてふさわしい人物であるかどうか」を効果的にアピールする方法も指導しています。
以上のように、TOMASの推薦・総合型の対策は至れり尽くせりです。みなさんが我々TOMASスタッフによる指導を受け憧れの志望校合格を勝ち取るよう、強く願います。
参考文献(順不同)
- 早稲田大学公式Webサイト「入学センター」
https://www.waseda.jp/inst/admission/undergraduate/system/ao/ - 慶應義塾大学公式Webサイト「学部入学案内――入試制度」
https://www.keio.ac.jp/ja/admissions/examinations/ - 「週刊ダイヤモンド 2023/09/16・23 合併号」p.38~49「年内入試」完全攻略/p.50~55「年内入試」に強い学校
- 『大学受験案内2024年度用』(晶文社学校案内編集部〔編集〕/晶文社/2023年)
- 『螢雪時代9月臨時増刊 全国 大学受験年鑑[推薦&総合型選抜ガイド](2024年入試対策用)』(旺文社〔編集〕/旺文社/2023年)
- 『学校推薦型選抜・総合型選抜 だれでも上手にまとまる 志望理由書合格ノート』(神尾雄一郎〔著〕/KADOKAWA/2023年)
- 『改訂第2版 書き方のコツがよくわかる 医系小論文 頻出テーマ20』(神尾雄一郎〔著〕/KADOKAWA/2023年)
記事作成協力
- 山川 徹:東北大学文学部卒業後、教育出版社に就職し、大手出版社に転職。2社で学習参考書編集に携わり、多数のロングセラーを担当。現在は編集者としてのみならず、教育ジャーナリスト・コンテンツプロデューサーとしても活躍中。
- 神尾 雄一郎:開成中学校・高等学校をへて、慶應義塾大学総合政策学部にAO入試で合格。同大学卒業後、中央大学大学院にて公共政策修士号を取得。現在は、㈱ジーワンラーニング代表取締役として、志望理由書・小論文・面接をはじめとする学校推薦型選抜・総合型選抜の指導を高等学校などで担当。また、ディベートの指導者として、母校である開成中・高の弁論部監督も務める。著書に、『改訂第2版 書き方のコツがよくわかる 医系小論文 頻出テーマ20』『話し方のコツがよくわかる 医系面接 頻出質問・回答パターン40』(以上、KADOKAWA)、『どんなテーマでもスラスラ書ける 3ステップ小論文』(Gakken)などがある。





![お電話でのお問い合わせ 0120-65-1359 [10:00-20:00/土日祝も受付]](/wp-content/themes/tomas/img/header/tel_header.svg)




![最難関大学合格のチャンスを広げる学校推薦型選抜・総合型選抜[傾向と対策]](./img/index_ttl01.svg)
![最難関大学合格のチャンスを広げる学校推薦型選抜・総合型選抜[傾向と対策]](./img/index_ttl01_sp.svg)