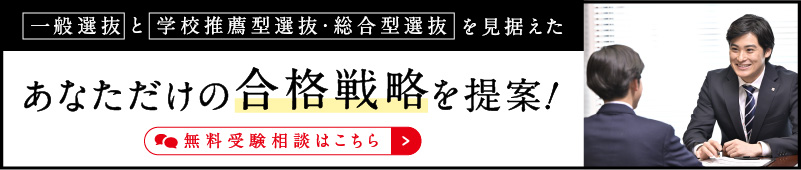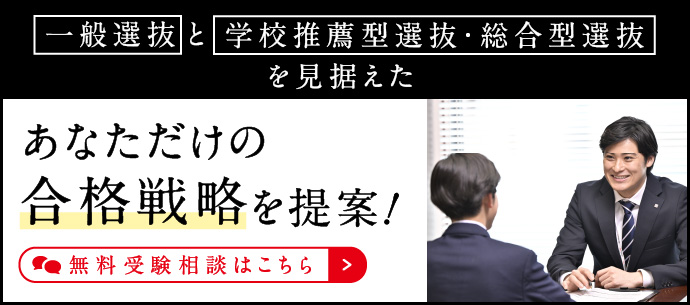学校推薦型選抜・
総合型選抜の概要

一般選抜/学校推薦型選抜・総合型選抜とは何か
「一般選抜」は、「知識・技能」で勝負できる方式
先に「一般選抜」を取り上げます。一般選抜とは、学科試験(ペーパーテスト)重視の受験方式です。
学科試験で試される「学力」は、おもに「知識・技能」をさします。「知識・技能」は、高校の授業を受けたり、自分で参考書や問題集を解いたりする過程、あるいは塾・予備校の集団授業や個別指導に参加する過程で身につきます。一般選抜は、基本的には知識・技能を試す学科試験だけで突破することが可能であり、出願時の煩雑な書類提出が義務づけられたり、学科試験以外の検査が課せられたりすることはありません。
「学校推薦型選抜・総合型選抜」は、「思考力・判断力・表現力」「態度」まで測る方式
一方、「推薦・総合型」は、「知識・技能」以外の多面的な学力を測る方式です。そこで試されるのは「思考力・判断力・表現力」と「態度」、正確には「主体性をもって多様な人びとと協働して学ぶ態度」です。大学側は、これらを評価するために、受験生に自身が取り組んできた学習や活動の成果を報告するよう求めます。
さらには、高校の「総合的な探究の時間」における取り組み姿勢や課題提出状況までが評価対象に含まれます。「総合的な探究の時間」とは、生徒自身にテーマを設定させ、そのテーマに関する情報収集・情報分析・結果報告を行なわせる授業です。教科の枠を超えて生徒がみずから学び考える力を養うことに目的が置かれています。
「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性をもって多様な人びとと協働して学ぶ態度」は「学力の3要素」とよばれます。
このように、推薦・総合型は、知識・技能を応用する力、学習[大学では「学修」]に向かう力、さらには人間性まで評価するという、一般選抜とはまったく方向性を異にする受験方式なのです。
「学校推薦型選抜」は「過去指向」、「総合型選抜」は「未来指向」を見る
ここまでの説明で「一般選抜」と「推薦・総合型」との違いがわかったと思います。では、「学校推薦型選抜」と「総合型選抜」にはどのような相違点と共通点があるのでしょうか。
相違点①:高校からの推薦の有無
学校推薦型選抜は、高校(学校長)による推薦が必要となる方式です。その種類には、以下の3つがあります。
| 指定校制 | 大学側が指定した高校ごとに割り当てられる入学定員枠にもとづいて出願する方式 |
|---|---|
| 内部進学 | 基準を満たしている大学の附属校生・系属校生が一般選抜なしで進学できる方式 |
| 公募制 | 高校での成績や取り組みとは無関係にみずからの意思で自由に出願できる方式 |
なお、指定校制・内部進学では、希望者数が入学定員枠よりも多い場合には校内選考が実施されます。
指定校制・内部進学で認められるのは「専願」、すなわち、1校のみの出願です。また、現役生のみが出願可能です。一方、公募制では、複数の大学への出願を可とする「併願」が認められている場合があり、既卒生も出願可能です。
一方、総合型選抜は、学校長による推薦は不要である方式です。ただし、その点を除けば、総合型選抜は公募制とほぼ同一だと考えて差し支えありません。
相違点②:アピールポイント
学校推薦型選抜は、過去の学習歴・活動実績をアピールする場です。したがって、出願時に提出する「志望理由書」(志望校に入学したい理由を記載する書類)、ならびに志望理由書にもとづいて実施される「面接」では、「過去に~ということに取り組んできた。だから、貴学を志望する」という点を強調する必要があります。言い換えると、学校推薦型選抜のアピールポイントは「実績」です。
一方、総合型選抜は、大学での学び[学修]に対する意欲と目的意識の強さ・前向きな姿勢をアピールする場です。したがって、志望理由書・面接とも、「入学後には~について学びたい。だから、貴学を志望する」という点を強調する必要があります。言い換えると、総合型選抜のアピールポイントは「ポテンシャル」です。
相違点③:提出書類・試験形態の違い
学校推薦型選抜と総合型選抜では、出願時に提出が義務づけられている書類や、実施される試験に違いがあります。以下のとおりです。
| 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 | |
|---|---|---|
| 志望理由書 | ○ | ○ |
| 学修計画書 | ― | ○ |
| 活動報告書 | ― | ○ |
| 面接 | ○ | ○ |
| 小論文 | △(公募制のみ) | ○ |
| プレゼンテーション | ― | △ |
| グループ ディスカッション |
― | △ |
| 学力検査 | ― | △ |
○:必ず提出・実施/―:提出・実施なし/△:提出・実施の場合あり
以下、上記の用語のうち説明を要するものについて解説します。
| 志望理由書 | 大学で学びたい研究を志した理由を表す書類。志望校、および学部・学科をみずからの意思で決め、出願という行動に至ったという積極的な理由・動機を説明する必要がある |
|---|---|
| 学修計画書 | 志望理由書で示された将来像の実現に向け、学内での学びと学外での学びに関するプランやビジョンを表す書類。自分が入学後に取り組みたい研究テーマと、自分が関心をもつ社会的課題に関する説明が求められる |
| 活動報告書 | 受験生が過去に取り組んだ活動を表す書類。各種大会やコンクールの成績、取得した資格や検定などについての記載が求められる |
| プレゼンテーション | 受験生自身がもつ考えを、試験官が理解できるよう、目に見える形で発表する試験。口頭での説明だけでなく、レジュメ・フリップなどの視覚的な資料の使用が認められる |
| グループ ディスカッション |
複数の受験生が1つのテーマについて話し合い、一定の結論を導き出す試験 |
| 学力検査 | 一般選抜における学科試験に相当する試験。ただし、一般選抜のような学科試験(ペーパーテスト)が課されることは少なく、専攻内容に関する知識を確認する「口頭試問」が、おもに理系で実施される。 |
学力検査では、教科学習能力の有無を測るために共通テストの受験が義務づけられる場合もあります。たとえば、早稲田大では、複数学部の総合型選抜で共通テストが課されます。また、慶應義塾大では、法学部の総合型選抜(FIT入試)A方式で口頭試問が実施されます。このような例からも、推薦・総合型はけっして学力不問の受験方式ではないのです。
相違点④:スケジュールの違い
以下のとおり、学校推薦型選抜と総合型選抜(共通テストが課されない方式の場合)では実施されるスケジュールがそれぞれ異なります。
| 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 | |
|---|---|---|
| 出願時期 | 11月~12月前半 | 9月 |
| 選考時期 | 11・12月 | 9~11月 |
| 合格発表時期 | 12月~翌1月前半 | 11月~12月前半 |
このように、総合型選抜のほうが学校推薦型選抜よりも早い時期から始まる点に注意してください。
共通点
ここまでは学校推薦型選抜と総合型選抜の相違点を比較してきましたが、一方ではそれぞれに共通する要素もあります。それは、受験生の在籍高校における成績が評価の対象になるという点です。
学校推薦型選抜と総合型選抜では、高校における教科の評定平均(現・学習成績の状況)が出願条件(出願の目安)に用いられます。「学習成績の状況」は0.7刻みでA~Eに分かれ、Aは「5.0~4.3」、Bは「4.2~3.5」、Cは「3.4~2.7」、Dは「2.6~1.9」、Eは「1.8以下」となっています。求められる成績の基準は大学によって異なりますが、難関校で求められる一般的な基準はおおむね4.0以上です。
もっとも、先述のとおり、学校推薦型選抜と総合型選抜ではともに「知識・技能」以外の要素も多面的・総合的に評価されますから、たとえ学習成績の状況が良好であるとしても、そのことだけで合格が保証されるわけではありません。先述の内容のうち、提出書類として最重要なのは「志望理由書」であり、試験形態として最重要なのは「面接」「小論文」です。志望校が設定する基準に沿ってこの「3点セット」をクリアすることが、推薦・総合型とも合否を分けるポイントです。
まとめ
ここまで推薦・総合型の相違点・共通点をくわしく述べてきました。ここまでの内容を要約すると、学校推薦型選抜は、受験生の活動実績や学業成績など、「現在までに実績を重ねてきた到達度」が評価される方式です。
一方、総合型選抜は、受験生の学業成績や活動実績が軽視されるわけではないものの、それ以上に、入学後に学問を修めるうえで欠かせない「表現力」や、卒業後に就く仕事で職場の中心的存在となるために欠かせない「リーダーシップ」など、未来に発現されるべきポテンシャル、すなわち「将来に実績がつくれる可能性」が評価される方式です。また、出願書類の種類が多く、選考方法もたくさんあります。
学校推薦型選抜・総合型選抜の出願戦略
推薦・総合型の概要をおさえたところで、以下、志望校の選び方、合格を確実に引き寄せる出願のポイント、および志望理由書や面接でアピールすることになる「自分の強み」の分析法を見ていきましょう。
志望校は、「学習成績の状況」を基準として決める
一般選抜は基本的には学科試だけの一発勝負ですから、合格可能性を上げるには、学力を構成する要素のうち「知識・技能」を試験本番までに最高潮にもっていく戦略が有効です。一方、推薦・総合型では、現時点での成績(学習成績の状況)を提出しなければなりません。
難関校の推薦・総合型には、成績優秀な受験生だけでなく、華々しい活動実績を誇る受験生も多数出願します。このような「強者」と対等に戦うのはしんどいことです。そこで、あえて無理をせず、自分の「学習成績の状況」よりも基準が低い大学への出願を優先してください。
また、学校推薦型選抜の指定校制と総合型選抜において「専願」と「併願」が選べる場合には、専願への出願を優先してください。併願を認める大学はえてして競争率が高くなりがちで、一般的に言うと高倍率であるほど合格可能性は低くなるからです。なお、競争率については、倍率が2倍未満であれば有望、6倍未満であれば勝負可能です。
さらに言うと、一般選抜と推薦・総合型との併願はあまりおすすめできません。先述のとおり、前者と後者では対策法がまったく異なり、頭の切り替えが大変だからです。また、一般選抜用の勉強と並行しながら推薦・総合型への出願に必要な書類を準備したり面接・小論文対策を行なったりすることもあまりにも大変だからです。対策にかける時間と労力が分散しないよう、どちらかの方式に絞るのが現実的だと言えます。
活動実績がイマイチだと不利なのか?
先述のとおり、推薦・総合型には、各種大会やコンクール出場経験などの輝かしい活動実績を誇る歴戦の「強者」が出願してきます。では、このような華々しい活動実績をもっている受験生でなければ合格できないのでしょうか。けっしてそんなことはありません。たとえ特筆すべき活動実績であるとしても、入学後の学びと直接結びつかない場合には、高く評価されることはないからです。
とはいえ、そもそも資格を満たしていなければ出願自体が不可能ですから、高校ではなんらかの活動実績を残しておくのが必要であることは言うまでもありません。しかし、その活動実績は、みなさんが想像するようにハイレベルなものである必要はないのです。
たとえば、資格取得・検定合格(英検、漢検、数検など)のような実績は、大学に入ってからもまじめにコツコツ勉強できることの証として十分なアピール材料となりえます。また、多くの受験生が経験しているはずの部活動・生徒会活動などの一般的な活動も、それらの活動から得られた経験が大学での学びと関連していることをアピールできれば、同じく立派な武器となりえます。
とくに、資格や検定は、出願後でも受験・受検し合格することも期間的に可能ですので、いまから実績をつくることも可能です。試験当日までコツコツと実績を積み重ねていってください。
「大学が合格させたい受験生」になるために必要な準備とは?
先述のとおり、学校推薦型選抜のメインは「過去」のアピール、総合型選抜は「未来」のアピールです。ただし、これらのアピールは、志望校側が掲げるいくつかの方針に沿っていない限り、加点対象とはなりません。では、受験生が踏まえなければならない大学側の方針とは、いったいどのようなものでしょうか。
その方針とは、以下のような3つのポリシーです。
| アドミッション・ポリシー | 「こういう受験生に合格してほしい」「入学後からこういう学生になってほしい」という方針 |
|---|---|
| カリキュラム・ポリシー | 「学生にこういうカリキュラムを学んでほしい」という方針 |
| ディプロマ・ポリシー | 「こういう学生を卒業させたい(=こういう学生に学位を授与したい)」という方針 |
これらの方針のうち、推薦・総合型ではとくにアドミッション・ポリシーが重視されます。志望理由書・面接では、このアドミッション・ポリシーに沿った「自分の強み」を強調する必要があります。
とはいえ、自分の強みを明確に意識し、なおかつ正確に言語化して伝えることができる能力の持ち主は、そこまで多くないはずです。しかし、以下のような点を洗い出していけば、アドミッション・ポリシーに結びつくあなたの強みが浮かび上がってきます。たとえば、教員養成系を志望する場合には、このような軸に沿って分析できるはずです。
| 放置できない社会的課題と、 自分の将来像とのかかわり |
例小学、中学と進むにつれ活字離れが加速し、高校に入ってからすっかり本ぎらいになる高校生が増えているという社会的課題を解決するとともに、その先にある大学での学びに堪えられる読解力を身につけさせる高校国語教諭になりたい。 |
|---|---|
| 過去の取り組み | 例古今東西の古典的名著を幼少期からたくさん読み、本の中の世界を味わうことの楽しさを体験してきた。 |
| 自覚している適性・能力 | 例読書の魅力を友人へ伝えるために工夫を凝らす過程で身についた説明能力と論理的思考力を有している。 |
| 志望校で学びたいこと | 例国文学・国語学だけでなく、関連する学問として哲学・歴史学・心理学も履修したい。 |
このような観点からあぶり出した自分の強みは、志望理由書の記載、面接の回答、小論文のアイディア着想などに直結するのです。





![お電話でのお問い合わせ 0120-65-1359 [10:00-20:00/土日祝も受付]](/wp-content/themes/tomas/img/header/tel_header.svg)




![最難関大学合格のチャンスを広げる学校推薦型選抜・総合型選抜[傾向と対策]](./img/index_ttl01.svg)
![最難関大学合格のチャンスを広げる学校推薦型選抜・総合型選抜[傾向と対策]](./img/index_ttl01_sp.svg)