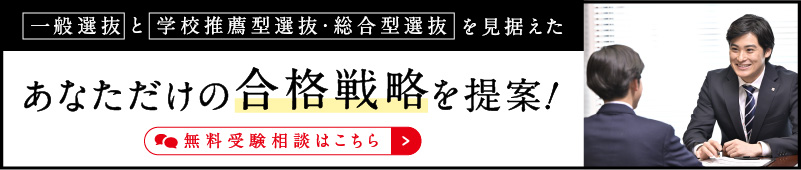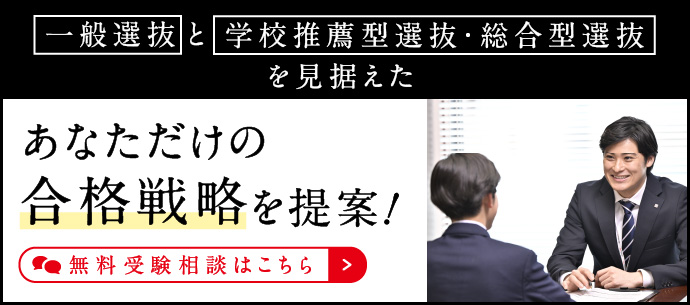慶應義塾大学
学校推薦型選抜・
総合型選抜の傾向と対策
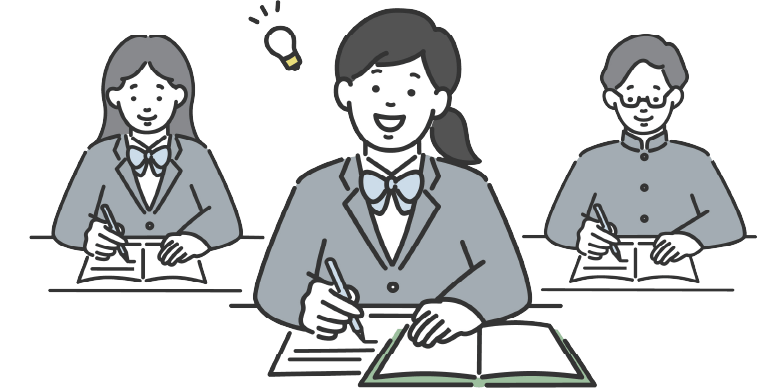
早慶における学校推薦型選抜・総合型選抜の特徴
自主応募制による推薦入学者選考―「文学女子」が大挙する
| 実施学部 | 文学部 |
|---|---|
| 募集人員 | 120人 |
| おもな特徴 | ●「第1志望」が出願資格 ●面接が課されない ●女子合格者が圧倒的に多い |
| こんな受験生におススメ | 文章力・語学力に自信がある女子受験生 |
この方式では、名称どおり「自己推薦書」の提出が必要で、併せて、受験生が在籍する学校の担任教員が記載すべき「評価書」の提出も求められます。「自己推薦書」は3項目、「評価書」は2項目の指示がそれぞれ含まれていて、各書類ともA4サイズで1ページ分です。このように、記載すべき分量は少なめです。
出願資格として注意しなければならないのは、「本学文学部を第1志望として入学を希望する国内の高校もしくは中等教育学校等の現役」という点です。すなわち、「併願不可・既卒生不可」です。なお、「学習成績の状況」の基準は4.1以上です。難関大における学校推薦型選抜の一般的な基準だと言えます。
これらの書類審査に加えて、「総合考査Ⅰ」と「総合考査Ⅱ」が実施されます。
「総合考査Ⅰ」では、与えられた課題文の内容理解にもとづいて分析・立論・表現させるという「課題型」の小論文とともに、英文和訳問題も課されます。語学力が試される出題だと言えるでしょう。
一方、「総合考査Ⅱ」は、与えられたキーワードに即して受験生自身の意見をエッセイ形式で書かせるという形式です。文章力が試される出題だと言えるでしょう。なお、慶大文学部は一般選抜でも「総合考査Ⅱ」と同形式の小論文を課しているので、一般選抜の小論文過去問も利用しましょう。
この方式では、小論文や記述試験と併せて実施されることの多い面接は課されません。ここからは、「文章が書ければよい。人物は見ない」というアドミッション・ポリシーがうかがえます。
この方式の競争率は例年2~3倍であり、一般選抜の競争率と同水準です。同学部一般選抜の厳しさを考慮すると、この方式は、一般選抜における競争よりも緩い「ねらい目」の試験だと言えるでしょう。
最後に、特筆すべきことがあります。それは、この方式における合格者男女比は、圧倒的に女子のほうが高いという点です。2023年度の合格者男女比は、なんと17:103(合格者数120人)でした。文章を書くことが好きでたまらないという「文学女子」の受験生が出願しやすい方式だと言えるでしょう。
FIT入試(A方式・B方式)―A方式とB方式は、もはや別の試験?
| 実施学部 | 法学部(法律学科・政治学科) |
|---|---|
| 募集人員 | 160人(法律学科・政治学科各80人) |
| おもな特徴 | ●「第1志望」が出願資格 ●A方式は活動実績重視型 ●B方式は成績重視型 |
| こんな受験生におススメ | ●地方在住の受験生はB方式で勝負 ●活動実績に自信がある受験生はA方式で勝負 |
この「FIT入試」は2006年度から実施されている、総合型選抜としては「老舗」の試験です。「A方式」と「B方式」の2通りがあります。
「B方式」は、全国を北海道・東北、北関東・甲信越、南関東、北陸・東海、近畿、中国・四国、九州・沖縄という7ブロックの地域枠に分ける方式であり、10人程度の合格者を各ブロックから均等に出します。この方式は、「入学志願者の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価・判定する」という、文部科学省が示している総合型選抜の目的・趣旨とぴったり符合しています。ここには、都市部に所在する一部の有名進学校からの合格者に偏らず全国各地から幅広く合格者を出したいという、大学側の強い意志が表れています。一方、「A方式」にはこのようなブロック分けはありません。
両方式とも、認められるのは第1志望のみであり、他校との併願は不可です。また、どちらも志望理由書の提出が必要です。なお、指定字数は2000字と、かなり多めの分量です。
これらが両方式の共通点ですが、相違点もかなりあります。以下、それぞれの方式の選考項目を挙げるとともに、とくにポイントとなる点につき説明していきます。
| A方式 | B方式 | |
|---|---|---|
| 第1次選考 (書類審査) |
志願者調書 志望理由書 自己推薦書Ⅰ・自己推薦書Ⅱ |
志願者調書 志望理由書 評価書 |
| 第2次選考 | 論述試験 面接 |
総合考査Ⅰ・総合考査Ⅱ 面接 |
第1次選考の書類審査について説明します。
A方式では「自己推薦書」内で活動実績の報告が求められる一方、B方式では活動実績の報告は求められない代わりに「評価書」を提出する必要があります。また、B方式には「学習成績の状況」に4.0以上という基準がある一方、A方式にはそのような成績基準はありません。
このように、教科学習の実績を重視するB方式は、学校推薦型選抜に近いタイプだと言えます。一方、「活動の具体的な内容」と「その活動で求められた役割」を活動実績として報告する必要があるA方式は、総合型選抜の王道タイプだと言えます。
第2次選考における記述試験のポイントを説明します。
A方式の「論述試験」では、摸擬講義の受講・講義の要点のまとめ・受験生自身の意見論述がセットになっています。45分という試験時間の中でこれだけ高密度な内容を2000字以上も記述させるという、きわめて高難度の試験です。
一方、B方式の「総合考査」では、「総合考査Ⅰ」では資料の読み取り、「総合考査Ⅱ」では小論文がそれぞれ課されます。試験時間は、それぞれ45分です。B方式のほうがA方式よりもトータルの試験時間は長いものの、記述試験としては比較的オーソドックスなタイプであり、A方式ほど難度は高くないと言えるでしょう。
第2次選考における面接のポイントを説明します。
A方式の面接は「口頭試問」です。この方式の口頭試問は、専攻内容に関する知識を確認するという一般的なタイプではなく、高度な質問に対して受験生自身の意見を述べさせるという応用型です。過去には、法律学科で「臓器売買の是非について」、政治学科で「女性議員の割合が低いことについて」という質問がなされました。知識があるだけでは不十分で、受験生自身に高い倫理観や深い洞察力がなければ答えられない、きわめて難度の高い質問だと言えるでしょう。
B方式における面接の形式は、複数の面接官(試験官)に対して受験生が1人で臨むという「個人面接」です。10分という短い面接時間内で面接官からの質問が1人の受験生に集中するので、その場での高い対応力が必要です。
なお、A方式の競争率は例年5~6倍であり、学科別では政治学科のほうが法律学科よりも若干低めです。一方、B方式の競争率は例年2倍超であり、A方式に比べてだいぶハードルが低いと言えそうです。
AO入試―「技術者の卵」である即戦力人材を求める
| 実施学部 | 理工学部 |
|---|---|
| 募集人員 | 若干名 |
| おもな特徴 | ●志望理由書の指定字数が多い ●技術的な裏づけを証明することが必要 |
| こんな受験生におススメ | 技術に関する広範なバックグラウンドをもつ受験生 |
この方式で提出を求められる書類には、「志望理由書」「活動実績を証明する書類または資料」などがあります。
この方式における志望理由書の指定字数は、法学部「FIT入試」と同様2000字であり、かなり多めの分量です。また、自己がもつすぐれた活動実績をアピールするための活動実績証明書類では、「あなたの全体像を表現しなさい」という項目につき、A4サイズで3枚分も記載しなければなりません。この項目がうまく書けるかどうかが合否のカギを握ると言われています。なお、この方式では、面接時に、数学・物理・化学の知識を要する「口頭試問」が課されます。
慶大理工学部のような難関理工系の総合型選抜で合格するためには、高校在籍時点ですでに技術的な裏づけを有していなければなりません。具体的には、専門学校生と同等の技術力や、理工系資格の取得が必要です。
大変酷な言い方ではありますが、技術力を有していることが証明できない受験生、あるいは理工系資格をもっていない受験生は、総合型選抜への出願をあきらめ、一般選抜に回ることを検討してください。酷な言い方ではありますが、「技術者の卵」としてすでにある程度完成された人材でなければこの方式で合格することは難しいはずです。
なお、この方式では2025年度から、書類審査と面接に加えて筆記試験が導入されます。対策すべきことが増える一方、「学力の3要素」のうち「知識・技能」が重視されることになるため、地道な努力によって合格可能性を上げる余地が増えそうです。
アドミッションズ・オフィスによる自由応募入試(AO入試)〔SFC〕―「頭」よりも先に「体」が動く人材を求める
| 実施学部 | SFC(総合政策学部・環境情報学部) |
|---|---|
| 募集人員 | 各150人 |
| おもな特徴 | ●合格させたい人物像がきわめて明確 ●出願資格に「学習成績の状況」の基準がない ●書類審査と面接のみ。小論文が課されない |
| こんな受験生におススメ | 他人が敷いたレールの上を歩くのではなく、むしろ自分でレールを敷こうとするようなバイタリティと行動力にあふれる受験生 |
総合型選抜を全国で初めて導入したのは、他ならぬ、このSFC(総合政策学部・環境情報学部)2学部です。両学部が設立された1990年度から始まった「AO入試」は、学力面の達成度だけでなく受験生の将来性や人間性までを評価の対象とし多様な受験生に門戸を開くという、総合型選抜のフォーマットとなっています。募集人員も各150人と多く、総合型選抜の代表格的な存在として認識されています。その分人気も高く、競争率は例年5~6倍にも上ります。また、両学部は、総合型選抜の先駆けとなっただけでなく、さまざまな分野を横断的に履修させるという学際教育の先駆けともなりました。
総合政策学部と環境情報学部はいわば「双子の兄弟」の関係にある一方、扱う学問分野はそれぞれ異なります。総合政策学部は政治学や政策学などを扱い、環境情報学部は科学技術やデザインなどを扱います。
しかし、対象領域が異なる両学部とも、合格させたい人物像は同じです。それは、「座学志向ではなく、実学志向の人物」「突き抜けた人物」「即戦力」です。反対に、「言い訳がましい人」「慎重な人」などは、合格するのが難しいはずです。
このように、両学部は、いろいろなことをバランスよくこなせる人材よりも、特定の分野に関して明確な適性をもつ人材を好む傾向が強いのです。両学部とも、受験生の「能力」よりも「適性」を重視していると考えられます。
この方式の大きな特徴は、出願資格に「学習成績の状況」の基準がないことです。すなわち、学業が優秀であるかどうかは直接には評価されません。また、他校との併願も認められていて、既卒生でも出願可能です。
この方式における書類審査用として必要な項目は、「志願者に関する履歴等」「志願者評価」「活動報告」「志望理由・入学後の学修計画・自己アピール」です。また、探究活動に関する資料を任意提出することも可能です。これらはすべてオンラインで申請する必要があります。
「志願者評価」は、客観的評価が可能な第三者の2人に書いてもらう必要がある項目です。客観的評価が書かれていない場合には評価対象とならないので、注意しましょう。
「活動報告」の項目では、単に取得資格や積んできた経験を記載するだけでは不十分です。その資格が社会的評価を有しているかどうか、積んできた経験が社会の発展にどの程度貢献したかまで伝えなければなりません。とくに、経験の中でも組織内で指導的役割を果たした経験が重視される傾向が強く、たとえば生徒会会長などの経験が有利に働きます。
「志望理由・入学後の学修計画・自己アピール」の項目には、文字どおり、大学での学修に関するプランを記載する必要があります。しかし、それだけでは他の受験生に差をつけることは難しいので、「社会人になってからも継続的に学び続ける意志がある」という点を盛り込んで記載内容の充実を図りましょう。
「自己アピール」は、2000 字以内の文章、および自由記述を書かせる項目です。自由記述の分量はA4サイズ2枚であり、形式は問いません。このスタイルは、就職活動時に書く必要があるエントリーシートに似ているので、就活本の記述が参考になるでしょう。
なお、両学部とも、大学側が指定するコンテスト・大会で所定の成績を収めたことを証明する書類の提出が可能な受験生については書類審査を免除する、という措置をとっています。具体的には、たとえば「三田文学新人賞 最終候補者」「日本数学オリンピック数学オリンピック 予選Aランク者」「高校生ビジネスプラン・グランプリ グランプリ・準グランプリ・審査員特別賞・優秀賞受賞者」などの受験生です。どのコンテスト・大会が該当するかを、前もって公式Webサイトで確認しておきましょう。
第1次選考である書類審査を通過した受験生が第2次選考に進みます。この選考で特徴的なのは、課されるのは30分の面接のみであり小論文は課されない、という点です。ここには、第1次選考通過に必要な書類作成能力が小論文作成能力を担保しているからわざわざ小論文を出題する必要はない、という大学側の考えが反映されています。
慶大SFCは、これまで数々の有名起業家を輩出してきました。そのため、両学部とも、自分で学んだり事業を展開したりすることができるような独創性のある学生を求めています。極端に言うと、起業準備のためなら学生が休学することをむしろ奨励している側面すらあります。実際、両学部には、企業準備や海外留学のために休学を申請する学生が多数存在します。
慶大の前身である慶應義塾の設立者・福沢諭吉は、『学問のすゝめ』という著書を刊行しました。一方、慶大SFCは、設立者の理念を引き継ぎ「起業のすゝめ」を説いているのです。
アドミッションズ・オフィスによる自由応募入試(AO入試)〔看護医療学部〕―難関であり、「コスパ」がよいとは言えない
| 実施学部 | 看護医療学部 |
|---|---|
| 募集人員 | 若干名 |
| おもな特徴 | ●一般選抜よりも競争率が高い ●B方式における「学習成績の状況」の基準が厳しい(4.5以上) ●SFCと同様、書類審査と面接のみ。小論文が課されない |
| こんな受験生におススメ | 明確な将来像をもっている受験生 |
看護医療学部で実施されているこの方式には、SFCと同じ「AO入試」という名称がついています。選考方法にもSFCとの共通点があり、第1次選考である書類審査をクリアした受験生が進む第2次選考では小論文が課されません。
一方、出願資格にはSFCとの相違点があります。具体的には、出願資格に「学習成績の状況」の基準がないSFCと異なり、2つある方式(A方式・B方式)のうち、B方式には「学習成績の状況」の基準が存在します。なお、その基準はなんと4.5以上です。
とても厳しいこのような成績基準が設定されていることからもわかるとおり、この方式は大変な難関です。そのレベルの高さは競争率にも表れており、2023年度については、A方式は64人の出願者に対して合格者は4人、B方式は36人の出願者に対して合格者は4人という結果でした。すなわち、競争率は10倍前後、です。一方、看護医療学部の一般選抜競争率は例年3倍程度です。
看護医療学部の学校推薦型選抜は、提出書類が多く手続きが煩雑だとはいえ、3科目の受験が必要となる一般選抜に比べれば相対的には楽です。そのため、看護医療系最高峰というブランド欲しさから、さほど学力の高くない受験生が大挙し過当競争が起きているのです。
このような点を考慮すると、この方式は「コスパ」が悪く、おすすめできません。この学部は一般選抜でめざすのが現実的だと考えてください。
一方、どうしても総合型選抜でめざしたいという受験生に助言したいことがあります。それは、面接で試験官から尋ねられる可能性が高い「どのような医療従事者(看護師、助産師など)になりたいかを具体的に話してください」という質問に答えられるよう、医療従事者としての将来像をあらかじめ明確にイメージしておいてほしい、ということです。「何となく看護師になりたい」というあいまいな志望理由しかもっていない受験生や、「なりたい医療従事者のイメージは入ってから考えます」というのんびりした受験生は、慶大看護医療学部が求めている人材ではないと認識すべきです。





![お電話でのお問い合わせ 0120-65-1359 [10:00-20:00/土日祝も受付]](/wp-content/themes/tomas/img/header/tel_header.svg)




![最難関大学合格のチャンスを広げる学校推薦型選抜・総合型選抜[傾向と対策]](./img/index_ttl01.svg)
![最難関大学合格のチャンスを広げる学校推薦型選抜・総合型選抜[傾向と対策]](./img/index_ttl01_sp.svg)