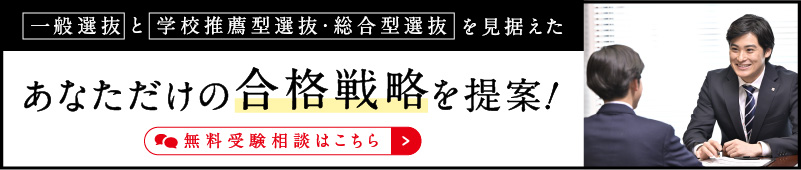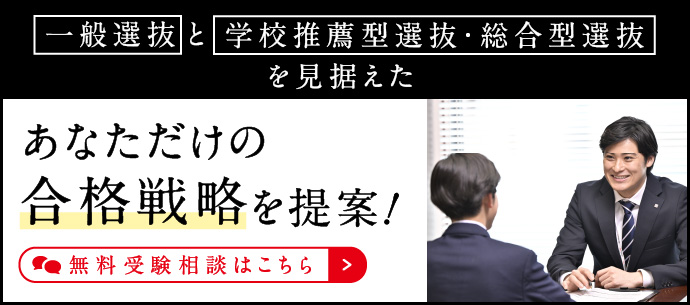早稲田大学
学校推薦型選抜・
総合型選抜の傾向と対策
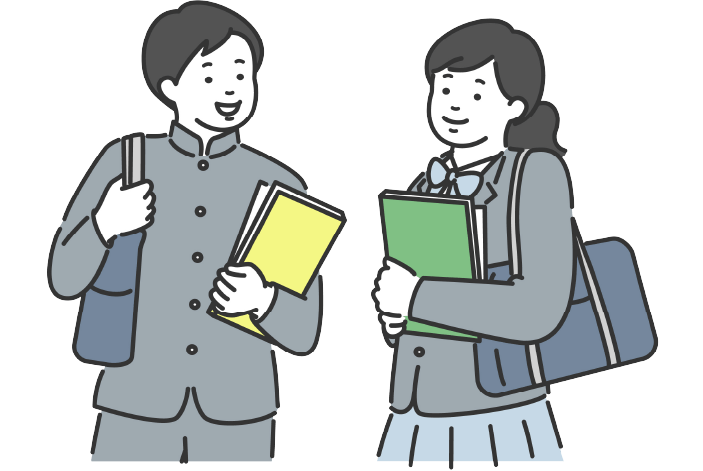
ここからは、総論として早慶、すなわち「早稲田大学」(以下「早大」と表記)、「慶應義塾大学」(以下、「慶大」と表記)の2校で実施されている学校推薦型選抜・総合型選抜の「共通点」「相違点」を先に示し、次に各論として「早稲田大学」「慶應義塾大学」各校の学校推薦型選抜・総合型選抜に関する具体的な内容を説明していきます。
早慶における学校推薦型選抜・総合型選抜の特徴
早慶の学校推薦型選抜・総合型選抜における共通点
共通点①:求められるレベルの高さ
当然ですが、私立大の最高峰である早大・慶大の両校では、一般選抜と同様、学校推薦型選抜・総合型選抜でもきわめて高い「達成度」と「将来性」が要求されます。両校に出願する受験生の多くは、各地区の公立トップ進学校生や、国・私立中高一貫校の上位層です。出願時には、これらのハイレベルな受験生と戦う覚悟が必要です。
共通点②:募集人員に対する枠のせまさ
両校とも、全体の募集人員に対して学校推薦型選抜・総合型選抜の募集人員がとても少なく、大変な難関です。募集人員最大の受験方式は慶大SFC(総合政策学部・環境情報学部)の総合型選抜であり、各150人です。次に募集人員が多いのは早大国際教養学部の総合型選抜であり、100人となっています。しかし、これらは例外であり、ほかの受験方式は2ケタ台、もしくは「若干名」という少なさです。
共通点③:早い段階での取り組みの必要性
先述のとおり、早慶の学校推薦型選抜・総合型選抜では、高い「達成度」と「将来性」が要求されます。これらを身につけるには膨大な時間と労力がかかるので、修得するにはどんなに遅くとも高2までには準備しておくべきです。高3からの取り組みでは間に合いません。すなわち、早慶の学校推薦型選抜・総合型選抜には高1・2という非受験学年からの対策が必要なのです。
共通点④:学部によっては「一点突破」が可能
このように、早慶の学校推薦型選抜・総合型選抜合格を勝ち取るためには高い総合力が必要です。しかし、すべての学部で合否が総合力だけで決まるわけではなく、自分がもつ突出した能力や適性を猛烈に押し出すことによる「逆転合格」「一点突破」が可能な学部、および受験方式もいくつか存在します。以下が、その例です。
| 早大複数学部で実施されている 「地域探究・貢献入試」 (旧「新思考入試」) 実施学部:法学部・商学部・ |
共通テストが課されるものの、3教科受験でOK。すなわち、「教科学習」の取り組みによる勝負が可能 |
|---|---|
| 早大国際教養学部の総合型選抜 | 英語外部試験のスコア提出が求められるものの、書類審査のウェイトは軽い。120分の筆記審査である「Critical Writing」が勝負 |
| 慶大SFC (総合政策学部・環境情報学部)の 総合型選抜 |
出願資格に「学習成績の状況」の基準がない。すなわち、たとえば「ビジネスコンクール入賞」などの目覚ましい実績による勝負が可能 |
早慶の学校推薦型選抜・総合型選抜における相違点
相違点①:学校推薦型選抜の扱いに関する違い
早大の学校推薦型選抜は指定校推薦のみであり、公募制推薦は存在しません。すなわち、早大で実施されているのは総合型選抜のみです。
一方、慶大には学校推薦型選抜が存在します。具体的には、文学部で公募制推薦(自主応募制による推薦入学者選考)が実施されています。
相違点②:共通テストの扱いに関する違い
早大の総合型選抜では、学部横断で実施される「地域探究・貢献入試」において共通テストの受験が義務づけられています。一方、慶大の総合型選抜には、共通テストを課す方式は存在しません。
相違点③:重視される評価軸に関する違い
早大の学校推薦型選抜・総合型選抜で大きなウェイトが置かれるのは、活動実績や学修計画のような現在の総合型選抜で重視される項目よりも、「学習成績の状況」や調査書のような従来のAO入試で重視されていた項目、すなわち、「達成度」に関する項目です。
一方、慶大の学校推薦型選抜・総合型選抜で重視されるのは、「表現力」や「リーダーシップ」のような「将来性」に関する項目です。
相違点④:「多様性」のとらえ方の違い
早大で重視している「多様性」は、法学部・商学部・文化構想学部・文学部・人間科学部・スポーツ科学部で「地域探究・貢献入試」が実施されているように、「学生の出身地の多様性」です。
一方、慶大で重視している「多様性」は、総合考査、模擬講義、口頭試問など、選考方法のバリエーションが豊富であるように、「学生の選考方法の多様性」です。
地域探究・貢献入試―地方在住者こそ受験したい
| 実施学部 | 法学部・商学部・文化構想学部・文学部・人間科学部・スポーツ科学部 |
|---|---|
| 募集人員 | 各若干名 |
| おもな特徴 | ●合否判定に共通テストが用いられる ●地方在住者への広い門戸が開かれている |
| こんな受験生におススメ | 地域貢献に関するクリアなビジョンをもち、入学後も地域について積極的に学ぶモチベーションがある受験生 |
旧名称の「新思考入試」から現名称に変更されてからも、この方式の目的・主旨に変更はありません。
この方式では、たとえばボランティア活動、ワークショップ、就業体験プログラム(インターンシップ)など地域で実施されているイベントにかかわった実績が求められるだけでなく、入学後も「人口減少」「高齢化」「伝統産業の衰退」「若年層の都市部への流出」など地域が抱える課題への意識をもち、これらの解決に取り組む姿勢・意欲が問われます。したがって、志望する段階ですでに、入学後からの具体的な活動に関する明確なイメージが描けていなければなりません。
また、入学後の取り組みに対するイメージと同時に、卒業後のキャリア(将来像)についても明確なイメージをもっていることが必要です。たとえば、将来像としては、「地元○○県の県庁職員となり、行政の立場から障碍者のサポートに務めたい」などという内容が考えられます。
この方式では、2次選考時に「総合試験」という名称の筆記試験が課されます。試験内容は、たとえば、発表された行政データの中から特徴的な自治体を取り上げ、そのデータを分析したうえで提案する、というものです。
2次選考の合格発表後には、共通テストの受験が課され、その成績にもとづいて最終合格が発表されます。先述のとおり、受験教科は3教科でかまいません。ただし、最低でも8割の得点が求められます。
上述のとおり、他大学との併願が可能です。しかし、早大総合型選抜の花形ともいえる方式であり大変な難関ですから、専願に絞るのは危険です。上位国公立大、上智大、ICU(国際基督教大)、GMARCHなどとの併願も検討しましょう。
このように、地域貢献に対する高いモチベーションをもって臨む必要がある方式ですから、自分が住む地域への強い興味・関心を有する人が多い地方在住の受験生に向いている試験だと言えます。
全国自己推薦入試―「情熱」こそが最後にモノをいう
| 実施学部 | 社会科学部 |
|---|---|
| 募集人員 | 35人 |
| おもな特徴 | ●英語外部試験のスコア提出が求められる ●活動記録報告書の提出が求められる |
| こんな受験生におススメ | 学ぶ意欲と「早稲田愛」にあふれる受験生 |
選考方法の流れは第1次選考⇒第2次選考です。第1次選考時に提出が求められる書類のうち、志望理由書の指定字数は800字程度という、ごく標準的な分量です。併せて、「学習成績の状況」の提出も求められます。基準は4.0以上です。
書類審査では、英語外部試験の成績が確認されます。たとえば、英検CSEスコアの基準は1950以上、すなわち、高校卒業レベルに該当する英検2級レベルです。早大をめざすような受験生にとってはさほど高いハードルではないはずです。
活動記録報告書の提出も求められます。この書類の記載内容としては、学芸系の実績、生徒会活動の実績などが重視される傾向にあります。記入例が公式Webサイトで確認できますので、目を通しておきましょう。
第2次選考では、面接が課されます。入学後から積極的に学ぶ強い意欲があることを最大限にアピールしてください。
また、小論文も課されます。出題形式は、唯一のヒントである設問指示文中のキーワードに即して構想を練り、答案上で立論していくというオーソドックスな「テーマ型」です。この形式では、書くべきアイディアを思いつくかどうかで勝負が決まります。『書き方のコツがよくわかる ●●系小論文 頻出テーマ▲▲』シリーズ(KADOKAWA)や『大学入試 小論文の完全ネタ本 ●●系編』シリーズ(文英堂)などのいわゆる「ネタ本」を使って対策しておけば十分です。
ここまで見てきたように、この方式は、提出書類が多かったり小論文が課されたりして対策すべきことが多い一方、1つひとつの試験のハードルはさほど高くないという点で、従来型であるAO入試のようにオーソドックスなスタイルであると言えます。「一点突破」で勝負せず地道に対策していけば、十分に合格がねらえます。
この方式を実施している社会科学部は、「早稲田にどうしても入りたい」という受験生が多い学部です。そのため、この方式では、学ぶ意欲だけでなく、「どうしても早稲田でなければならない」という、志望校に対する強い意欲と情熱のアピールが他学部以上に重要です。
この方式の競争率は、例年約7~8倍という高い水準にあります。一方、一般選抜の競争率は例年約10倍前後です。総合型選抜のほうが、やや競争が緩めだと言えます。
AO入試(4月入学・国内選考)―とにかく「英語」で決まる
| 実施学部 | 国際教養学部(国際教養学科) |
|---|---|
| 募集人員 | 100人 |
| おもな特徴 | ●英語外部試験のスコア提出が求められる ●英語の筆記審査が課される |
| こんな受験生におススメ | 突出した英語力を有する受験生 |
この方式の第1次選考のために提出する志望理由書(Application Form)には、3つの記載項目があります。1つ目は「中学卒業以降の国際体験」、2つ目は「中学卒業以降に一番力を入れて取り組んだこと」、3つ目は「Essay(自身の経験と将来の夢をつなぐ場として本学部を選んだ理由)」です。いずれも日本語による記載であり、指定字数はそれぞれ500字以内、300字以内、800字以内です。トータルの分量は多めですが、項目ごとの指示が明確ですから比較的書きやすいはずです。
また、「体験・取組内容証明書」という活動記録報告書の提出も求められます。社会科学部の「全国自己推薦入試」ではこの書類への記載内容が重視される一方、この方式におけるウェイトは比較的軽めです。
社会科学部の「全国自己推薦入試」と同様、この方式でも英語外部試験の成績が確認されます。たとえば、英検CSEスコアの基準は2300以上、すなわち、英検準1級レベルです。一般的には高い要求レベルですが、この方式に臨む受験生であれば当然クリアすべき水準です。
第1次選考合格者には、第2次選考として筆記審査が課されます。その内容は「Critical Writing」(120分)であり、入学試験要項では「与えられた資料を理解し分析したうえで自分の考えを表現する審査」と説明されています。出題形式としてはエッセイ・ライティングがある一方、一般選抜で見られるようなリーディングの出題もあります。後者については、一般選抜も併願する受験生であれば特別な対策は不要でしょう。
2023年度競争率は倍率3.8倍でした。ちなみに、一般選抜の2023年度競争率は2.7倍でした。この数字は、早大文系他学部の競争率に比べるとやや低めの部類に入ります。しかし、かといって競争が緩いわけではなく、その大前提としてとにかく高い英語力をもっていることが必要だという点で相当ハイレベルな戦いを強いられると考えましょう。
早稲田建築AO入試[創成入試]―実技も課される
| 実施学部 | 創造理工学部(建築学科) |
|---|---|
| 募集人員 | 25人 |
| おもな特徴 | 鉛筆によるドローイングが課される |
| こんな受験生におススメ | 建築に対する情熱と、最低限のデッサン能力を有する受験生 |
この方式では、2024年度までは「数学Ⅰ・A・Ⅱ・B」まで履修していれば出願可能です。すなわち、「数学Ⅲ」の履修は不要なのです。一般選抜であればほとんどの大学・学部で数学Ⅲを課す理工系で数学Ⅲが免除される、しかも早大ほどのハイレベルな大学を数学Ⅲなしで受験できるというのは、きわめて異例の条件です。実際、創造理工学部の一般選抜では数学Ⅲが課されています。
一方、この方式では、出願資格に「理科の合計修得単位数が10単位以上」という条件を設けています。すなわち、理科を専門科目・基礎科目込みで3科目以上履修することが必要となります。この点から、「数学はほどほど・理科が得意」という受験生が勝負をかけるのに向いている方式だと言えます。
ただし、この措置は2024年度で終了し、2025年度からは出願資格として「数学Ⅲ・C」までの履修が必須となります(2022年度からの教育課程変更により、履修範囲に「数学C」も含まれることとなりました)。数学Ⅲ・Cを履修していないと出願資格が得られなくなるので、注意が必要です。
第1次選考時には「志願者自己報告書」「活動実績報告書」「推薦状」の提出が必要です。また、書類審査通過者に対する第2次選考では、課題として「自己PR資料」が与えられます。さらには、第2次選考では、筆記試験、面接まで課されます。このように、この方式は選考方法が多種多様です。ここには、将来的に建築のエキスパートとなるのにふさわしい高い専門性と強い意欲を有する人材を入学させたいという、大学側の強い意志が表れています。
この方式の選考方法における最大のポイントは、第2次選考の筆記試験です。筆記試験は、入学試験要項では「鉛筆によるドローイングと文章による提案・表現」と説明されています。
「鉛筆によるドローイング」は、要するに「デッサン」です。この試験は創造理工学部の一般選抜でも課されており、同学部がこの試験を重視していることがわかります。たしかに、この試験は、絵を描くことに自信がない受験生にとっては大きな関門です。
しかし、この試験のために専門的なデッサン技術を習得する必要はありません。この試験で重視されるのは、技術よりも、造形という行為をつかさどる能力、たとえば空間描写力・思考力・論理構築力などです。たとえ技術的に稚拙であっても、自分が思い描いているイメージを的確に表現することができれば問題ありません。
「文章による提案・表現」は、要するに「小論文」です。ただし、建築に対する受験生自身の価値観が問われるという高度な出題であり、初見の状態からいきなり書くことはほぼ不可能です。建築家が書いた本を読んだり、すぐれた建築物を見学して感想を記したりするなど、入念に事前準備しておきましょう。
FACT選抜入試―向き・不向きがはっきり分かれる
| 実施学部 | 人間科学部 |
|---|---|
| 募集人員 | 若干名 |
| おもな特徴 | 高度な事前課題が与えられる |
| こんな受験生におススメ | ●高校でまとめたレポート・課題に高評価がついた経験をもつ受験生 ●理科が得意で、国語力にも自信がある受験生 |
ここでは、帰国生向けである「出願資格B」ではなく、一般の受験生向けである「出願資格A」を取り上げます。
この方式における提出書類は志望理由書のみであり、推薦状などは不要です。志望理由書の指定字数は1200~1500字であり、学修計画を記す欄もありますが、書かなければならない分量は少なめです。
一方、出願資格はかなり細かく規定されています。1浪までの既卒生でも出願可能とされるほか、全体の「学習成績の状況」が3.9以上で、国語および理科のそれぞれ3科目以上を履修し、国・理で履修したすべての科目を合わせた「学習成績の状況」が4.1以上という条件が課されています。また、「数学Ⅰ・A・Ⅱ・B」をすべて履修しているという条件も加えられています。ここからは、大学側が国語・理科の学力を重視し数学の学力も考慮するというアドミッション・ポリシーをもっていることがうかがえます。
この方式の選考方法における最大のポイントは、出願時に提出すべきレポートである「事前課題」です。この出題はとても高度かつ特殊であり、一例を挙げると、「ナイフだけで平面図形の面積を求めよ」などという出題です。ここからは、知識量はさほど求められない代わりに、初見で出題意図を把握する判断力や、与えられた条件にもとづいて立論する思考力、また、その立論を筋道立ててまとめていく国語力が必要であることがわかります。さらに言うと、この出題タイプは、公立中高一貫校の「適性検査」に似ています。そういう意味では、このようなスタイルで受検した経験をもつ公立中高一貫校生には有利です。また、理科の実験レポートをまとめた経験がある人にも有利です。
反対に、このような出題になじみがない受験生、理科の実験レポート作成経験がない受験生などにとっては、きわめて不利です。合格のためには、先に挙げた「判断力」「思考力」「国語力」などの能力もさることながら、それ以上に、「そもそもこういう出題に抵抗がないかどうか」という「適性」の有無が重要です。公式Webサイトで閲覧可能な過去問を見て出願するかどうかを見きわめましょう。
この方式では「事前課題」に目が向きがちですが、事前課題以外にもさらに、120分の論述試験、20分の面接まで課されます。ハードな試験だらけの早大総合型選抜の中でもとりわけタフな受験方式だと言えるでしょう。
なお、競争率は例年2倍未満であり、例年5倍程度の競争率となる一般選抜に比べると、競争はやや緩めです。そういう意味では、ハードルが高く受験者数が少ない分、適性をもつ受験生であれば一般選抜で受けるよりも有利だと言えます。
スポーツ自己推薦入試―特定の種目で頂点を極めた受験生が集う
| 実施学部 | スポーツ科学部 |
|---|---|
| 募集人員 | 60人 |
| おもな特徴 | ●スポーツにおける突出した実績が求められる ●「学習成績の状況」の基準は低め |
| こんな受験生におススメ | ●高校でまとめたレポート・課題に高評価がついた経験をもつ受験生 ●スポーツで全国大会出場実績があり、小論文を書くことに抵抗がない受験生 |
先述のとおり、早大スポーツ科学部の総合型選抜としては「地域探究・貢献入試」という方式もあります。一方、ここで取り上げる「スポーツ自己推薦入試」はそれとは別枠であり、競技活動の実績を評価する方式です。
同学部で実施されているスポーツ関連の総合型選抜には「Ⅰ群」「Ⅱ群」「Ⅲ群」の3つの方式があり、この「スポーツ自己推薦入試」はⅢ群に属します。Ⅰ群は「トップアスリート入試」、Ⅱ群は「アスリート選抜入学試験」であり、それぞれ若干名を募集します。ただし、Ⅱ群は公募制ではない点に注意してください。
「スポーツ自己推薦入試」の出願資格として、入学試験要項には「あらゆるスポーツ種目で全国大会出場などの競技成績を有する者」という記載があります。ここで挙げられている「競技成績」として想定されているレベルは、高校日本代表、もしくはその候補者です。出願資格として具体的に考えられるのは、たとえば「高校野球甲子園大会でベスト8入りしたチームの所属」「高校総体での優勝」「国際大会への出場」などです。このように、評価基準はきわめて高く、国内だけでなく海外でも通用するレベルの競技歴が求められます。したがって、たとえどんな高い身体能力・学びへの強い意欲を受験生が有していたとしても、輝かしい競技実績がなければ合格することは不可能です。
なお、出願資格として求められる全体の「学習成績の状況」の基準は3.5以上と、他の受験方式に比べると緩めです。また、例年の競争率は約3倍と、一般選抜の例年の競争率と同程度であり、特別に高いわけでもありません。トップレベルのアスリートであれば競技実績だけで「一点突破」することが十分可能だと言えるでしょう。
第2次選考では小論文が課されます。出題形式は典型的な「テーマ型」(唯一のヒントである設問指示文中のキーワードに即して構想を練り、答案上で立論していくというタイプ)であり、同学部の一般選抜で課される小論文とよく似ています。先述した「ネタ本」を使いながら、一般選抜の過去問も対策として利用しましょう。





![お電話でのお問い合わせ 0120-65-1359 [10:00-20:00/土日祝も受付]](/wp-content/themes/tomas/img/header/tel_header.svg)




![最難関大学合格のチャンスを広げる学校推薦型選抜・総合型選抜[傾向と対策]](./img/index_ttl01.svg)
![最難関大学合格のチャンスを広げる学校推薦型選抜・総合型選抜[傾向と対策]](./img/index_ttl01_sp.svg)