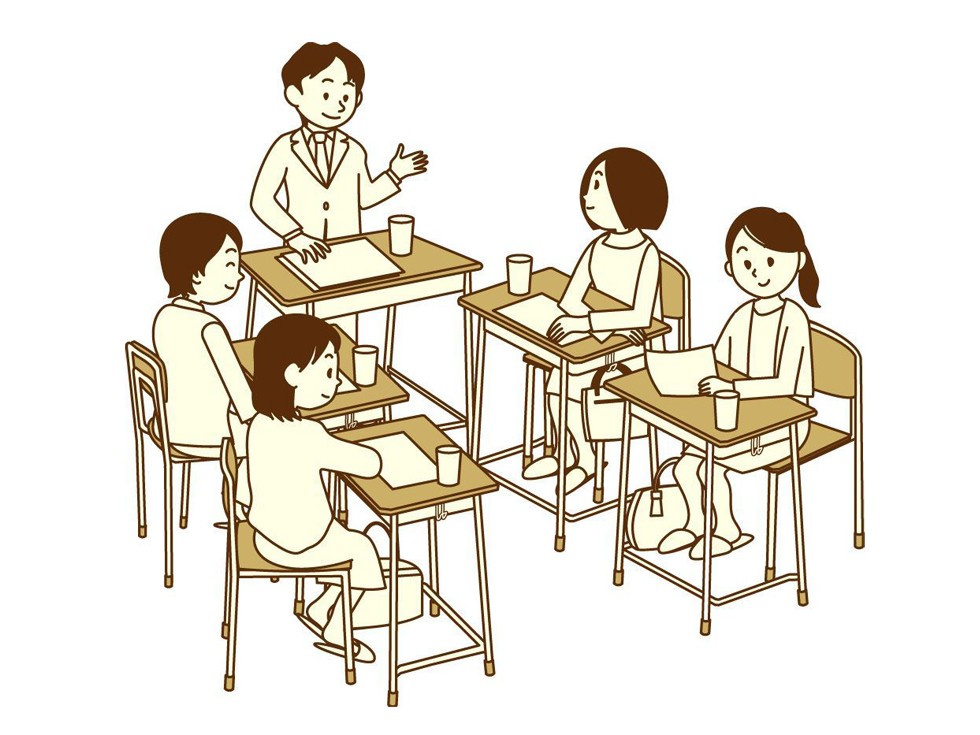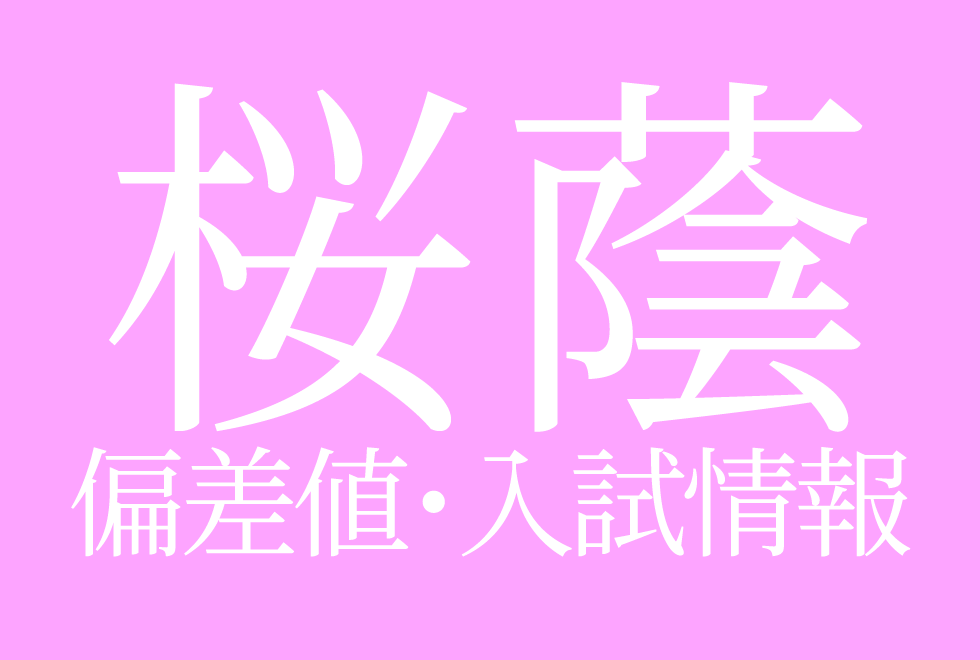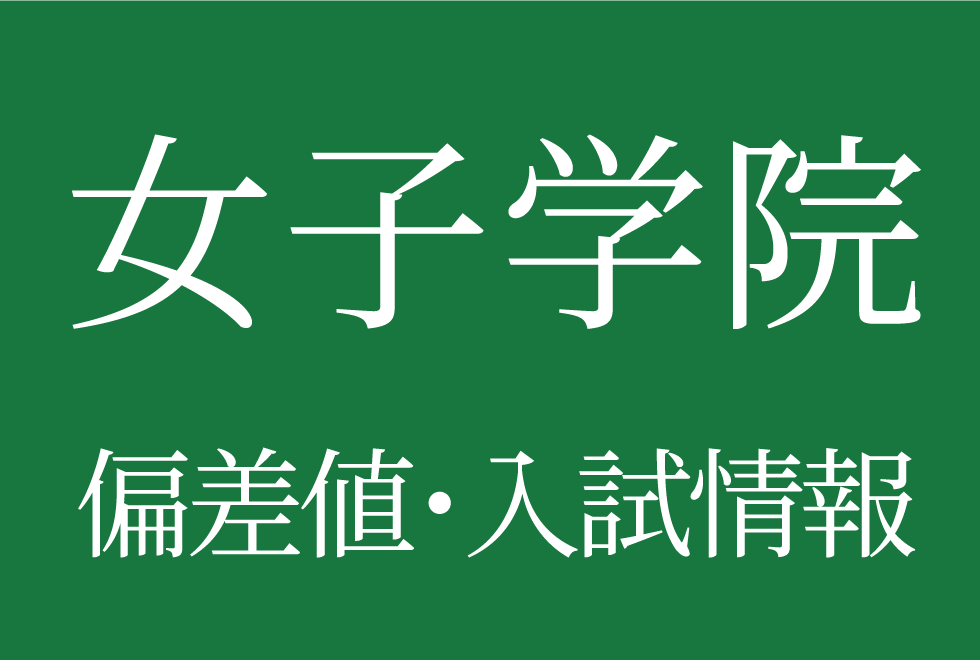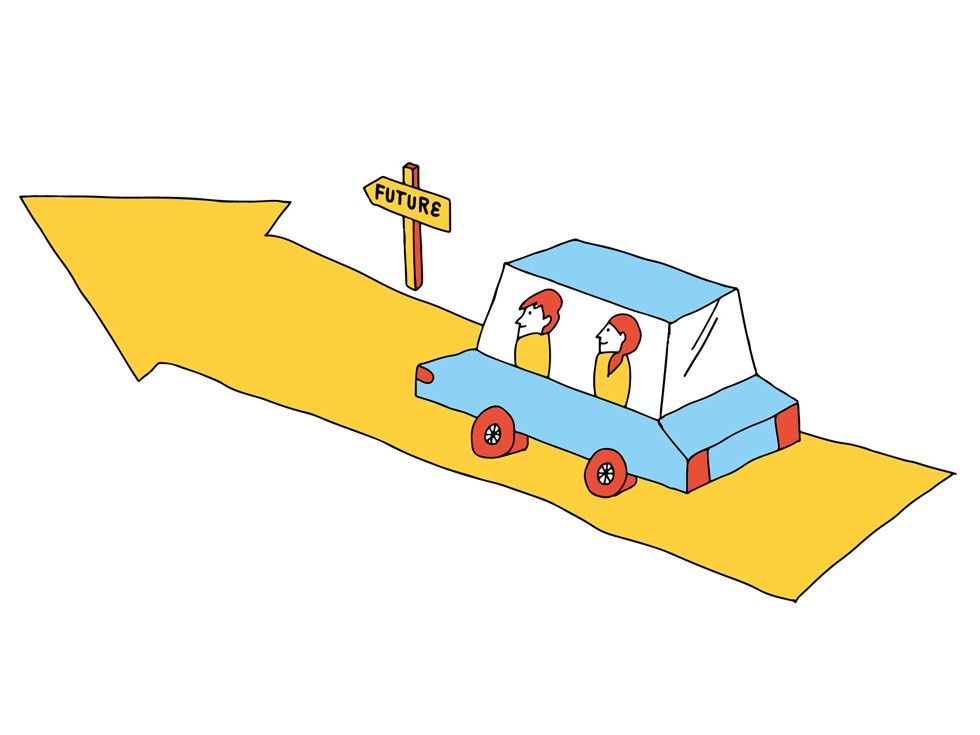


ゲーム、スマホ、習い事、塾、中学受験などで、子どもと考え方が違うとき、どうすればいい?
子どもが成長するにつれて、親子の考え方の違いが表面化することが増えます。
例えば、ゲーム、スマホ、タブレット、YouTube、SNSなどについてです。
または、習い事、部活動、塾、中学受験……。
そして、もっと先の話としては高校受験、大学受験、就職などの進路についてです。
あるいは、ある日突然、子どもが「もっとお小遣いが欲しい」「ちょっとくらいお化粧したい」「友達と子ども同士で○○に行きたい」などと言い出して、そこで親子の考え方が違ってくる場合もあります。
こういうことは、子どもが成長すればするほど多くなりますが、健全に成長している証でもあります。
かえって、こういうことが何も言い出せないほうが心配とも言えます。
では、このようなことで親子の考え方が違うときは、どうしたらいいのでしょうか?
私の考えをひと言で言えば、共感的かつ民主的な話し合いをすることが大事です。
ゲームについて、どのように話し合えばいい?
例えば、ゲームを例にとってみます。
ほとんどの親は、「ゲームは悪いもの。できるだけやらせたくない。勉強や運動など、もっと有意義なことに時間を使わせたい」と思っています。
そのため、ゲームのことで子どもを叱りがちになります。
ところが、子どもたちにとって、ゲームは親が思っている以上に大切なものなのです。
彼らは、心の中で「ゲームほど楽しいものはない。生き甲斐でありストレス解消にもなる。ゲームで身につくものも多い。やらないと友達との会話にもついていけない」と思っています。
ですから、ゲームのことで親に叱られてばかりいる子は、「自分のことはどうせ理解してもらえない。言っても無駄だ」という思いを強く持つようになります。
そして、親と顔を合わせたり会話をしたりすることを避けるようになり、孤独を感じるようになります。
こういうパターンは実に多いのですが、これには親が考える以上に大きなリスクがあります。
なぜなら、ゲーム中毒・依存症のリスクは、家族とのコミュニケーションが不足するなどの孤独な状態で一層高まるからです。
そうならないために、まず親のほうから歩み寄る必要があります。
具体的には、ゲームを通して親子のコミュニケーションが深まるようにすることが大事なのです。
ステップ1:親の方から歩み寄って良好な雰囲気を作る
子どもたちは、ゲームの中で目標を持って努力しています。ステージをクリアしたり、レベルが上がったりすることで、達成感を感じています。
ですから、そういう話を子どもと同じ目線で聞いて、ほめてあげれば子どもは非常に喜びます。「自分のがんばりを認めてもらえた。自分が大好きなことを受け入れてもらえた」と感じ、親への信頼感が高まります。
親が子どもと一緒にゲームをやらせてもらうのもいいと思います。
そうすれば、内容について理解できますし、おしゃべりの材料にもなります。
普段は親とあまり会話しない子でも、ゲームの話なら乗ってくることがありますので、ぜひ、やってみてほしいと思います。
そして、そういう良好な雰囲気を作った上で話し合いに進みます。
ステップ2:子どもの本音を共感的に聞く
話し合いで大事なのは、まず子どもの話を共感的に聞くことです。
例えば、子どもが「やらないと友達との会話にもついていけない」と言ったら、「たしかにそうだよね」と共感します。
とにかく、子どもが本音を話しやすいようにして、その全てを共感的に聞きましょう。
その後で、親が心配していることなどを話します。
例えば、勉強や運動の時間がなくなる、視力のことが心配、有害な内容だと心配、課金のことが心配、などです。
不思議なことに、最初に親が子どもの話を共感的に聞いていると、子どもも親の話に耳を傾けてくれるようになります。
このような共感的な雰囲気の延長線上で、次のルール作りの段階に進みます。
ステップ3:共感的かつ民主的な話し合いでルールを作る
ここでも、お互いの話を共感的に聞き合いながら、民主的に決めていくことが大切です。
いわば外交交渉のようなものです。主張したいことは主張し、譲れるところは譲り、お互いが納得できる着地点を見つけていきます。
ルールが決まったら、ホワイトボードに書いて明文化しておきます。
このように、子どもがルール作りに関わることが大事です。この過程を経てはじめて、ルールを守る気になれるのです。
一方的に押しつけられたルールは決して守られません。
結論がどうなるにせよ、共感的かつ民主的な話し合い自体が大事
ここまで、一つの例としてゲームについて書いてきましたが、スマホ、YouTube、習い事、塾、部活動、中学受験、就職、進路など、ほかの問題でも全て基本的には同じです。
つまり、共感的かつ民主的な話し合いをするということです。
そして、このような話し合いを親子ですること自体が、非常に教育的な効果が高いのだと、私は強調したいと思います。
なぜなら、こういう話し合いによって、子どもは「親は自分の話を真剣に聞いてくれている。自分のことをわかろうとしてくれている。自分のことを一生懸命考えてくれている」と感じることができて、親への信頼感が高まるからです。
話し合いの結果、スマホを買うにせよ買わないにせよ、中学受験するにせよしないにせよ、どちらの方に進んだとしても、「親子の信頼関係」という鉄壁の安全装置を携えながら進むことができるのです。
信頼があれば、新たな考え方の違いが出てきても、あるいは予期せぬ問題が発生したとしても、どんなときにも安心して親に相談できるようになります。
これほど大事なことはありません。
だからこそ、私は親子で共感的かつ民主的な話し合いをすること自体が大切だと強調したいのです。
そして、もう一つ、こういう話し合いを経験している子どもは、「人と考え方が違うときは共感的かつ民主的な話し合いが大事だ」ということを身をもって学んでいるといえます。
これもまた非常に重要なことであり、子どものこの後の人生にとって得難い学びになるはずです。
親野先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。