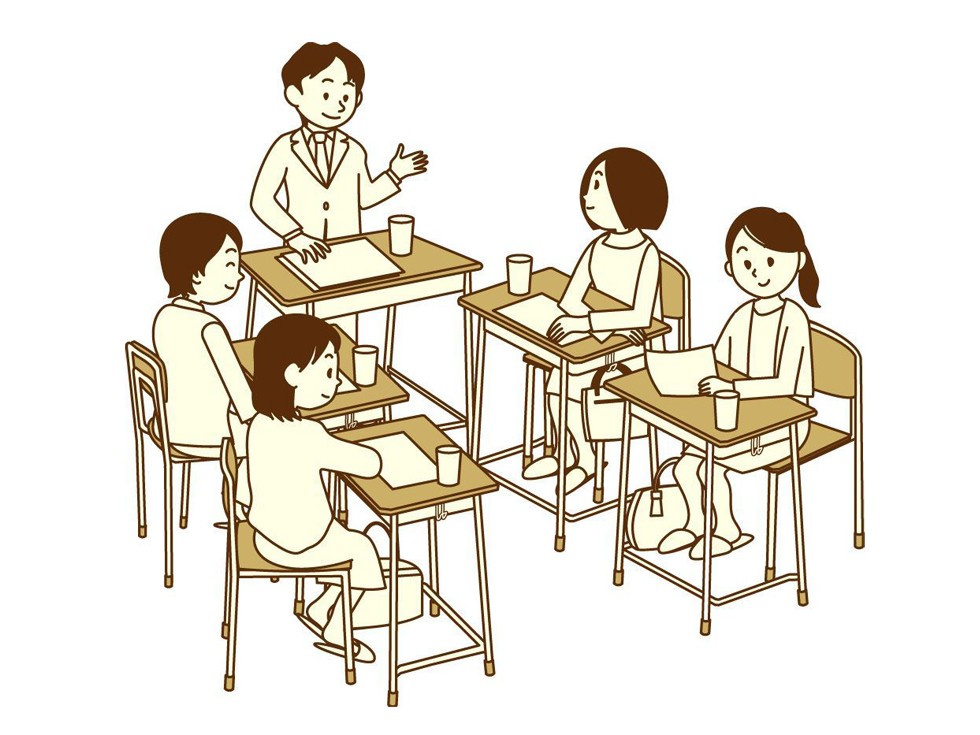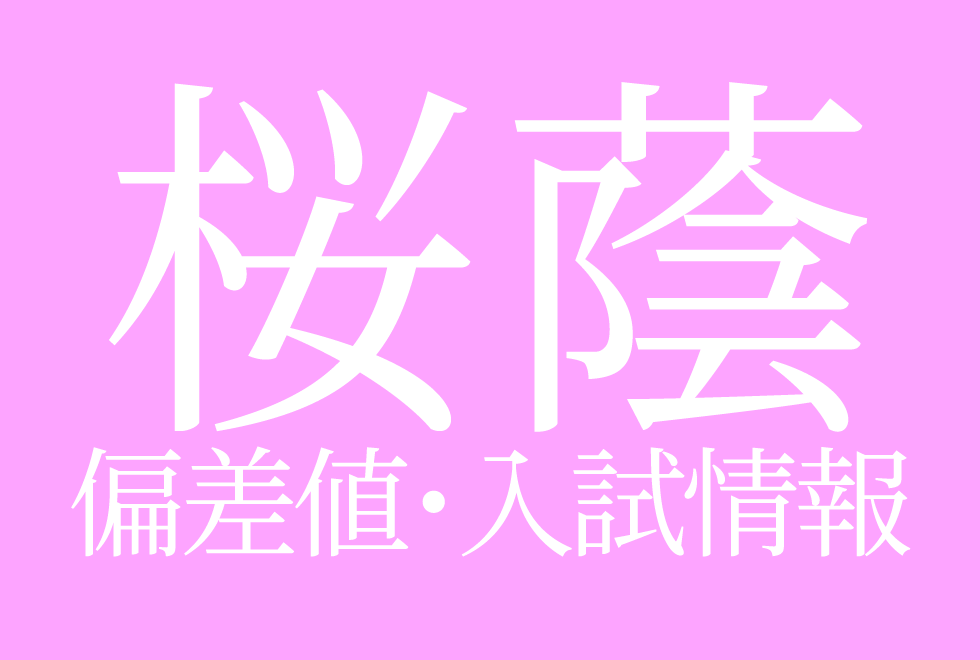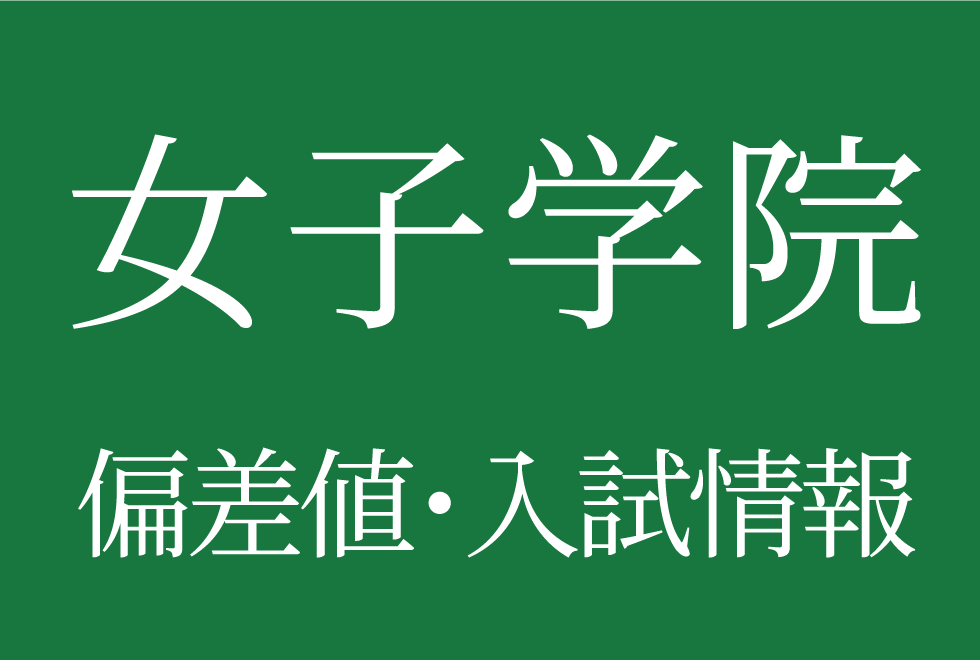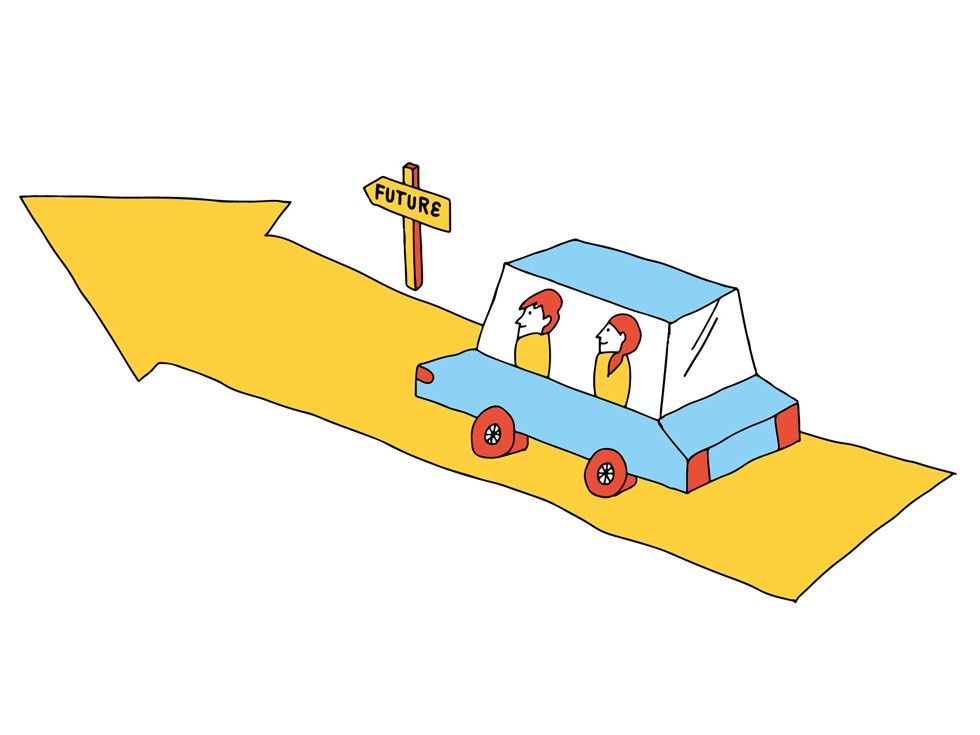


気付かないうちに「逆接の言葉」を使っていませんか?
子どもとの会話で、どんな受け答えをしていますか?
次のパターンA・Bの会話を比べてみてください。
どんな違いがあるでしょうか?
【パターンA】
子「今日、嫌なことがあったの……」
親「どうしたの?」
子「授業中に隣のY君が話しかけてきたから答えただけなのに、先生に叱られた。私は悪くないのに、めっちゃ頭にきた」
親「でも、先生から見ればおしゃべりしてるように見えるよね」
子「Y君が隣だといろいろ迷惑。しょっちゅう筆箱を忘れて、私の鉛筆を借りようとするんだもん」
親「だけど、あの子おもしろいところあるじゃん。物まねもうまいし」
子「この前なんか、私の消しゴムを使って、『ありがとう』も言わないのよ」
親「けど、あの子勉強できるんだから、あんたもいろいろ教えてもらいなよ」
子「あんなやつに教わりたくないよ。勉強ができても、だらしがなさすぎ」
親「そうは言っても、やっぱり勉強ができないと、いい学校に入れないよ」
子「また勉強の話? 私の悩みなんて、どうでもいいんだね?」
親「でも、あなた、もうすぐ期末テストでしょ? そんなこと言ってるヒマがあったら勉強しなきゃダメでしょ」
子「もう、いい! 私の話なんか、なんにも聞いてくれないんだね」
【パターンB】
子「今日、嫌なことがあったの……」
親「どうしたの?」
子「授業中に隣のY君が話しかけてきたから答えただけなのに、先生に叱られた。私は悪くないのに、めっちゃ頭にきた」
親「そうなんだ……。それは頭にくるよね」
子「Y君が隣だといろいろ迷惑。しょっちゅう筆箱を忘れて、私の鉛筆を借りようとするんだもん」
親「なるほど、それは困るね」
子「この前なんか、私の消しゴムを黙って使って、『ありがとう』も言わないのよ。『ありがとう』くらい言って欲しいよ」
親「たしかに、『ありがとう』のひと言くらい欲しいよね」
子「そうだよ。そうだよ。お母さんもそう思うでしょ。礼儀ってもんがあるよね」
親「ほんと、そうだよね」
子「ああ、しゃべったらすっきりした」
親「Y君って、勉強はできるんでしょ」
子「そう、たしかに、勉強はできる」
親「今度、勉強を教えてもらっちゃえば。あなた、いつも助けてあげているんだし」
子「そうだね。それはいいかも。私が苦手な理科も、あいつは得意だから」
親「期末テストもあるし、もう準備を始めておいたほうがいいよね」
逆接の言葉で返すと、相手は「わかってもらえない」と感じる
いかがでしょうか?
違いをひと言で言えば、共感のあるなしです。
Aの親の受け答えは、子どもの気持ちへの共感がまったくありません。
それが端的に出ているのが、「でも」「だけど」「けど」「しかし」「そうは言っても」などの言葉です。
これらは逆接の言葉であり、相手の話や気持ちを否定する働きがあります。
人の話を聞いて、すぐにこれらの逆接の言葉で返してしまう人は気をつけてください。
というのも、相手は「この人には話を聞いてもらえない」「自分の気持ちをわかってもらえない」と感じるからです。
共感の言葉で返すと、相手は「わかってもらえた」と感じることができる
Bの親は、「そうなんだ」「なるほど」「たしかに」「ほんと、そうだよね」など、子どもの気持ちに共感する言葉が最初に来ています。
それによって、子どもも愚痴を吐き出しやすくなります。
そして、親にわかってもらえたと感じて気持ちが安らかになりますし、親を信頼する気持ちも高まります。
ですから、親が最後に勉強の話を持ち出したときも、素直な気持ちで受け入れることができるのです。
親野先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。