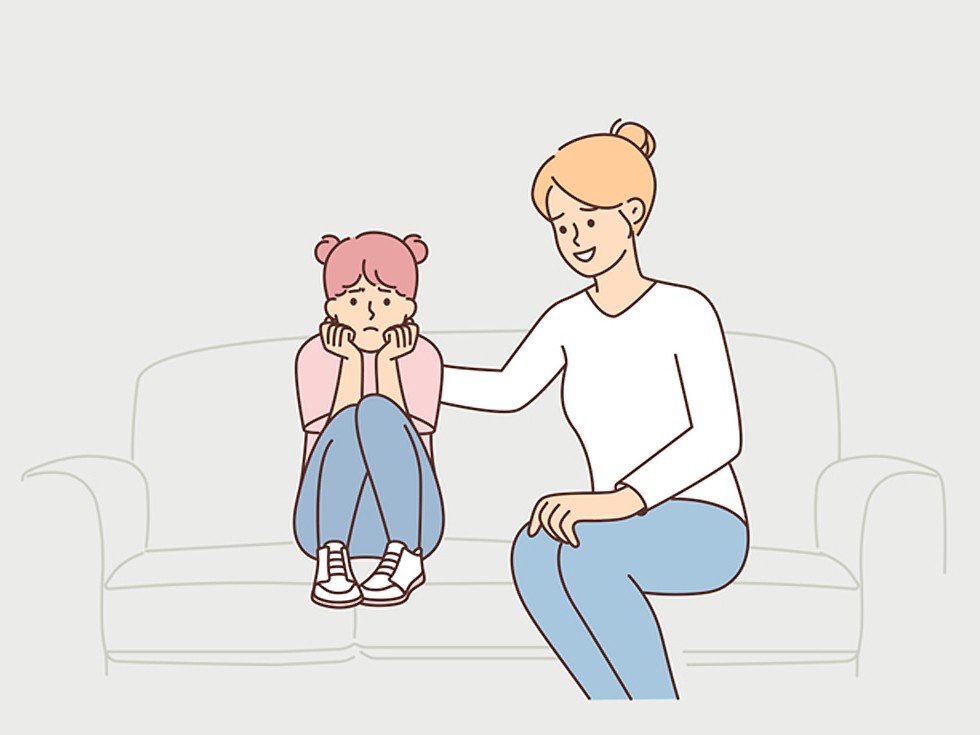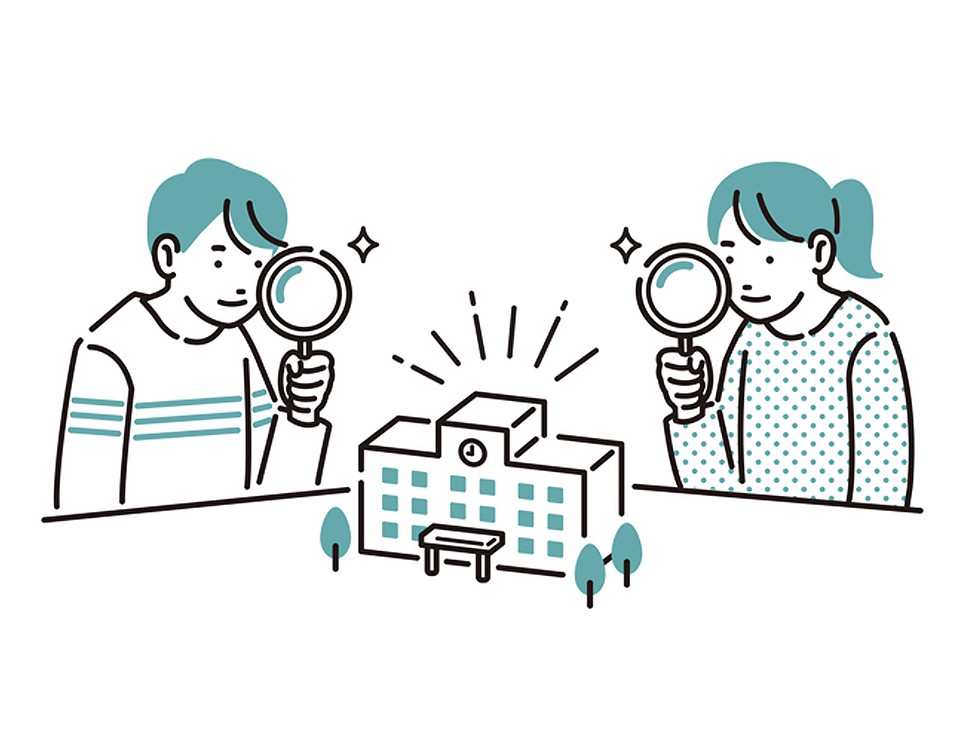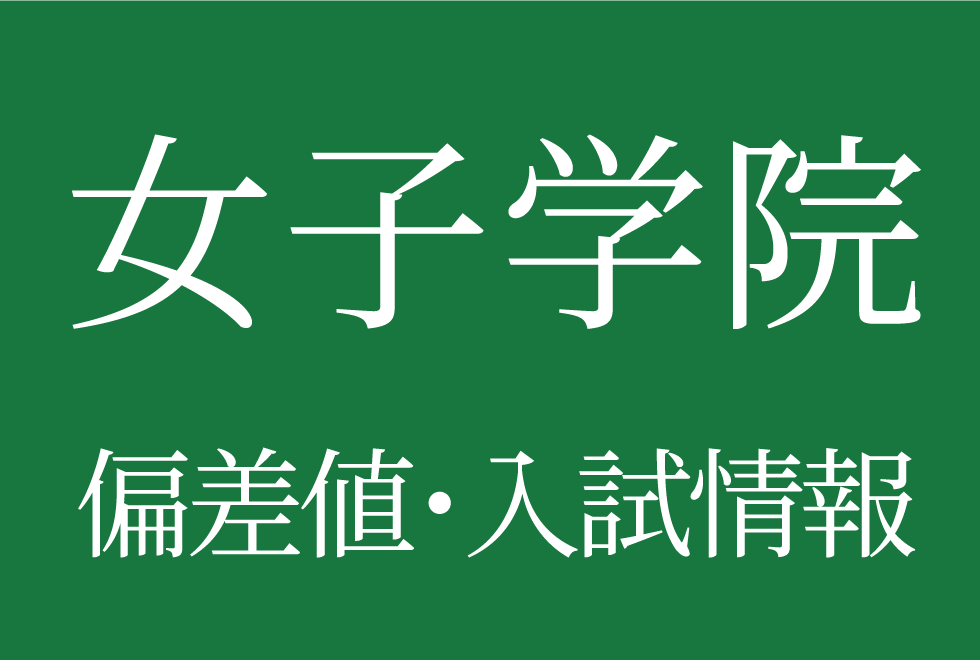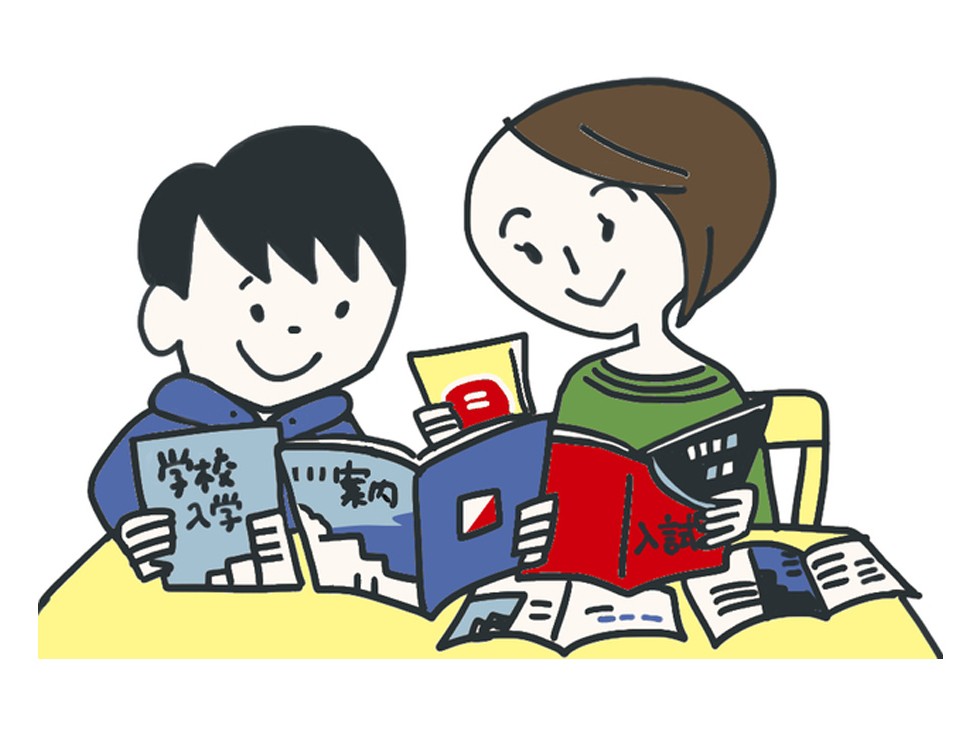

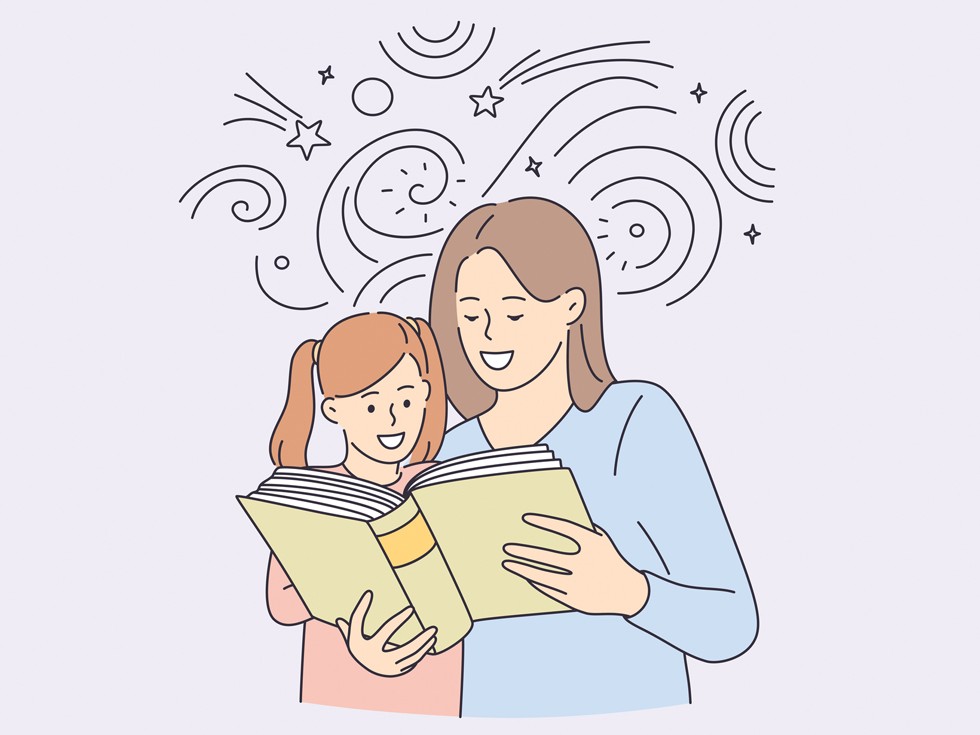
先取り教育を考える
今は「第3次中学受験ブーム」であるとの声も聞かれます。実際、2022年首都圏中学入試は受験率・受験者数ともに過去最高を記録し、東京都の受験率は30%の大台に乗ったといわれています。
さらに、「今後10年近くは中学受験のブームが続く」と分析している中学受験関係者も少なくありません。
一般的に中学受験は「塾ありき」で考えられています。そのため入塾を検討する人が多く、現状が過熱傾向であることもあいまって、最難関私立中学への進学実績が高い塾では、小学1年生という早い段階で募集を締め切ってしまう教室が続出し、親の焦りを余計に刺激する事態になっています。
このような状況のため、中学受験を始める好機といわれる小学4年生を前倒しにして、もっと早い時点から「中学受験」を目指し、入塾に向けて動いているご家庭も多いようです。
いわば一種の「先取り教育」です。今回はこのことについて考えてみましょう。
先取り教育の問題点は「親の焦り」
「先取り教育」とは、その子の年齢に必要とされる学習よりも先の内容をあらかじめ勉強しておくことです。
もちろん、これ自体は悪いことではありません。
物事を柔軟に吸収できる幼少期に、たくさんの言葉や数字などを身につけることは、自然や科学への興味を深め、自分なりの知識をふくらませる第一歩になりえます。
子どもの発する、「これは何?」「なぜなんだろう?」「どうしてこうなるの?」という小さな発見や疑問を解決に導くことができれば、子どもの成長が実感でき、子育てがいっそう楽しく感じられるでしょう。
先取り教育で問題になるのは「親の焦り」です。
先述のように、首都圏の一部地域では入塾年齢が早まる傾向があるのですが、「4年生からでは入塾できない=有名中高一貫校に合格できない」→「周りは既に動いている」→「取り残される!」という「焦り」をもつことは、長い目で見ると決して得策とはいえません。
「周囲の人たちが子どもを入塾させたから」「早めにスタートしないと合格できないから」といった理由で、わが子をむりやり塾に入れたり、親が塾の成績で一喜一憂したりすると、早い段階で子どもを「勉強嫌い」にしてしまう結果になりかねず、注意が必要です。
なぜなら、親のそういった態度によって、勉強の目的が「点数を取ること」にすり替わってしまう危険があるからです。
点数を取るより大切なこと
子どもが低学年のうちは、公式を丸暗記したり、あるいは解き方を丸暗記するなどのテクニックで点数を上げることが可能です。それゆえ、親のほうが躍起になって、「点取り虫」に仕立てようと一生懸命になる傾向が見られます。
いうまでもなく勉強は、答えにたどり着くために自分で考え、試行錯誤をし、その考え方を自ら表現するものですので、理解できないまま丸暗記しても、いずれ行き詰まることは確実です。高学年になると、丸暗記学習法では対応できず、伸び悩んだ結果、勉強そのものを拒否するということも起こります。
繰り返しになりますが、先取り教育が悪いわけではないのです。
ただ、早期教育として、受験塾、もしくはそれに近い学習塾での学習を検討しているご家庭には、まずは子どもが基本的な生活習慣を身につけるのを優先し、そのうえで中学受験を考えてほしいと思います。
結果論ではありますが、すべての土台となる基本的な生活習慣をしっかり作ってきた子のほうが、充実した中高時代を過ごす率は上がります。
わが子主体で考える先取り教育
未就学児、あるいは低学年の子どもをもつ親御さんには、次の4つの習慣を意識した子育てをお勧めします。
1. よい習慣の確立
2. ルールをふまえて自主性を育む
3. 知的好奇心を刺激し、興味をもったことを好きなようにやらせる
4. 愛情をもって褒めて伸ばす
要は、睡眠・食事・遊び(ごっこ遊びのような形でのお手伝いや学習なども含む)を大切にし、家庭内のルールに応じて、規則正しく暮らしていくことです。
その中で、興味をもったことを好きなようにやらせるといったサポートに徹しながら、「点数」に関係なく、愛情を注ぐということです。
結局のところ、親の庇護のもとで暮らすしかない小学生以下の子どもに親ができることは、日々の暮らしをちょうどいい塩梅に整えるということだと思います。
そのためには、親自身が子どもと共有できる時間が限られていることを知り、限られた時間を楽しもうとすることが最も大切です。
「周りがこうだから」「塾の座席確保のために」という他者主体の動機ではなく、「幼いわが子の脳と体を健康に育てるには?」というわが家主体の意思をもって、先取り教育を考えてほしいと願っています。
鳥居先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。