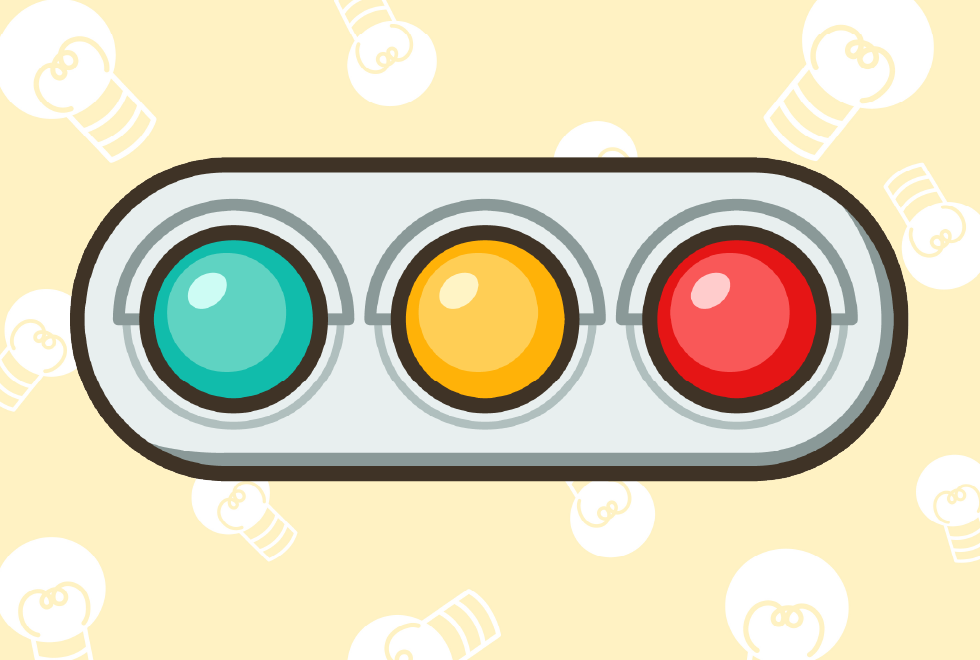発達障害と中学受験を考える
最近ではメディアでも「発達障害」という言葉が頻繁に取り上げられるようになりました。これは脳の働き方の違いにより、物事の捉え方や行動パターンに違いがあるために、その人自身、あるいは周りの人たちの日常生活に支障が出る状態を指します。
10年ごとに行われる文科省の調査(2022年)によると、通常の学級に在籍する小学生の10.4%の児童に発達障害の可能性があると指摘されています。35人学級であれば3人から4人ほどの計算になります。
発達障害ないしはグレーゾーンと呼ばれるお子さんをお持ちの親御さんは、わが子の教育にとても悩まれる傾向があり、私の元にもご相談は数多く入ります。
「中学受験をしたほうがいいでしょうか?」というのも、とても多いご質問ですので、今回は「発達障害と中学受験を考える」という視点で語ってみようと思います。
わが子の得意分野を伸ばしてくれる学校へ
考え方は人それぞれですが、私個人の結論を先に言えば「事情が許せば、中学受験はしたほうがいい」です。事情とは、①通学可能な範囲に適した学校がある、②金銭的に問題がない、③入試を突破できるだけの素養がある、ということになります。
地方ですと中高一貫校が通学できる範囲にないことも沢山ありますし(この場合は寮生活という選択肢もあります)、授業料無償化となったとしても私立の教育費総計は高額です。
さらに、一番の問題点は学力です。中高一貫校は基本的には入試を突破しなければならないので、その学校が求める学力水準に達していなければ入学できません。
この3点に対応できるという場合は中学受験を考えてみるといいかもしれません。
発達障害であろうとなかろうと、親御さんたちが中学受験をしようと思った動機のひとつに「公教育」への不信感があります。もちろん、学校にもよりますが、今現在の公教育は「平均」に近付けることを目指しているように捉えられているのだと感じます。
日々の授業では理解が進まない子を平均に近づけようとする傾向があり、いわゆる「浮きこぼれ」と呼ばれる子へのケアが疎かになりがちということが問題視されているのです。
これに加え、公立中学校には高校受験に向けた内申点という制度があります。内申点とは単にテストの成績だけで決まるものではなく、授業態度や提出物の提出状況、部活・委員会・ボランティア活動、さらには生活態度なども評価対象になります。
これが発達障害の子どもにとってはハードルが高いという傾向があるので、当日の入試一発勝負で合否が決まる中学受験を目指すご家庭が多いのです。
けれども何と言っても一番の魅力は「選べること」。ご家庭の経済状況やお子さんの学力に左右されるものではありますが、お子さんとご家庭に合った学校を選べる自由があるのは幸せな話です。
発達障害のお子さんはこれまで「普通じゃない」ということで、できない部分を指摘され続け、善意で矯正させようと様々な場所でプレッシャーをかけられてきたことかと思います。
しかし、多くの私立学校では伝統的に「その子らしく」という思いが強いので、どちらかと言えば「得意なことを伸ばす」ような教育プログラムが組まれています。
面白いのは、それが直接、勉強に関わることでなくとも、本人が興味・関心を持つ分野があるならば、それを「温かく見守る」学校が多いのです。これは、6年間の中で徐々に成長すればいいという長期的視野に立てる中高一貫校の良さのひとつであります。
ある難関校の先生は私にこうおっしゃいました。
「本校はオタクの巣窟です。もちろん、発達障害のオタクも沢山いますよ。でも、生徒たちはその分野のスペシャリストとして、ソイツを逆に尊敬します(笑)。もっとも、6年も付き合うと混ざっちゃうから、発達障害児も健常児もあまり関係ないと思いますし、我々、教員団もそういう分け方では考えないですね」
また、ある超進学校では、校長先生が「発達障害? 本校では3分の1強はそういう生徒ですよ。でも、何か問題でも?」と笑顔でおっしゃったことがあります。
発達障害であろうがなかろうが、どの子も「個性を持ったひとりの人間」として見ているのだということがわかりましたが、難関校ではこの考え方が特に強いように感じています。
ご家庭も学校もそうですが、子どもの教育にとって一番大切なのは、「その子の良さを消さないこと」だという思いを私は持っています。発達障害を持つお子さんをお育ての親御さんには特に「その子の存在を認め」ながら「得意な分野を伸ばす」教育をしてくれると「信じられる」学校を選んで欲しいと願っています。
「信じられる」というのは、育児も教育も祈りでしかないからです。親の「こうなりますように」「こうなりませんように」という思いが、必ずしも望み通りにいかないのは世の常です。
それでも、子どもの未来に幸多かれと祈りながら、できることをやっていくしかないわけです。そういう意味では、わが子に合った学校を選ぶことはできます。その自由があるのが中学受験なのです。
学校訪問の場数を踏むこと、そして隠さないこと
では、どう志望校を選べばよいのかという問題になりますが、これは親の努力にかかっています。志望校との出会いは「ご縁」とも言えますが、ご縁を掴むためには行動あるのみです。
自説で恐縮ですが「中学受験は結婚相手選びと同じ」。毎日を一緒に過ごすことが自然体でできる、素の自分でいられるということは結婚の重要な要素だと思いますが、中学受験の学校選びもそうです。
あなたのお子さんと隣の子は違います。子どもによって居心地の良い環境は様々ですから、お子さんのことを一番よくわかっている親こそが、まず実際に足で訪ねてみて、合う・合わないの感覚を養ってください。
では、具体的な学校見学についてお話しします。
学校見学はすべての学校を見て回ると途方もなくなってしまうので、まずは条件を設定してからのほうが行きやすくなります。条件の一例を挙げてみましょう。
1)通学時間
通学時間は90分以内と決まっている学校があるくらい、90分という数字は中学生がギリギリ通学できる時間だと思います。発達障害のお子さんであれば、なおさら、通学時間は短いほうがいいと思いますが、満員電車ではないか、乗り換えが多くないか、バス通学が負担にならないかなども考慮に入れてください。
2)別学校か共学校か
発達障害をお持ちの方は別学校を選ぶ傾向がありますが、お子さんによって好みは分かれますので、まずは、どちらかに絞って、実際に行ってみてください。
3)大学附属かそれ以外か
エスカレーター式で系列大学に行ける道が良いのか(その場合は、成績順に志望学部が決定するのが負担になるタイプか否か)、それとも一般受験が主流の学校が合うのかを想像してみてください。
4)高校募集があるか、ないか
発達障害をお持ちのお子さんは小学生時代にいじめにあっているケースが多く見られます。万が一、いじめた子と高校で一緒にならないために完全中高一貫校を選ぶご家庭があるのも確かです。
(余談ですが、いじめた子と中学で一緒になった場合、学校側に入学前に「こういう事情があるので、クラスを離して欲しい」と穏やかに伝えることをお勧めしています。)
関連記事「学校説明会で何を見るかを考える」を読む
このように各ご家庭の事情に合わせた条件が見えてきたら、実際に行ける範囲の学校にはすべて行く気持ちで頑張ってみてください。
合う・合わないが段々と明確になってくるので、やはり「場数」は大事です。
できれば同じ学校でも気に入った、あるいは気になる学校ができたならば、複数回、出かけてみることをお勧めします。
親子でファンになれる学校ができるならば、それは学校側が最も望んでいることでもあり、双方にとって幸せです。入学後も、さらには卒業後も生涯にわたって良い関係を築くことができるでしょう。
そして、最後にこう申し上げたいと思います。
「隠すな!」
学校訪問に出かけた際には、ぜひ、個別に面談させてもらってください。学校説明会や文化祭の際には、ほとんどの学校が「個別相談ブース」を設けています。
関連記事「個別相談会で何を聞くかを考える」を読む
怖く感じるかもしれませんが、先述のとおり、今や発達障害に慣れていない学校はありませんし、発達障害で不合格になることはありません(合否はあくまで当日の試験の出来具合です)。
ですから「ウチの子にはこういう傾向があって」ということをまずは正直に打ち明けてみてください。
そして、「ウチの子のようなタイプの生徒さんはおられますか? どのようにご指導されていますか?」と聞いてみてください。
さらに、在校生の様子をじっくり観察することです。在校生は未来のお子さんの姿です。どんなタイプの子が多いのかの雰囲気を味わうことは、思うよりも大事なことです。
ご相談者であったお母さんが教えてくれました。
ある学校の個別相談で「ウチの子は思ったことをすぐに口に出す傾向があるので、きっと授業中に要らない発言をしてしまい、クラスで浮くと思う」と打ち明けたと。
きっと嫌がられるだろうと思いきや、そこの先生は「いい子じゃないですか! 我々も反応があったほうが、授業がやりやすいですから、大歓迎。それもあって、本校の授業は生徒の発言が飛び交ってうるさいですよ(笑)。(ご子息には)何の心配もありません」と言われたそうです。
今までの子育てで「いい子」だと評価されたことは一度もなかったそうで、そう言われて、思わず涙ぐんでしまったとのことです。そのご家庭の熱望校になったのは言うまでもありません。
実際に入学した後も、その子の謎行動を「○○はこういうところがあるけど、面白いヤツ」という雰囲気を作ってくださったとかで、現在は気の合う仲間たちと充実した学校生活を送っていると聞いています。
このケースも、入学前にカミングアウトしていたからこそ、学校側も有形・無形の様々な配慮ができたのだと思います。
正直に申し上げると、発達障害の生徒を歓迎していない学校もあります。また、指導経験が少ない、その面での教員間の連携がないという学校もあります。
学年によっても違いがあり、見極めるのは至難の業なのですが、それでも肌感覚として「ここならばわが子は楽しくやっていける!」と信じられたならば、その学校があなたの大切なお子さんを預けるに相応しい学校と言えるでしょう。
皆さんのお子さんが「楽しい!」と言って通える学校に巡り合うことができますように。
以上のことが、ご参考になると嬉しいです。
TOMAS全校で無料受験相談を承っています
「志望校に向けて何から始めてよいかわからない」「足を引っ張っている科目がある」「塾・予備校に通っているが成果が出ない」など、学習面でお困りのことはありませんか? 進学個別指導TOMASならではの視点で、つまずきの原因を分析し、課題を解決する具体策を提案します。まずはお気軽にご相談ください。
鳥居先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。