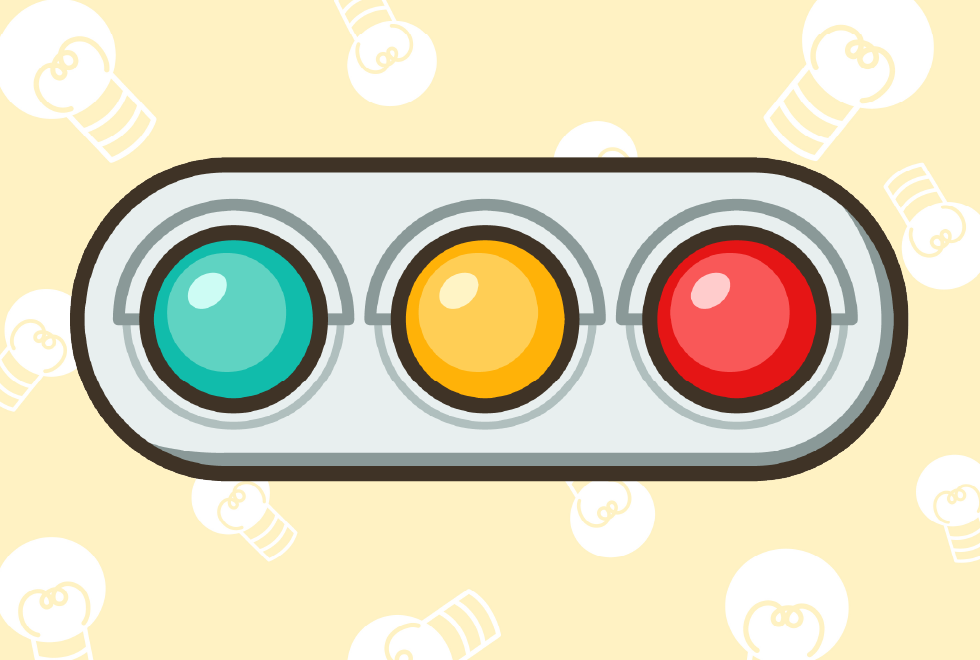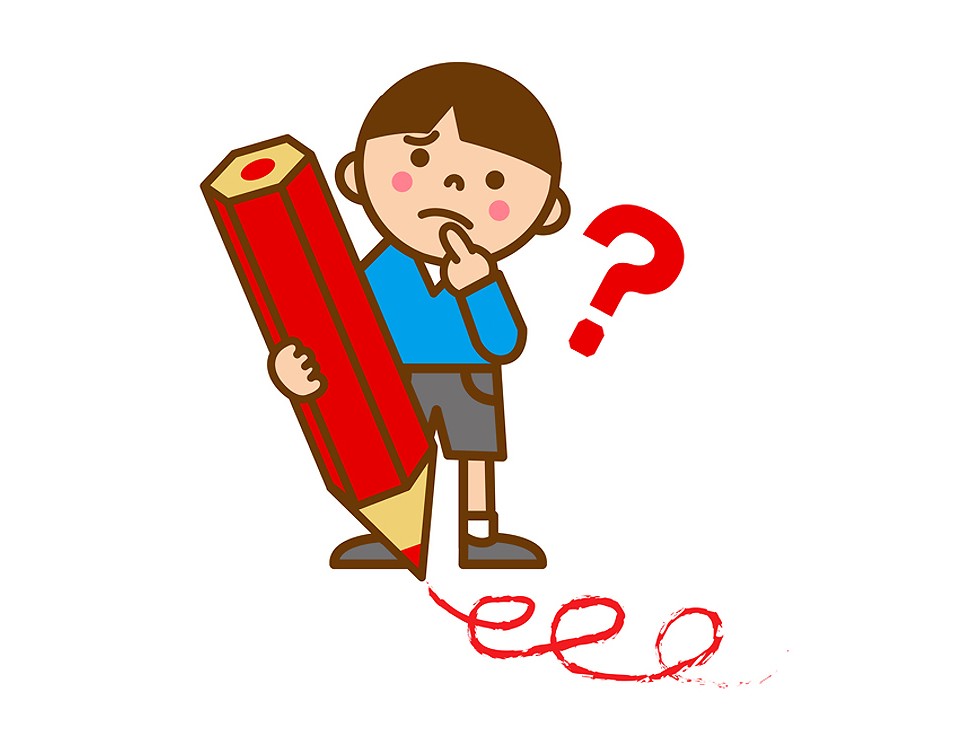
「なんで勉強しなきゃいけないの?」と子どもに聞かれたら、どう答える?
「なんで勉強しなきゃいけないの?」は静かに語り合いたいテーマ
「なんで勉強しなきゃいけないの?」と子どもに聞かれたことはありませんか?
高学年になった子どもはこれまでとは異なり、「勉強はしなければいけないもの」という前提そのものを疑います。
さあ、あなたはなんと答えますか?
子どもはなぜ勉強したほうがいいのか、しなければならないのかを知っているわけではありません。
親や教師がうまく習慣づけて勉強していても、子どもたちは、3~4年生になるころからその習慣に疑問を持ち始めます。
特に、受験をめざしている子どもは、受験しない子どもより多くの時間を勉強にあてています。
受験することを決めたときは納得していたとしても、受験しない子と比べると、なぜ自分ばかりこんなに勉強しなきゃいけないんだろうと疑問に思っても不思議はありません。
ただ、子どもにこの質問をさせてはいけない場面があります。
それは、親が「勉強しなさい!」「もっとがんばりなさい」と叱咤し、子どもがそれに耐えきれず、「なんで勉強しなきゃいけないの!」と思わず叫ぶ場面です。
この時、子どもは素直に疑問を口にしたのではなく、親にこれ以上勉強を強要されないように、感情的になって勉強を否定しているのです。
こんな時は、何を言っても子どもは聞く耳を持ちません。
本来、「なんで勉強しなきゃいけないの?」は静かに語り合いたいテーマなのです。
この質問の受け止め方
「なんで勉強しなきゃいけないの?」と思いながらも、でもそんなもんだと達観している子どももいます。
一方で、この疑問を親にぶつけて話し合いたいと思っている子どももいます。
ですから、この質問をされたときは、親にとってもよい機会です。
なぜ勉強するのか、なぜ受験するのかを、子どもと一緒に考えてみましょう。
「面倒なことを聞いてきたなぁ……」という姿勢ではなく、「本当に、なんで勉強しなきゃいけないのかしら」という思いで受け止めてください。
正しい答えを与えなければならないとか、すぐに答えを出さなければならないと思う必要もありません。
なぜなら、この質問は、子ども自身が答えを見つけなければならない問いかけだからです。
だから、お母さんは、この質問を十分に受け止めてあげてください。
普段から親も考えよう
さて、お母さん。
あなたは、なぜ勉強する必要があると思いますか?
私が勉強できなかったから、せめて子どもはいい成績を取って、いい仕事を見つけてほしい……。
これでは、子どもはお母さんのために勉強しなさいと言われているようで、納得できないし、やる気にもなれません。
また、お母さんも子どものころ受験勉強したんだから、あなたもがんばっていい中学に入って……と言うのも説得力がありません。
子どもは、お母さんはどうであれ自分はしたくないと言うでしょう。
私たちは、親として「なぜ人は勉強しなくてはならないか、なぜ勉強したほうがいいのか」を考えることが重要なのです。
テーマはいろいろ
この時に、子どもに伝えられることはいろいろあります。
例えば、子どもがサッカーを好きなら、サッカーに関わる仕事を例に挙げるといいでしょう。
選手になれるか、子どもたちにサッカーを教える仕事をするか、スポーツ業界に就職してサッカーに携わるか……。
いずれにしても、勉強していればそういった職業に就くことができます。
ゲームに夢中な子どもであれば、デザインやプログラミングを学べば、いつかゲームを創ることを仕事にできるかもしれない。
パンを焼くのが好きな子なら、食物について学べば、将来自分のパン屋さんが開業できるかもしれない。
……など、子どもの好きなこと、夢中になっていることを例に挙げながら、子どもの将来と今やるべき勉強をつないで見せることが重要です。
伝え方のコツは、「勉強しないと~になれない」ではなく、「勉強すれば~になれる」と肯定的に見せることです。
お母さんはハローワーク
そういう意味では、子どもにとって、親は人生最初のハローワークです。
ですから、子どもに働くこと、生活することについて話していくといいでしょう。
お父さんやお母さんの仕事などを例に挙げて、会社で働くとその分の給料がもらえて家族が生活できることを話します。
ほかにも、様々な職業を例に挙げて話すといいでしょう。
流通業の話、製造業の話、サービス業の話など、子どもがよく目にする仕事を例にとって話します。
そして、組織や社会の役に立つ人が、その分の給料を受け取れることを伝えましょう。
高学年になるころには、学習や練習など、何かに打ち込んで努力した人ほど、高額の報酬を受け取る可能性が高いことに、興味を持つようになるでしょう。
ただし、最後に「だから勉強しなさい」で締めくくらないように気をつけて。
そうすれば、子どもはよく理解してくれますよ。
菅原先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。