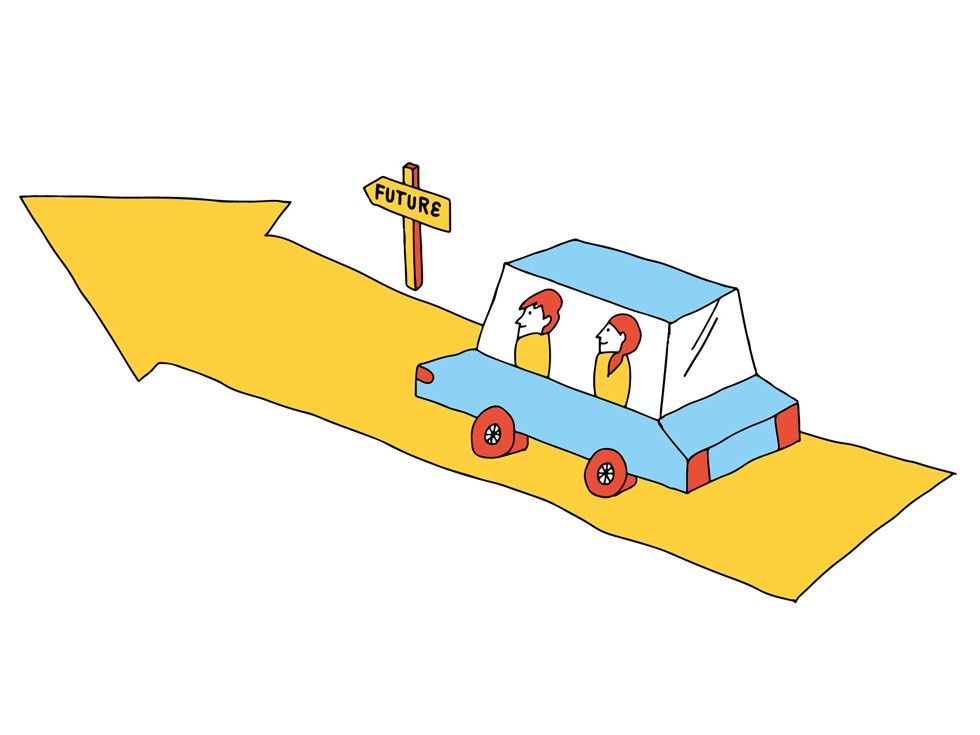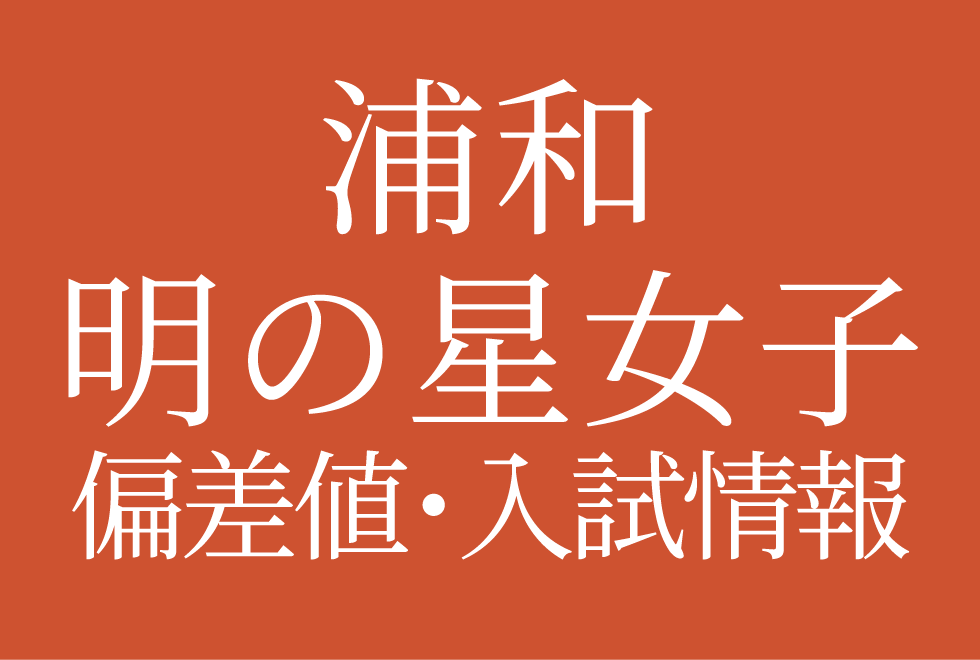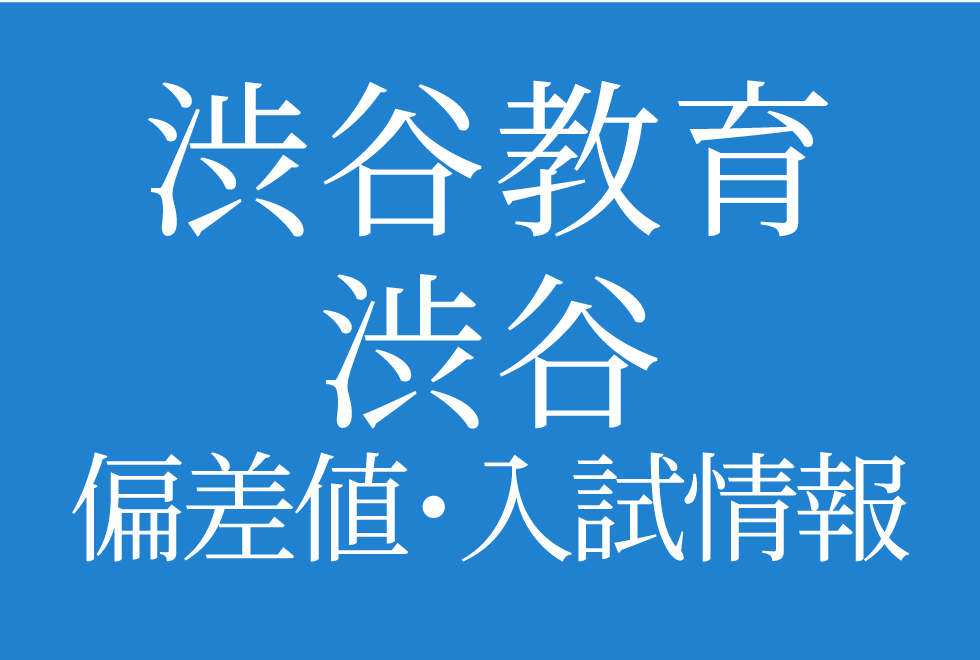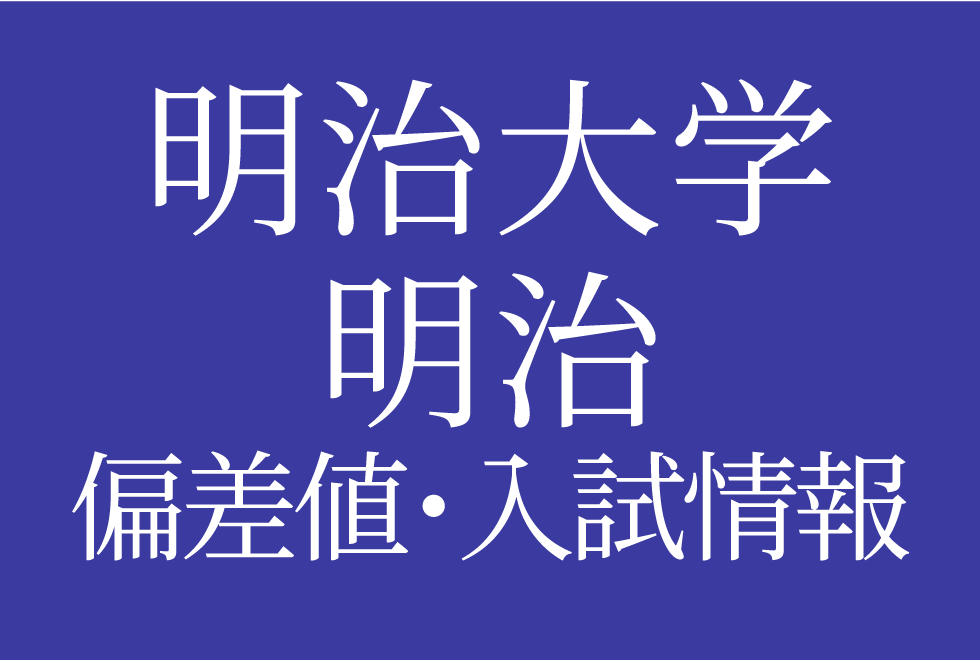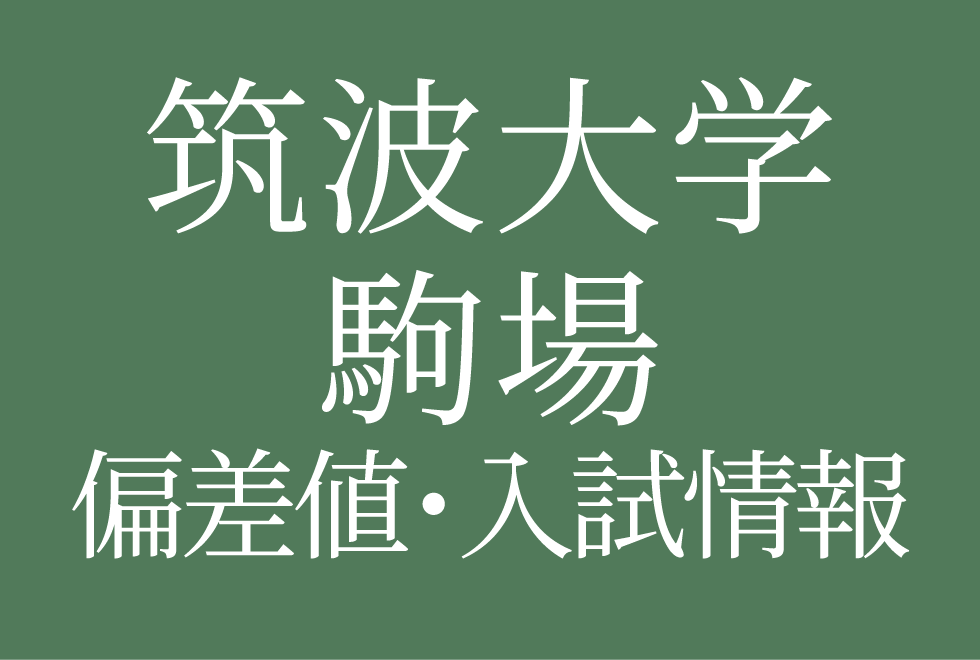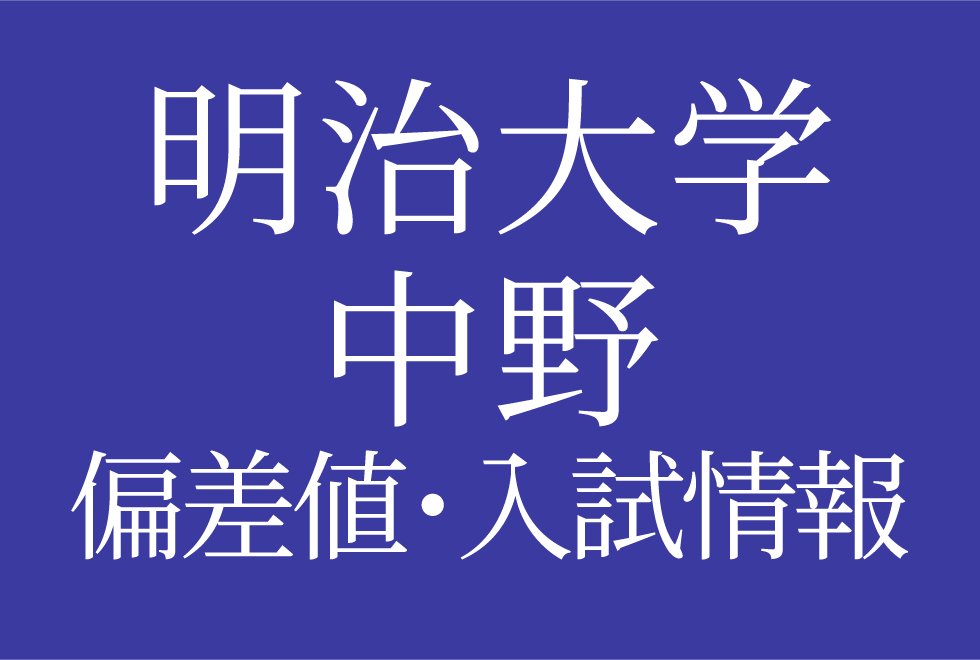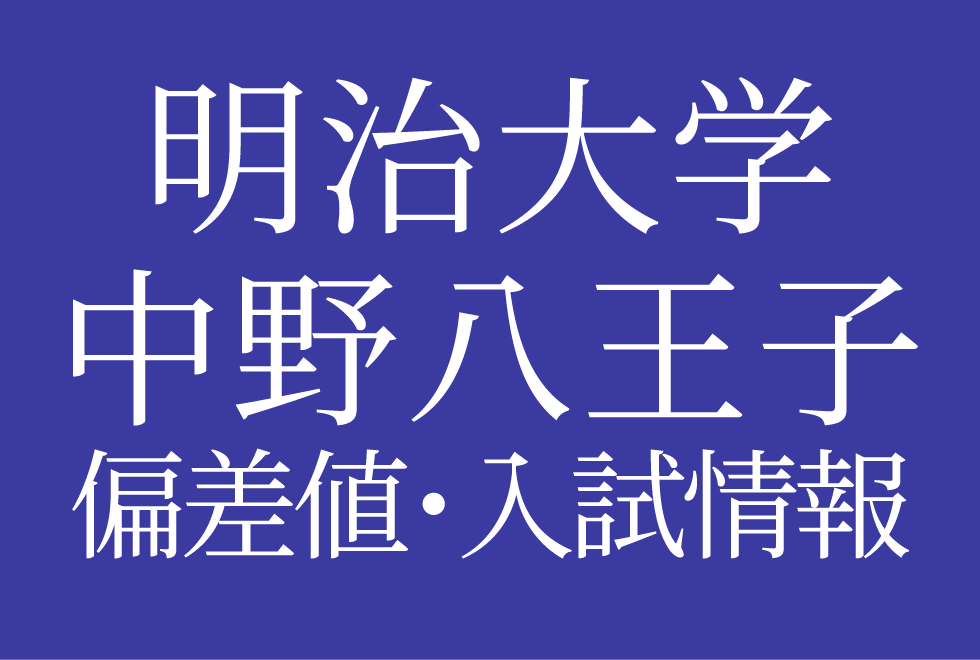親も自分をアップデートしよう。子どものためにも、自分のためにも
「就職は銀行」にこだわった父親
ある20代半ばの男性から聞いた話です。
大学を卒業するとき、父親が彼を地元の某銀行に就職させたがり、彼はとても困ったそうです。
父親は、昔、自分自身がその銀行に就職したかったとのことです。
父親が若い頃は、銀行は給料がいい、公務員並みに安定している、ステータスが高くかっこいいなどと世間で思われていました。
でも、父親はその銀行に就職できず、別の会社に就職しました。
その会社で働きながらもずっと銀行への憧れは続き、息子は絶対銀行に就職させたいと思っていたらしいのです。
ところが、息子本人は就職活動の当初から、銀行は就職先としての魅力に乏しいと感じていました。
低金利政策が続いている、ITの進化で金融業務が銀行以外でも可能になってきている、そして長引く不景気、特に地方経済の衰退などにより、銀行の先行きはかなり不透明だと考えたからです。
実際に、今は多くの銀行の収益が悪化して経営危機に陥ったり、それを避けるために統合したりなどが増えています。
時代の流れは大きく変わってきているのに、父親は自分が若い頃の思い込みにとらわれていて、情報や価値観のアップデートができていなかったのです。
親がアップデートできていないと子どもの足を引っ張る
似たような話はほかにもあると思います。
例えば、親はわが子がキャリア官僚になるのを期待するけれど、子ども本人は嫌がるケースです。
これはありそうなことだと思います。というのも、就職先として憧れの的だったキャリア官僚が、最近は若者から敬遠されている実態があるからです。
東大出身のライター・池田渓さんによると「長時間労働、国会議員や官邸からのパワハラまがいの指示、劣悪なオフィス環境、多発するうつ病や自殺……これらの悲惨な官僚の勤務環境が世間に周知されてきたということだろう」とのことです。
親がアップデートできていないと、わが子に従来型の常識や価値観に従った線路を敷き、それに乗るよう強制したりして結局は子どものためにならない、などということになりかねません。
激動の時代に必要な力とは?
今は激動の時代です。
温暖化による気候変動とSDGs(持続可能な開発目標)の推進はもう待ったなしです。
莫大なエネルギーを使う大量生産と大量消費の時代は終わります。
それに伴って、今まであった産業が衰退し、新しい産業が生まれます。
人工知能(AI)の進化が加速度的に進みます。
決まり切ったことをする単純な仕事はAIがするようになり、「人間にしかできないことは何か?」を考えて、その能力を伸ばす必要があります。
超高齢社会が到来し、人生が長くなります。
今の子どもたちは100歳、あるいはそれを超えて長生きする可能性が高いとのことです。
このようなわけで、今までのように、どこかの会社に就職して、定年まで勤めて、後は余生、というようなスタイルは成り立たなくなります。
就職した会社がいつまであるかわかりませんし、その仕事や職業自体がなくなる可能性もあります。
オックスフォード大学のオズボーン准教授によると、AIの進化により、10~20年後には47%の仕事が自動化される可能性があるそうです。
会社が倒産したり仕事がなくなったりしたとき、途方に暮れたまま立ち尽くすだけではやっていけません。
もう親に聞くわけにはいきませんから、転職するにしても起業するにしても、とにかく自分から動いて新しい道を切り開いていく必要があります。
自ら切り開く能力を身につけるには?
でも、「自分で動いて新しい世界を切り開く」のは、親の敷いた線路をたどってきただけの人には難しいのではないでしょうか?
小さいときから主体的な生き方ができるようにしていくことが大切です。
つまり、自分がやりたいことを自分で見つけてどんどんやっていけるようにする必要があるのです。
激変する社会においては、自らの意思や判断で変われる人が生き残れますし、活躍もできます。チャレンジができる人といってもいいでしょう。
答えがない、お手本もない、マニュアルもすぐに通用しなくなる、そういう時代においては自ら切り開いていく力が必要です。
生きる意味、人生のビジョン、仕事のアイデア、目標達成の方法、トラブル解決などなど、いたるところで自らの目標を設定し、自ら考えて実行することが大事です。
親の敷いた線路をたどるだけでは、身につかない能力と言えます。
子育てや教育についての考え方もアップデートを
子育てや教育についての考え方もアップデートが必要です。
というのも、児童心理学、教育心理学、脳科学などの急速な発展で、過去に常識と思われていたことが今は否定されたり、真実はその逆だと判明したりといったことが頻繁に起こっているからです。
例えば、以前は「3歳児神話」というものがありました。
3歳まではとにかく母親は育児に専念して、つきっきりで育てたほうがいいという考え方です。でも、今この考え方は否定されています。
また、「抱き癖」などという言葉が流行ったことがありました。
「乳幼児が泣いたときすぐ抱っこしていると、抱き癖がついてますます泣くようになり、よくない」という説です。
これも今は否定されています。
ほかにも、「短所や困った性格も子どものうちなら直しやすい」「できないことを手伝ったりやってあげたりすると自立できない」「忘れ物をして自分が困れば、自分で何とかするようになるから放っておけばいい」などという説もよく言われてきましたが、全て勘違いだったのです。
また、「子どもの言うことを何でも聞いているとわがままになる」とよく言われていました。
でも、この説も児童心理学の研究で否定され、真実は逆だということがわかったのです。
「抱っこ」と言ったら「歩けるでしょ」などと突き放さずに抱っこし、「読んで」と言ったら読んであげることが大事なのです。
自分の言うことを聞いてもらえた子は、自己肯定感が高まり、親を信頼するようになるからです。
親世代も自分自身のアップデートが必要
私は、大人よりも子どものほうが、来たるべき時代の空気を敏感に感じ取れるのではないかと思います。
子どもは実際に自分がその時代を生きていかなければならないので、生物としての本能的な予感能力のようなものが働くのではないかと思うのです。
では、親御さんたちはどうでしょうか?
親御さんたちも、現在の平均年齢をはるかに超えて、長生きする可能性が高まっています。ぜひご自分をアップデートすることをおすすめします。
お子さんのためにも、ご自分のためにも、です。
親野先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。