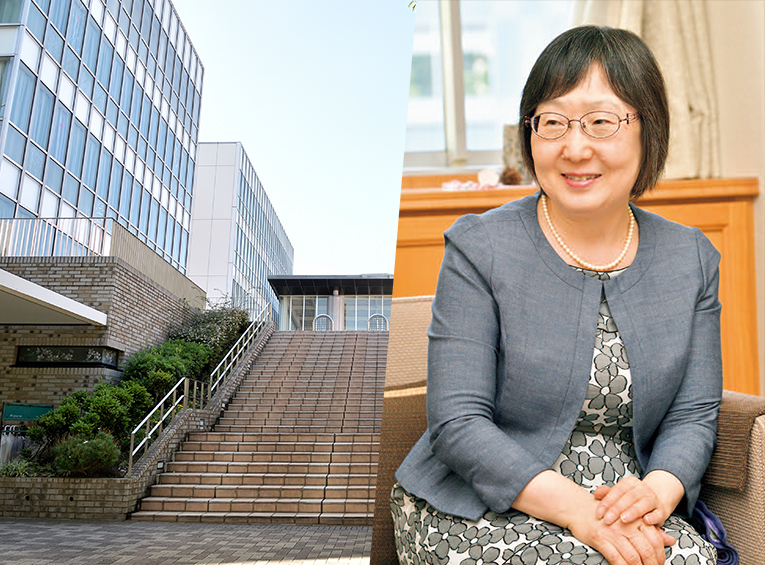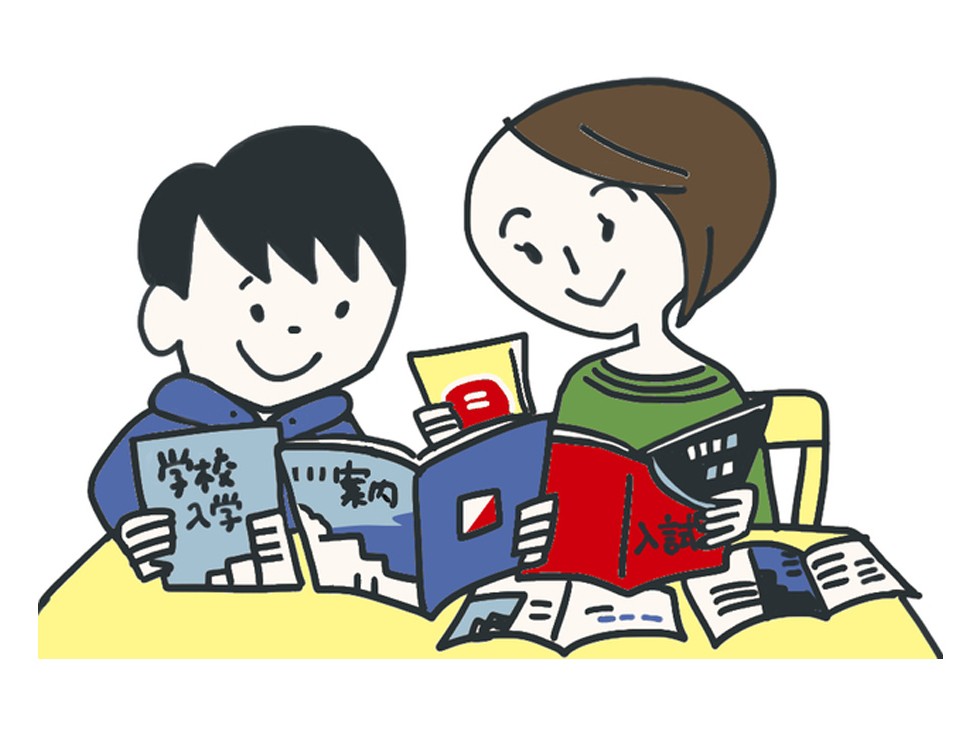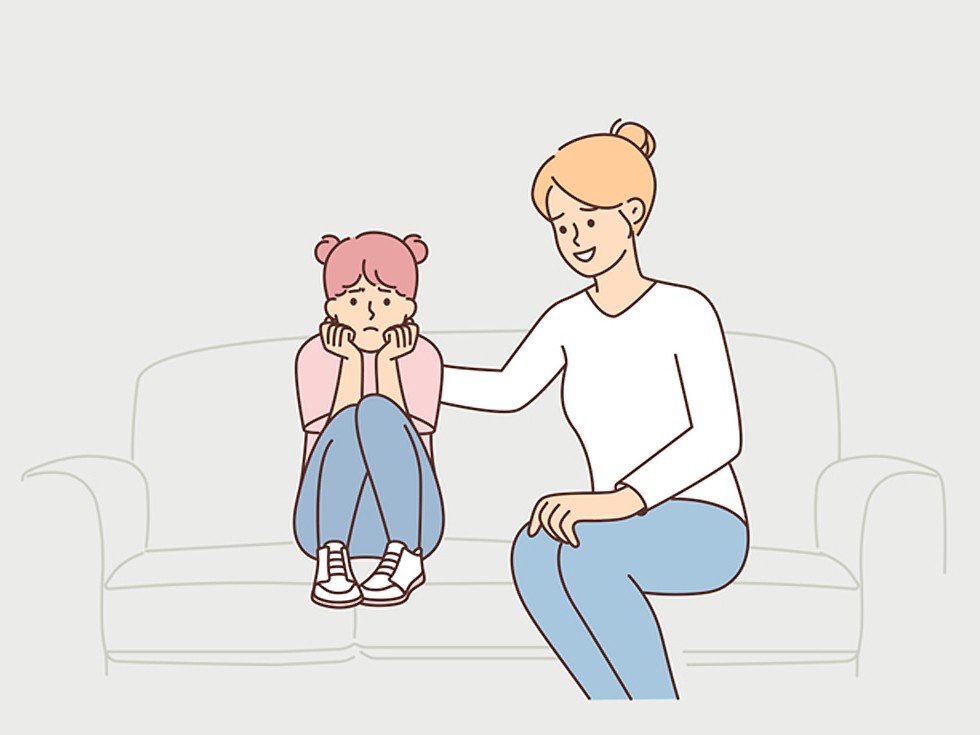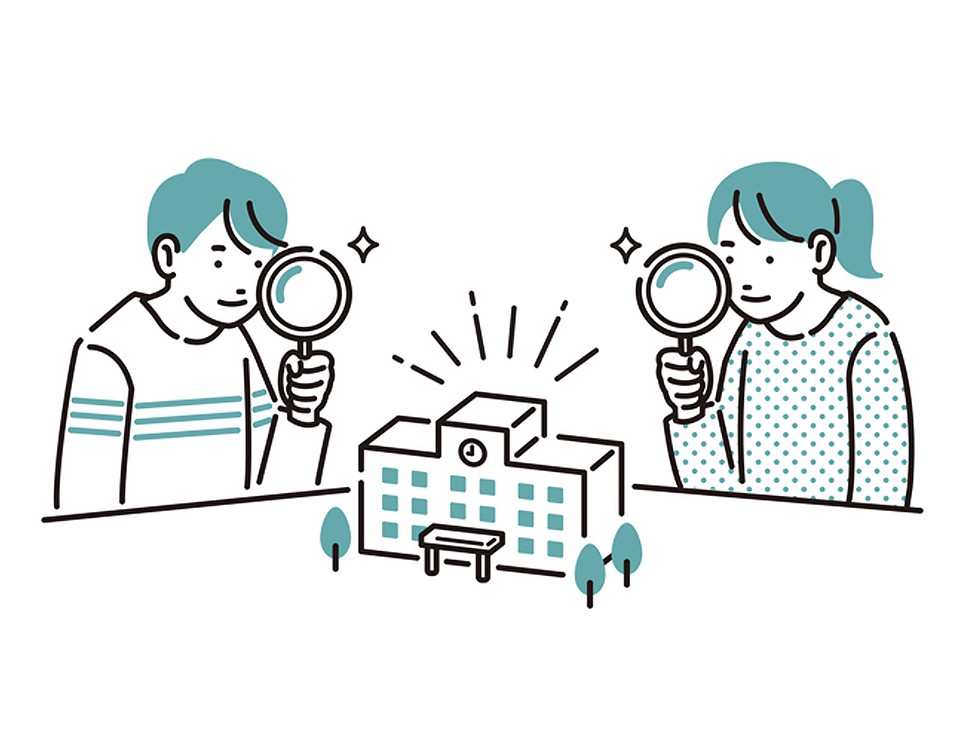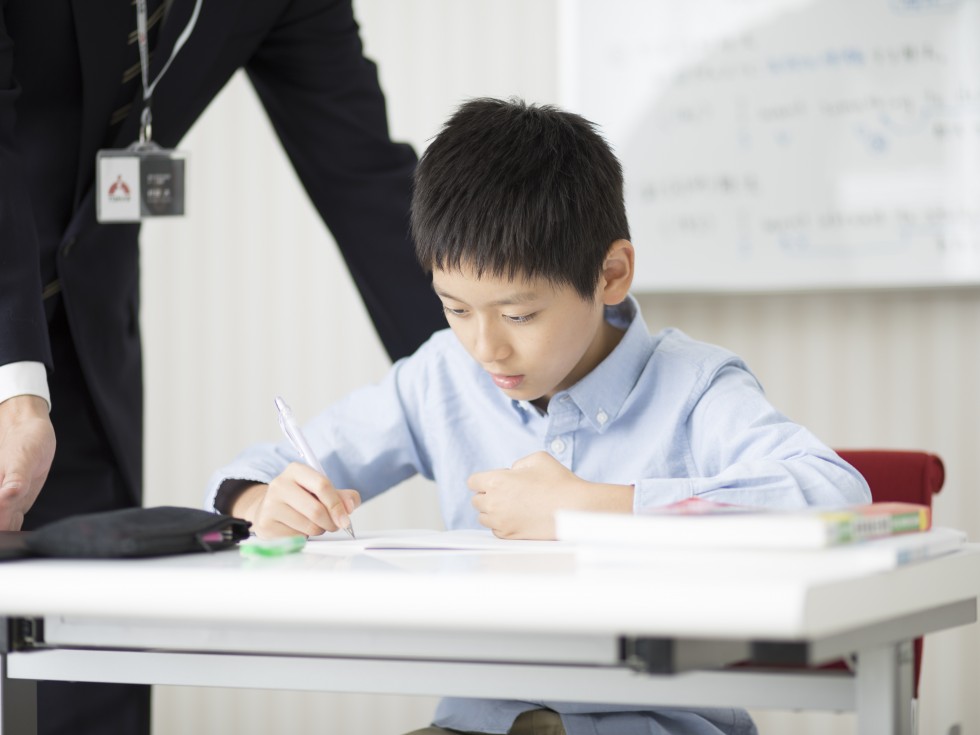
医学部に合格するための具体的勉強法
study tips to pass medical school
医学部入試では、とくに単科医科大を中心として、応用レベル・発展レベルの大変な難問がたびたび出題されます。たしかに、一部の最難関校では、このような難問でもある程度までは得点できなければなりません。しかし、そのような例外を除けば、医学部入試では難問の出来で合否が決まることはありません。医学部の受験戦略としては、「難問をとる」ことではなく、「基本問題・標準問題で落とさない」ことが必要なのです。
ここでは、「医学部という進路」「学習計画と学習戦略」「もっと知りたい医学部受験」のカテゴリで述べてきた「総論」からもう一歩踏み込み、「各論」として教科・科目別の対策と、個別対策を超えたより実践的な対策に触れていきます。医学部用の受験勉強に必要なステップである「入試基礎固め」「典型問題演習」「共通テスト対策」の具体的な方法論を確認し、日々の受験勉強に落とし込んでください。
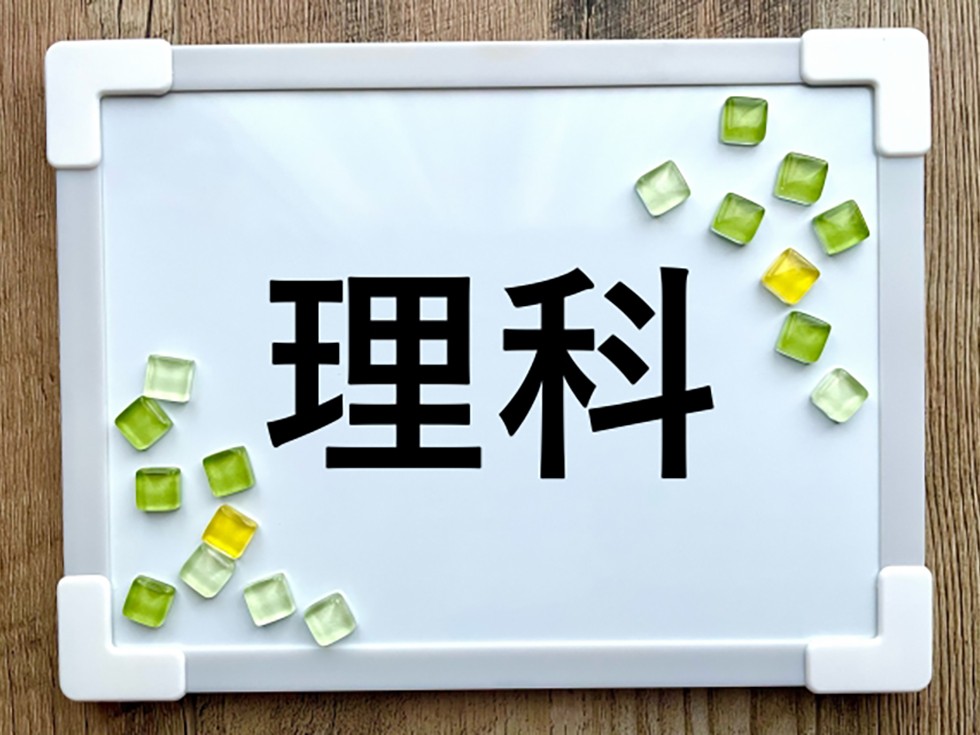
【医学部受験用 教科・科目別対策⑥】物理・化学・生物に共通する学習上の大前提
powered by MEDIC TOMAS
物理・化学・生物には、いくつかの共通点があります。科目別の「入試基礎固め」「典型問題演習」を開始する前に、理科全般に当てはまる学習上の大前提を確認しておきましょう。以下の3点です。
- 「先取り学習」が必須
- 「ビジュアル」からの理解が必須
- 「原理・法則」の理解が必須
ここからは、それぞれの大前提について説明していきます。
「先取り学習」が必須:「やり残し」はNG
「医学部という進路_おさえておきたい科目別対策の『前提条件』」の記事で述べたとおり、受験生の中には、医学部入試で課される理科2科目の対策が間に合わず、1科目は勉強し終えたものの、残りの入試科目を未履修としたまま試験本番に臨んでしまう人がいます。このような事態が起きてしまうおもな理由は、以下のとおりです。
- 英語・数学の対策に時間をとられすぎたため、理科の対策に手が回らなかった
- 学校の進度が遅かったため、入試直前になっても全範囲が終わらなかった
- 学校で英語・数学の学習を最優先するよう指導を受けてきたため、理科の対策が後回しになってしまった
このような事態が招く「理科のやり残し」を防ぐためには、英語・数学の学習だけに偏らず、本来習うべき学年よりも繰り上げて勉強するという「先取り学習」が必須です。「先取り学習」に適する参考書には、物理では『物理のエッセンス[力学・波動]』『物理のエッセンス[熱・電磁気・原子]』(以上、河合出版)、化学では『リードLight化学基礎』『リードLight化学』(以上、数研出版)、生物では『リードLight生物基礎』『リードLight生物』(以上、数研出版)などがあります。これらの本を使って、学校の進度とは無関係に、早く、そして先にどんどん進めていきましょう。
「ビジュアル」からの理解が必須:「資料集」を「受験の友」とする
理科は、特定の事象を扱うという性質については、数学と共通しています。しかし、異なる点もあります。それは、数学は世の中に存在しない抽象的な事象を扱うため実験が不要である一方、理科は世の中に存在する具体的な事象を扱うため実験が必要である、という点です。理科の学習では、実験から学べる視覚面の情報を理解することが大切です。つまり、情報を視覚的なイメージとしてとらえるという「ビジュアル」からの理解が必要なのです。
理科の学習教材では、実験が重視されています。実際、理科の教科書では、実験を構成する要素である「条件」「展開」「結果」について、多くの記述があります。しかし、教科書は、公式・定理など実験以外の記述も載せなければならないため、実験だけにフォーカスすることはできません。
実験を教科書よりもていねいに取り上げている学習教材があります。それは、「資料集」です。「資料集」は、読者に実験の視覚情報を与えてくれます。理科の受験勉強は、教科書よりもむしろ「資料集」から始めるのがよい、といっても過言ではありません。たとえば、「資料集」では、化学反応を学ぶうえで重要な「色」の情報もカバーされています。
「資料集」は、実験に関するたくさんの情報を含みます。受験勉強の最初だけでなく、最後まで使いましょう。実際、医学部合格者には、「資料集」をボロボロになるまで読み込んだという人たちがいます。よく使われているのは、『フォトサイエンス物理図録』『フォトサイエンス化学図録』『フォトサイエンス生物図録』(以上、数研出版)です。「資料集」を、あなたの勉強に伴走する「受験の友」として愛読しましょう。
「原理・法則」の理解が必須:「試行錯誤」を繰り返す
理科は、「暗記」の側面を持つとともに、「理解」の側面も有しています。理解しなければならないのは、実験によって扱われる事象の背後にある「原理・法則」です。
先ほど述べたように、実験は「条件」「展開」「結果」の要素を含みます。入試問題であらかじめ与えられる情報は、主として「条件」です。「展開」「結果」は、多くの場合、問題文の「条件」から自分で分析・考察していく必要があります。先に挙げた「原理・法則」とは、実験における「展開」「結果」を導き出すために必要な思考の型です。
「原理・法則」は、単体で覚えても意味はありません。前提となる実験の「条件」はケースバイケースであり、「展開」「結果」が実験ごとにまったく異なるからです。
「原理・法則」の習得には、分析・考察の段階において、頭の中で「試行錯誤」を繰り返すことが求められます。これはつまり、所与の「条件」にもとづいて頭の中で思考をグルグルとめぐらせるプロセスを意味します。これは、たとえば、「そもそも、この実験を行う理由・目的はどこにあるか」「この結果はどのような展開をへて導かれたのか」「この結果からどのようなことがいえて、ほかの実験にどう応用できるか」などと、深く、順序立てて考えていくことを意味します。思考の型は、実験の過程をていねいに追う訓練によってしか身についていきません。
頭の中での「試行錯誤」は「
「原理・法則」理解用の定番書は、物理なら『大学入試 漆原晃の 物理基礎・物理[力学・熱力学]が面白いほどわかる本』『大学入試 漆原晃の 物理基礎・物理[電磁気]が面白いほどわかる本』『大学入試 漆原晃の 物理基礎・物理[波動・原子]が面白いほどわかる本』(以上、KADOKAWA)、化学なら『理系大学受験 化学の新研究』(三省堂)、生物なら『生物合格77講【完全版】』(ナガセ)などです。これらは、頭の中での「試行錯誤」の指針を与えてくれる本です。教科書や資料集に出てくる実験の内容でわからないところがあったら、このような「調べ物用の辞書的な本」を使って「原理・法則」の理解を深めていきましょう。
以上のような大前提を踏まえたうえで、物理・化学・生物各科目の「入試基礎固め」と「典型問題演習」に入っていきましょう。
■本気で医学部をめざすなら……医学部受験専門の個別指導塾・予備校[メディックTOMAS]
https://www.tomas.co.jp/medic/
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。


![[体験談]わが子がボーディングスクールへ合格するまで](/schola/common/images/uploads/2020/09/3684775_m-980x735.jpg)