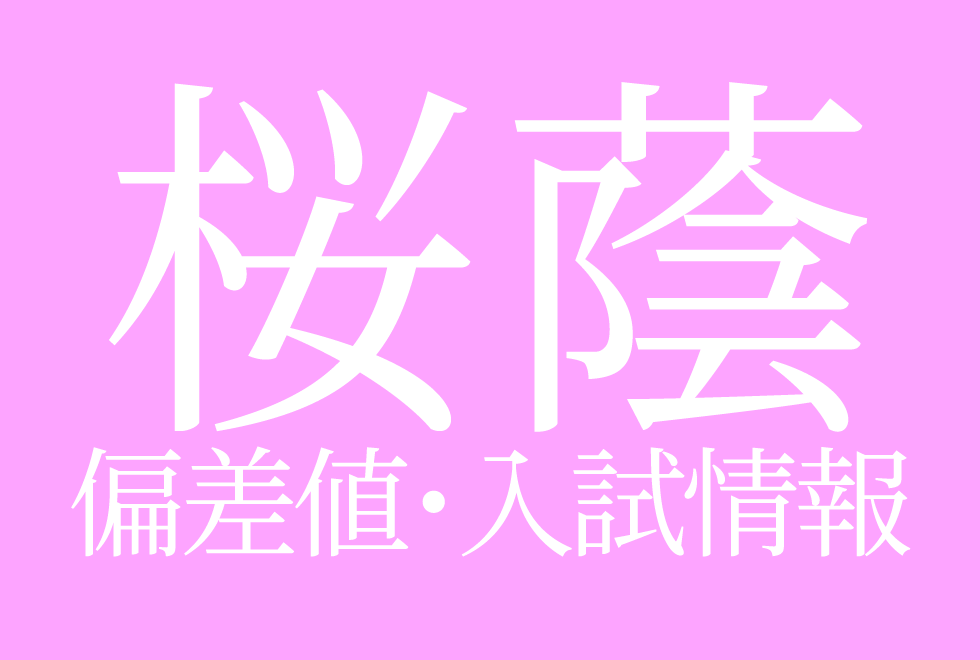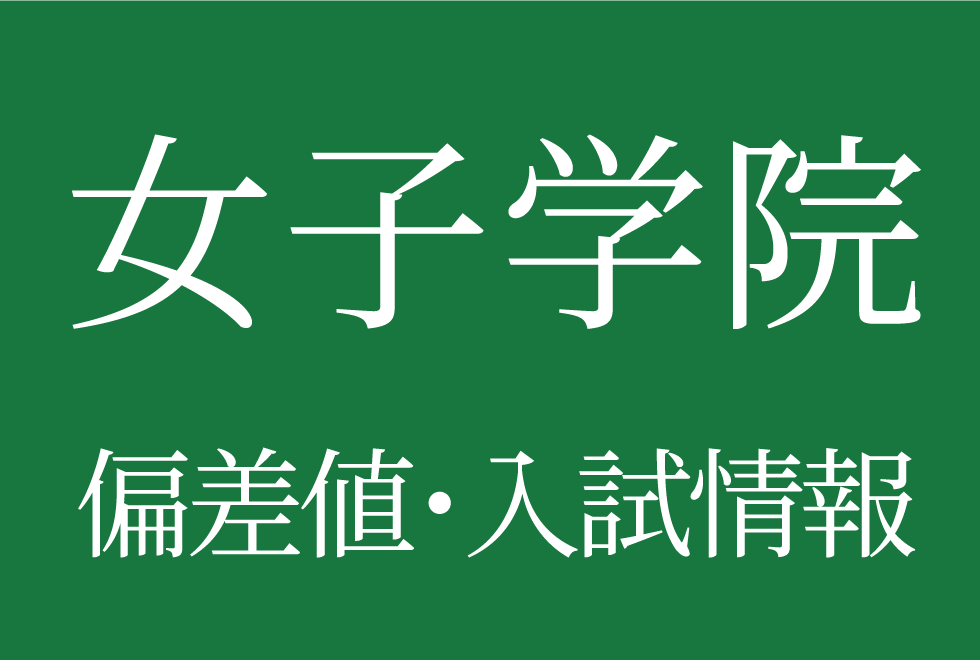夏の学習法

夏までに仕上げておきたい
小6 難関校志望者
教科別チェックリスト
秋から志望校対策を有利に進めるためには、夏休み中にどこまで基礎を徹底できるかが勝負になります。優先順位をつけて、一つひとつ確実に仕上げていきましょう。
<POINT>
チェックリストは優先度の高い順に上から下へと並んでいます。上から順に潰していきましょう。
算数
培ってきた基礎力・応用力をさらに磨き上げ、理解を深めていきましょう。公式や定理の原理を自力で導いたり、自分で問題をつくってみたりと、創造的な取り組みも必要です。
 計算の工夫と精度のアップ
計算の工夫と精度のアップ
複雑な計算や逆算、特殊な計算の工夫(平方数や円周率の九九など)の仕方を身につけましょう。ハイレベルな学校ほど、複雑な計算が必要となります。
 数の性質や規則性の応用
数の性質や規則性の応用
最難関校では必須単元です。様々な問題にチャレンジし、試行錯誤を重ねて経験を積みましょう。
 応用・発展的な文章題
応用・発展的な文章題
比を利用した問題や条件が複雑な文章題などに挑戦しましょう。条件整理の力が問われます。
 平面図形の応用問題
平面図形の応用問題
平面図形の性質や比、相似などを組み合わせた応用問題に挑戦しましょう。基本形を発見する力も求められます。
 立体図形の応用問題
立体図形の応用問題
くり抜きや組み合わせ、切断された複雑な立体に関する問題に取り組みましょう。正確で乱れのない計算処理能力が問われます。
 場合の数の応用問題
場合の数の応用問題
推理や場合分けの使いこなし、もれや重複なく数え上げる手順を組み立てる論理思考力が問われます。
国語
文章のより一層深い読み取りや、多量の情報処理が求められます。これらの力は一朝一夕には養われませんから、日々の積み上げが大きな差になってあらわれることになります。
 漢字・ことばのレベルアップ
漢字・ことばのレベルアップ
志望校の傾向に合わせて、知識や漢字のレベルをさらに上げていましょう。
 出題者の意図を考える
出題者の意図を考える
問題を作る側の考え方を理解することで、解答の精度が増すだけでなく、文章をより深く理解することができるようになります。
 随筆・韻文の理解
随筆・韻文の理解
随筆や韻文の読解には、背景となる教養や世間知が必要です。大人の世界では当たり前である知識を身につけ、随筆や韻文の世界を理解しましょう。
 自由記述問題
自由記述問題
最難関校では頻出の自由記述形式問題について、記述の作法や手順からしっかりと身につけていきましょう。
 出題の理念の理解
出題の理念の理解
最難関校の国語の入試問題は、「それぞれの学校の求める生徒像や教育理念」を反映させて作られています。志望校への理解と研究を深めておくことで、より精度の高い解答づくりができるようになっていきます。
理科
未知の知識をその場で理解して考える問題や、高度な実験・考察問題に対応する力が要求されます。付け焼き刃ではない、本質の理解に努めましょう。
 暗記テストの継続
暗記テストの継続
重要事項に関しては反復・継続して暗記テストをおこない、完璧に身につけましょう。また、余裕があればその量も増やし、意味や仕組みまで深く理解しておくと更に有利になります。
 知識の関連と精度のアップ
知識の関連と精度のアップ
例えば二酸化炭素は、気体の性質の他、光合成や呼吸にも関連します。このように、分野を横断する知識の関連を意識した学習を進めましょう。
 天文分野の強化
天文分野の強化
上位校では頻出となっています。地球・月・惑星の自転や公転に関する応用問題に挑戦しましょう。
 実験データからの考察
実験データからの考察
与えられたデータや実験が意味するものを考察する問題への対策を強化しましょう。記述・論述問題も出題されます。
 初見問題への対応
初見問題への対応
未知の内容について、その場で実験や解説を理解して解く問題に対する訓練が必要です。学習してきた内容と結びつけて考えるにはどうしたらよいのか、そのアプローチ法を身につけましょう。
社会
基礎知識はもちろん、テキストや授業で学んだ知識が日常にどう活かされているのか、身の回りの事象と結びつけて捉える視点が大切。公民分野の知識もここで定着させましょう。
 知識暗記の継続
知識暗記の継続
地形、年号、人物、憲法、統計などに関する知識を日々継続して確認しましょう。
 統計からの考察
統計からの考察
統計データと地理・歴史・政治や経済の知識を結びつけ、データから考察する力を養いましょう。近年の難関校入試では、特に必須の力です。
 文化史・テーマ史
文化史・テーマ史
文化や特定のテーマに沿って各時代を整理し直し、文化的な特色の背景となった歴史について理解を深めましょう。
 近代史と政治・経済
近代史と政治・経済
現代の社会の情勢(少子高齢化や財政赤字の拡大、領土問題や国際紛争といった社会問題など)と近現代の歴史を結びつけ、現代社会に関する問題への理解を深めましょう。
 論述問題対策
論述問題対策
近年の入試では、データから推論を組み立てたり、社会問題に対する身近な取り組みを論じたりなど、創造的な取り組みが求められることが多くなっています。正しい論述の方法を身につけるようにしましょう。
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。