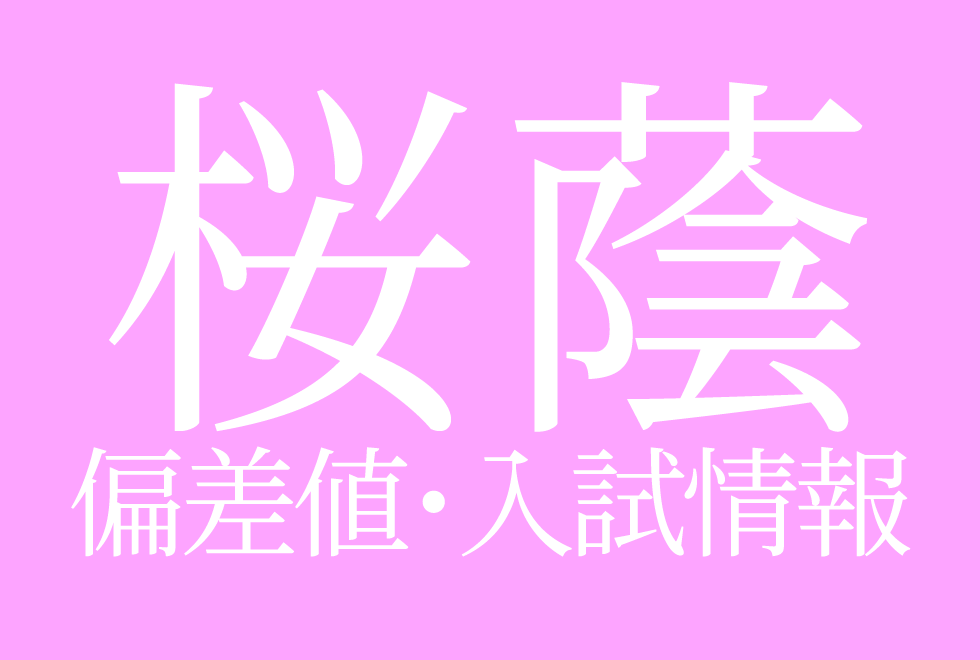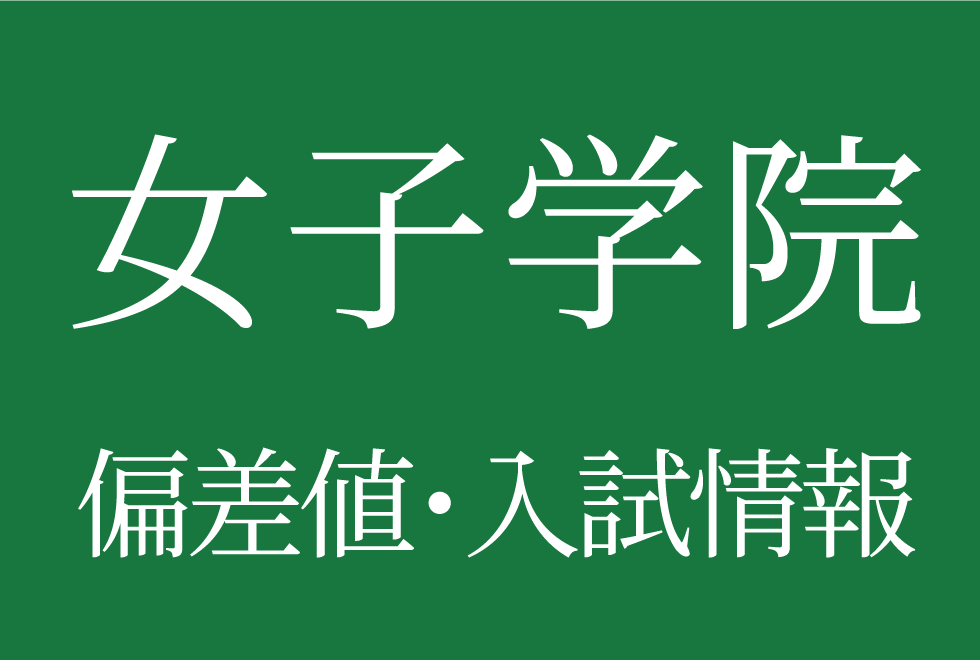最難関校合格を勝ち取る 中学受験の「理科」勉強法
Science Study Tips for Top Junior High School Entrance Exams
最難関校受験生であれば、多くの子どもが受験学年までに理科用語や暗記事項はひと通り覚えています。しかし、そういう受験生であっても、「記憶したことを活用して問題を解くこと」「これまで見たことがない科学的事象を考察すること」「長い問題文や複雑な図表から、設問の要求に応じて必要な情報を読み取ること」などは苦手だというケースがよく見られます。一方、最難関校の入試問題は、受験生のそのような弱点を突き、試験という現場での対応力を測ります。合格を勝ち取るためには、このような厳しい出題でも手堅く得点できなければなりません。
以下では、最難関校入試の理科で1点でも多くもぎ取るための実践的な勉強法をご紹介いたします。
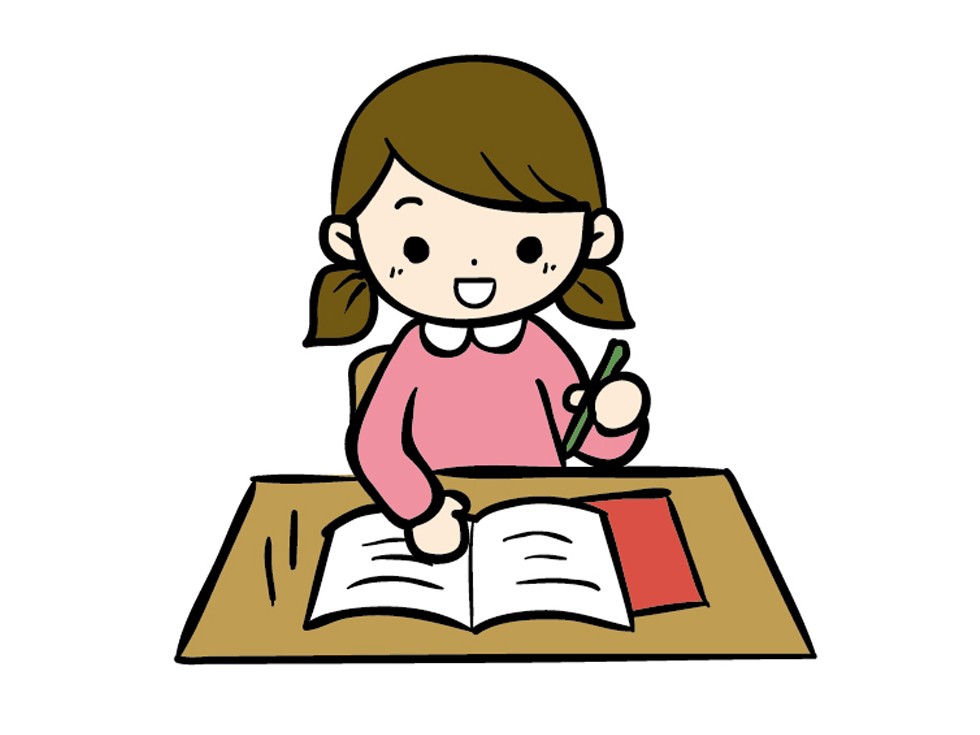
【中学受験の「理科」勉強法③】合格点をとるために必要な「設問形式別対策」の方法
powered by Spec. TOMAS
ここでは、中学受験理科の設問形式別対策として、「合格点をとるために必要な『分野別対策』の方法」の記事で扱った内容をさらに掘り下げていきます。
「知識問題」対策
一問一答問題集は「逆」に使う
たとえ最難関校の入試であっても、「知識問題」はけっして消滅しておらず、依然として出題され続けています。このような出題に対応するために必要なのは基礎の定着ですが、その場合にやりがちなのが、一問一答問題集だけに頼ってしまうという勉強法です。多くの受験生が、「~は何といいますか」のように用語を答えさせるだけの問題を解くだけで満足してしまうのです。
入試の基礎として大切なのは、用語そのものよりもむしろ、上の「~」の部分で説明される、その用語の意味内容・概念です。一問一答問題集を使う勉強では、ただ単に用語を答えるだけでなく、用語から意味内容・概念をたどり、それらを口頭や文章で説明してみましょう。つまり、一問一答問題集を「逆」に使ってみるのです。
「読んで覚える」よりも、「読んだことを思い出す」やり方が有効
子どもたちがつい陥りがちな勉強法は、ほかにもあります。それは、何度も読んで覚えようとするというやり方です。読んで覚えようとすることには限界があります。記憶というものは、一方的なインプットだけでは定着しないからです。
記憶の定着には、「読んで覚える」方法よりも、「読んだことを思い出す」方法のほうが有効です。記憶は、「さっき読んだ教材に書かれていたことって、何だっけ?」などというように、書かれていた用語、あるいはその意味内容や概念を再現していく過程で定着します。つまり、アウトプットを通じて記憶が強化されていくのです。
アウトプットの方法は、いくつかあります。たとえば、「書き出してみる」「口に出して言ってみる」、あるいは「問題を解きながら思い出そうとする」などです。それぞれ試してみましょう。
問題演習でも生きる、知識の「ネットワーク化」
「合格点をとるために必要な『分野別』の方法」の記事では、暗記事項はそれぞれのつながりをおさえていくこと、つまり、「ネットワーク化」して覚えていくことが大切だと述べました。
この「ネットワーク化」という手法は、問題演習にも応用可能です。具体的には、たとえば、「出てきた問題に関連する周辺知識をまとめて整理する」「誤答の選択肢に含まれる間違い箇所を正しい情報に訂正する。わからなかったら、調べながら訂正する」などをさします。
「思考力問題」対策
解いたプロセスはノートに残す
「思考力問題」の種類には、「計算問題」や「初見問題」などがあります。「計算問題」は、具体的な数値を求めさせる問題です。また、「初見問題」とは、多くの受験生が体験したことがない非定型的な科学的事象を考察させ、試験という現場での対応力を測る出題をさします。
「思考力問題」のトレーニングで大切なのは、問題を解くプロセスを自分の言葉で表現することです。頭の中で考えておしまいにしてはなりません。思考過程は必ずノートに書き、文章のかたちで記録しておきましょう。
子どもたちは、小学校入学以来、「ノートをとりなさい」「計算式を書きなさい」と繰り返し言われて育っています。しかし、多くの子どもは、「なぜノートが必要なのか」が把握できていません。受験生の中には、「こんなの、簡単。暗算で解けちゃうよ」などとうそぶく子までいます。そのような子には、「解いたプロセスを計算式として残すことに意味があるのだよ」などと話し、ノート作成の目的を伝えてあげることが必要です。
「ノートとり」は、解いたあとの「振り返り」を行うために必要
では、なぜここまで「ノートとり」の重要性を強調するのでしょうか。それは、「思考力問題」の演習では、「この答えはどのようなプロセスで導かれたのか」という、解いたあとの「振り返り」が不可欠だからです。
「思考力問題」のトレーニングで大切なのは、問題を解く行為よりもむしろ、問題を解く過程です。受験生は、問題を解きながらさまざまなことを学んでいきます。問題の解きっ放しは、あまりにもったいないことです。
「思考力問題」の演習では、正答率の向上よりも、問題の「解き直し」、すなわち「復習」を重視しましょう。復習のポイントは、「どのように情報を整理したか」「どこからヒントを得たか」「どのような考えにもとづいて計算式を立てたか」などです。このような点に注意しながら入念な「振り返り」を行い、思考回路の性能を高めていってください。
「読解問題」対策
「拒絶反応」が起きないよう「耐性」をつけておく
最難関校の理科入試問題には、長い問題文や複雑な図表の読み取りが必要となる「読解問題」が多数出てきます。これは、多くの受験生が苦手とする出題タイプです。
「読解問題」対策として大切なのは、きわめて当たり前ではありますが、文章量自体に慣れていくことです。そのため、子どもには低学年のうちに、あらかじめ「読解問題」に対する「耐性」を植えつけておきましょう。たとえば、「入試にはこんなに長い問題文も、難しそうな図表も出てくるのだよ」と予告しておくのです。そうすれば、子どもが実際の出題に触れたときに「こんな問題、解けないよ」という「拒絶反応」を起こす可能性が回避できます。受験学年から始まる本格的な対策の前触れとして、子どもに心の準備をさせてください。
解答根拠には「目印」をつけよう
ここでは、実際に「読解問題」を解いていく際の留意点をお話しします。
「読解問題」では、設問の要求を踏まえたうえで解答根拠となる情報を問題文や図表から読み取る必要があります。その際に必要なのは、問題文の中から読み取れた解答根拠箇所に視覚的な「目印」を残すことです。具体的には、たとえば、「解答根拠箇所に線を引く」「問題冊子や過去問集の余白やノートなどに、問題文や図表の読み取り過程で考えたことをメモとして残す」などです。
「問題文の情報整理」がカギ
このように、解答根拠を「ビジュアル」として残すことには、問題が解きやすくなるという効果だけでなく、「思考力問題」対策の項目で述べたように、解いたあとの「振り返り」にも役立つという効果もあります。自分の思考過程が記録として残せていれば、たとえ正解できなかったとしても、自分がどこで間違えたのかをたどることが可能となるからです。
ここまで述べてきた「読解問題」対策のポイントは、「問題文の情報整理」という点に尽きます。問題文は、ただ目で追って読むだけでなく、手を動かして読んでいきましょう。これは、国語の「読解問題」対策にも通じる、とても大切な姿勢です。
「時事問題」対策
題材になりやすいのはタイムリーなニュース
「時事問題」の出題には、大きな特徴があります。それは、題材としてタイムリーなニュースが使われるケースが多い、という点です。
タイムリーなニュースにもとづく出題には、いくつかのパターンがあります。
1つ目のパターンは、「大きな出来事のメモリアルイヤーに関連する出題」です。たとえば、「関東大震災100年」というメモリアルイヤーだった2023年の入試では、地震に関する出題が目立ちました。もしかしたら偶然なのかもしれませんが、学校側がメモリアルイヤーにちなんで意図的に出題した可能性もゼロではないはずです。
2つ目は、「理科にからむ出来事に関連する出題」です。たとえば、かつて、駅の構内で空き缶が爆発するという騒ぎがありました。爆発の経緯は、「アルミ缶と、その中に入っていたアルカリ性洗剤が接触☞アルミ缶とアルカリ性洗剤が化学反応を起こし、水素が発生☞水素がアルミ缶内に充満して爆発☞水素がアルミ缶を破壊」というものでした。その影響なのか、爆発が起きた年の入試では、「水素の発生」に関する出題が散見されました。
3つ目は、「ニュースそのものの知識を問う出題」です。たとえば、ノーベル賞を日本人が受賞すると、受賞者の氏名を尋ねる問題が出てくる場合があります。
対策の基本は「単元学習」
以下では、ここまでに述べた「時事問題」に関する出題パターンを踏まえ、具体的な対策法をお話しします。
ここまでのお話から、もしかしたら、「ニュースから出題されているのだから、『時事問題』の対策にはニュースを見ればよい」と思われた方がいるかもしれません。たしかに、ふだんからニュースを見ていれば、時事的な知識は相当なレベルまで増えていきます。しかし、「時事問題」対策のためだけに毎日必ずニュースを見ることは、入試対策としてはむだが多い、といわざるをえません。
拍子抜けしてしまうかもしれませんが、タイパの面から最も現実的な「時事問題」対策は、じつは「単元学習」の徹底です。「単元学習」が「時事問題」対策を兼ねると考えてください。
対策専用の教材を使うという手もあり
もっとも、志望校の過去問に「時事問題」が出ている場合には、個別の対策が必須です。しかし、その場合でも、ニュースを見ることよりも、「時事問題」に特化した教材を使うことを優先してください。教材には、毎日一定ペースで、分量と時間を区切って取り組んでいきましょう。「時事問題」対策のやりすぎは禁物です。
過去問の総合的対策
ここまでの個別具体的な「設問形式別対策」を踏まえた総論として、最後に、志望校の過去問対策に関する話題を取り上げます。
一問一答問題集自体は必須
先ほど、多くの受験生が一問一答問題集を正しく使えていないとお話ししました。しかし、ここで誤解なきよう強調したいことがあります。それは、一問一答問題集そのものはけっして不要ではなく、受験対策に必須の教材である、ということです。一問一答問題集には、入試問題を解くうえで基礎となる理科用語が網羅されています。一問一答問題集として有名な教材は、たとえば『理科コアプラス』(日本入試センター)や『理科メモリーチェック』(みくに出版)などです。
過去問対策は、これらの教材に載っている用語の理解なしには成立しません。その前提となる基礎力養成の段階では、知識の習得を最優先しましょう。
対策しづらい「図表読み取り問題」は、「類題の過去問」で演習
ここでは、「読解問題」の過去問対策について、ここまでに触れてこなかった内容をお伝えします。
先ほど、「読解問題」では解答根拠の読み取りが必要だとお話ししました。読み取りの対象となるのは、問題文と図表の両方です。とくに、図表の読み取りについては、解くうえでヒントとなるデータをグラフなどから抽出していく作業が必要です。しかし、「図表読み取り問題」に特化した教材は、少なくとも市販参考書には皆無です。では、どう対策すればよいのでしょうか。
「図表読み取り問題」対策として有効なことがあります。それは、過去問の中から志望校の過去問と出題傾向が似ている他校の過去問を選び、「類題」として解くことです。
最難関校のうち、「図表読み取り問題」が頻出するのは渋谷教育学園幕張中と渋谷教育学園渋谷中です。両校の入試問題では、非常に複雑な図表のデータ処理が求められます。「図表読み取り問題」の対策においては、最難関校の過去問から「類題」を探し出し、たくさんの分量をこなし、なおかつ何度も反復して解いていく必要があります。
もっとも、志望校の類似過去問を見つけることは、保護者、ましてや子ども自身には難しいはずです。その場合には、プロ指導者に頼るという選択肢もぜひ検討してください。
まとめ
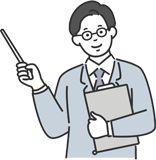
最難関校の設問形式別対策で重要なのは、「問題を解いたあとのプロセスの振り返り」です。復習時には、ノートを見直し、問題を解いたときにたどった思考過程を再現してみましょう。
■夢の志望校合格に導く 低学年からの難関校対策個別指導塾[スペックTOMAS]
https://www.tomas.co.jp/spec/
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。