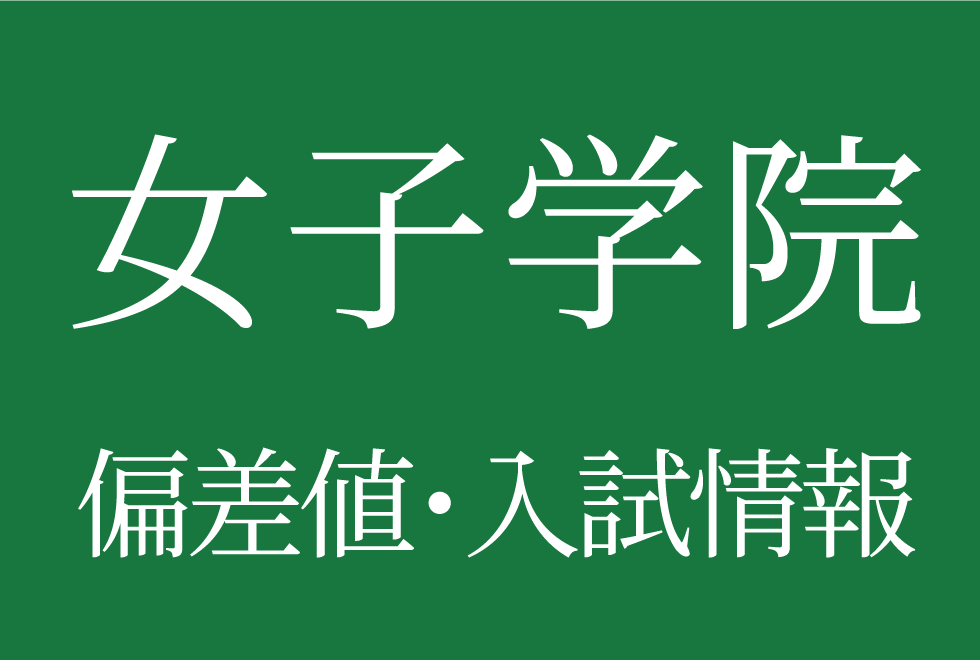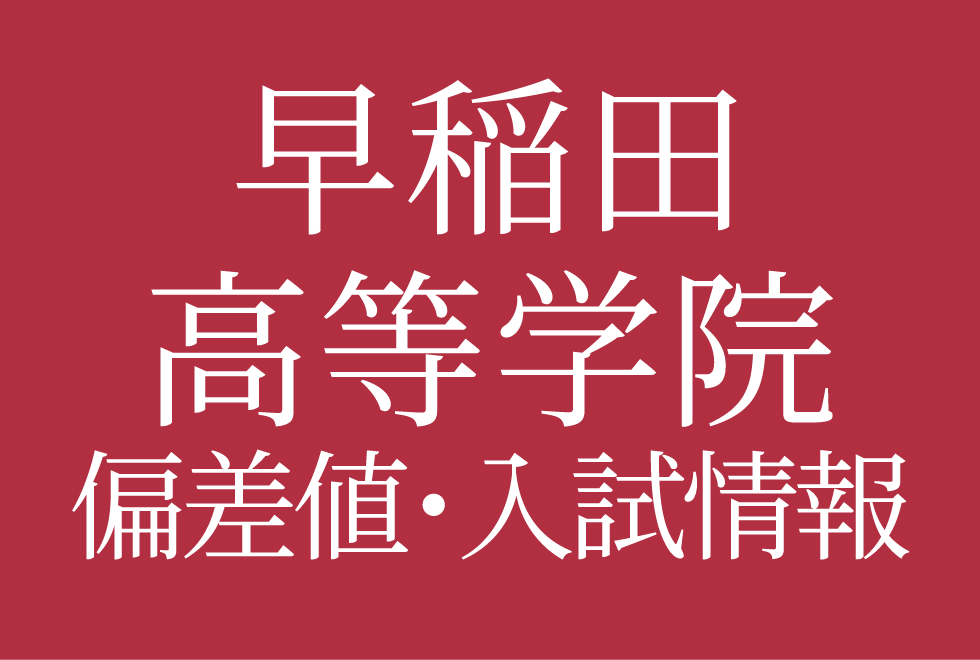さきよみ中学受験

全国学力テストに見る「大学受験に必要な学力」
知識を「覚えているか」ではなく、「活用して問題解決ができるか」
7月31日、文部科学省は「全国学力・学習状況調査」、いわゆる「全国学力テスト」の今年度の結果を公表しました。全国の小学6年生と中学3年生を対象に、4月18日に全国一斉に行われたものです。
小学校では国語と算数、中学校では国語と数学、そして今回初めて英語も対象となりました。また、学校に対して、授業がどのように改善しているかをたずねる「質問紙調査」も実施されました。
今回の全国学力テストの出題の特徴は、「知識と活用を一体的に問う問題」です。授業で習った知識を「覚えているか」を問うのではなく、「活用して問題解決ができるか」を問う問題になっているのです。文章内容を把握する読解力や、わかったことや自分の意見をまとめて書く思考力や表現力などが試されます。
小学校の国語では「公衆電話」についての文章を読み、使い方や特徴をまとめて書く問題が出ました。正答率は28.9%と低く、相手にわかりやすく情報を伝達するために書き方を工夫し、まとめて書くことに課題があることがわかりました。
中学校の国語では、広報誌の情報を用いて、根拠のある意見文を書かせる問題が出ました。正答率は18.3%と低く、情報を適切に用いて正確に書くことに課題があることがわかりました。
算数・数学を見てみましょう。
小学校で31.3%と低い正答率になったのは「数と計算」の分野です。ある割り算の方法を取り上げて、「なぜこのような答えになるのか」理由を書かせる問題が出ています。単純な割り算の計算問題ではない点に注目です。
中学校では「関数」が、「図形」や「数と式」よりも正答率が低くなっています。冷蔵庫を買うのに式やグラフを用いて使用年数を比較させる、という問題が出されました。
今回から新たに加わった中学校の英語を見てみると、「聞くこと」「読むこと」はおおむねできていますが、まとまりのある文章を「書くこと」(正答率1.9%)や英語で即興的にやり取りする「話すこと」(正答率10.5%)に、課題があることがわかりました。
全国学力テストと新学習指導要領の考え方
ここまで読んで、「そんな問題を出すのか」と思われたかたもいるかもしれません。
これが今、国が推進する「知識の活用力」を試す問題なのです。
公式や漢字、英単語を思い出す力ではなく、初めて出合う課題を読み解き、自分の知識を用いて思考力や表現力を発揮するのが今後の学力なのです。
では、思考力や表現力はどうしたら身につくのでしょうか。
期待されているのは、新学習指導要領に盛り込まれた「主体的・対話的で深い学び」というキーワードです。
学ぶことに興味や関心を持ち(主体的)、さまざまな人との対話で考えを広げ(対話的)、得た知識を関連付けて解決策を考える(深い学び)――こうした授業が小中学校でできていれば、活用型の学力テストの課題はできるようになる、と考えているのです。
実は、今回の新学習指導要領は小・中・高とすべてこの考え方で一貫しています。
そして、大学入試は高校までの学力を試すものですから、知識だけでなく、活用力が身についているかを試すことになります。センター試験に代わって始まる「大学入学共通テスト」で記述式問題を導入し、4技能活用型の英語スコアを求めるのは、こうした理由からです。
「活用型問題」が解ける力を付けるのが今後の課題
冒頭で紹介した全国学力調査テストでは、「主体的・対話的で深い学び」になるよう授業改善をしているか、学校に質問しています。
「児童生徒が授業で課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいる」と答えた学校は小・中とも8割です。しかし、来年度から新学習指導要領が全面実施になる今の段階で、「どちらかと言えばそうは思わない」「そう思わない」と答えた学校もまだ14%程度残っており、早急な授業改善が求められます。
私立中高一貫校の入試や、教育内容においても「活用力」は注目されています。4教科で「活用型」の問題を出す傾向は高まっていますし、「適性検査型入試」のように教科融合型で、資料やデータを読み解かせる入試も増えてきました。入学後も「活用力」に注目して、論理的思考力や言語能力を高めるオリジナルの科目を設定する学校も出てきています。
すべての中学入試が全国学力テストのような問題形式になるわけではありませんが、少なくとも今の保護者が受験してきた入試とはひと味違う、活用型問題が解ける力をつけることが、中学入試だけでなく、その先の大学入試をも突破する学力になると言えるのです。
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。