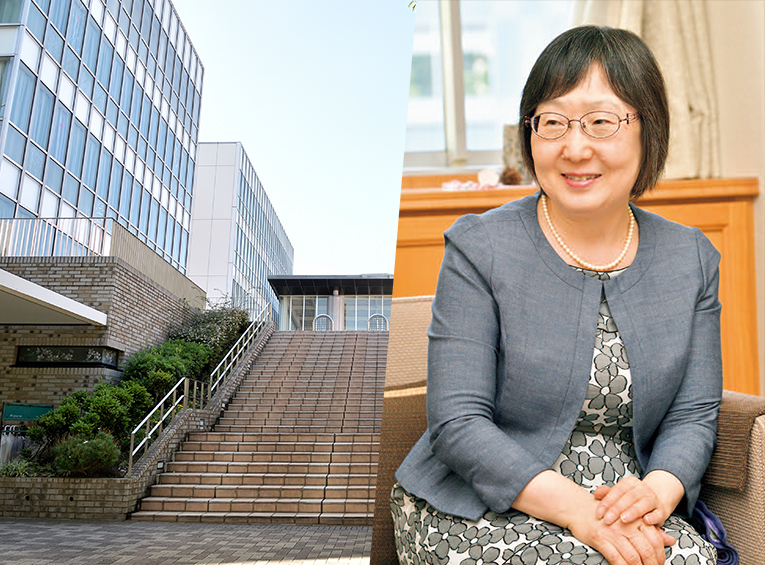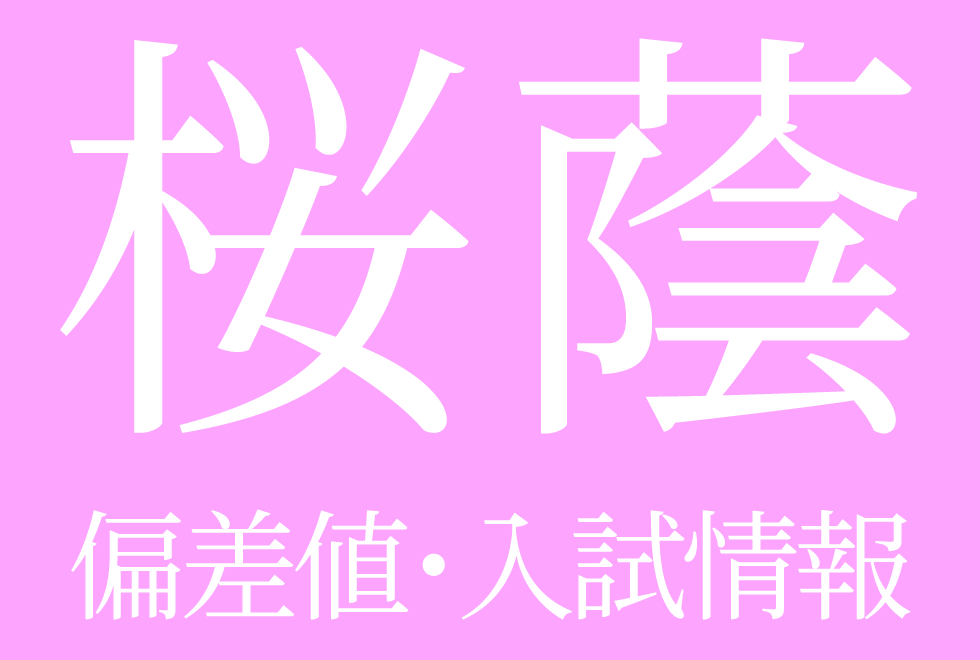合格点を取りに行く 一橋大「地歴」の勉強法
一橋大における地歴科目(日本史・世界史・地理)の個別学力検査では、例年大変ハードな出題が課されます。その難しさは、「複雑な資料を読み取らなければならない」点、「設問条件が厳しい」点、「解答として求められる記述量が多い」点などにあります。
たしかに、一橋大地歴の攻略は大変です。しかし、たとえ難攻不落に見えるそのような出題であっても、適切な教材、合理的な学習計画、傾向と対策を踏まえた正しい学習法などによって、合格点への到達は十分に可能です。ここでは、一橋大「地歴」の攻略に必要な情報をくわしく説明していきます。
*本記事がもとづく情報は執筆時点のものです。最新の情報はご自身で確認してください。

【一橋大の傾向と対策】一橋大「地理」の「出題傾向」
powered by TOMAS
一橋大「地理」の「出題形式」
2025年度からは出題範囲が「地理総合、地理探究」に変更
学習指導要領の改訂にともない、2025年度から、出題範囲が「地理総合、地理探究」に変更されました。「地理総合」は、「防災」など、身近で時事的なテーマを含みます。
後述するように、じつは、一橋大地理には、もともとニュース性の高いテーマを好んで出題する傾向があります。そういう意味で、一橋大地理の出題は、「地理総合」「地理探究」という新科目の導入以前からその理念を先取りしてきたといえるでしょう。現在の出題傾向は、2025年度以降も継続していくと思われます。
ほとんどが記述式のハードな出題
以下では、一橋大「地理」の出題における大問と設問のつくりを取り上げます。
例年の出題では、大問が3題に固定されています。しかも、ほとんどは記述式です。大問に含まれる一部の設問には、記号を答えさせたり、用語のみを記入させたりする形式も見られます。しかし、例年は、客観式が単独の設問として出てくるケースはありません。一橋大「地理」では、もし客観式が出てくる場合には、記述式にからめて問われるスタイルが一般的です。このような点から、一橋大「地理」の出題は実質的に「オール記述式」だといえます。
大問1題に対する設問数は例年3個、もしくは4個であり、大問で記述させる字数の合計は約1,200字です。設問1問あたりの指定字数は75~150字前後となっています。このように、一橋大「地理」では、求められる記述量が多いため、120分という長めの試験時間が設定されているものの、時間的な余裕はほとんどありません。時間に追われるヘビーな出題だといえるでしょう。
大問と教科書的単元が対応していない
以下では、一橋大「地理」の出題における大問のつくりと記述量について説明します。
一橋大「地理」の出題においては、大問と教科書的単元との1対1の対応関係は見られません。地理入試問題において標準的なのは、たとえば2025年度の共通テストのように、第1問:「産業」、第2問:「地域調査」、第3問:「自然環境と防災」など、大問と教科書的単元が1対1にひもづいているスタイルです。一方、一橋大「地理」の出題では、大問と教科書的単元の1対1の関連性はありません。このような「大問単位の対策が立てられない」という点に、一橋大「地理」対策の難しさがあります。
「たくさん書けそう」「自由に書けそう」に見えて、じつはそうではない
先述のように、一橋大「地理」の出題では、1問あたり75~150字前後という長めの字数が設定されています。しかし、求められる答案内容の多さに比較すると、求められる記述量の制約はけっして緩くありません。むしろ、「とても厳しい」と考えるべきです。よほど表現を工夫し記述を吟味して書かなければたちまち字数オーバーとなってしまいます。
さらにいうと、字数設定だけでなく、設定条件もとても厳しめです。一橋大「地理」の設問は、一見しただけだと、1問あたりの記述量が多いため、自分の考えをたくさん、自由に書ける余地がありそうに思えます。しかし、実際にはそのようなイメージとは正反対の、きわめて制約が多い出題です。その設定条件のきつさは、「問題文から読み取れる情報を忠実に反映しなければならない」点、「設問中で与えられる条件が、1つだけでなく複数である場合が多い」点などにあります。
以上から、一橋大「地理」の記述答案においては、「表現を凝縮する」ことや、「出題意図から逸脱しないよう、客観的に書く」ことなどが求められるといえるでしょう。
一橋大「地理」の「特徴」
「出るところ」と「出ないところ」の差が激しい
一橋大「地理」の出題に関する特徴で際立っているのは、入試地理最頻出テーマといっても過言ではない「地形図」からの出題がきわめて少ないという点です。たとえば、2020~2024年度の過去5年度では、「地形図」からの出題は1度もありません。また、「地形環境」「気候分布」「雨温図」などの定番テーマからの出題も例年は多くありません。
一方、ほとんど出題が見られないテーマとは対照的に、好んで出題されるテーマがあります。なかでも、発展途上国に存在する「現代的課題」が頻出です。とりわけ、アフリカとラテンアメリカがよく問われます(アフリカは2020・2023年度、ラテンアメリカは2023・2024年度にそれぞれ出題実績あり)。そのため、いわゆる「グローバルサウス」諸国についてはかなり細かい内容までおさえておくとともに、「現代的課題」に対する興味・関心も養っておく必要があります。
「初見資料」が頻出
地理では、地図・統計・グラフ・年表などの資料が頻出します。しかし、一橋大では、ほかの入試問題に見られるような定番資料はほとんど出題されません。
一橋大が好むのは、受験生にとってなじみが薄い、教科書・参考書・資料集などではまずお目にかからないマニアックな資料、すなわち「初見資料」です。たとえば、2024年度・大問1では、「コロンビア(大陸部)のコカ産地」という地図が出題されました。一橋大対策の過程でこの地図を見たことがある受験生はほとんどいなかったはずです。
一橋大は、「初見資料」の出題によって「知識の運用力」を試します。「初見資料」は、覚えてきた知識をそのまま当てはめても読み取れません。そのため、読み取りにあたっては、「これまでに身につけてきた知識をフル活用して思考する」ことと、「答案作成に必要な情報を素早く引き出す」ことの両方が求められます。
しかも、さらにやっかいなことに、一橋大「地理」では、1つの大問につき複数の「初見資料」が与えられます。この点から、一橋大「地理」は、受験生に複数資料を比較検討できる「分析力」があるかどうか試しているといえそうです。
おさえておくべき「背景情報」がたくさんある
上で述べたように、一橋大「地理」では「初見資料」が頻出します。「初見資料」を分析するためには知識が必要です。この場合の「知識」とは、「直接問われているわけではないが、背景としておさえておくべき情報」を意味します。たとえば「統計の前提情報」などです。
例を挙げますと、2022年度・大問1・問2は、地図などのヒントなしに資料のみでEU加盟国を特定させるという出題でした。この設問では、資料に示されている情報だけで加盟国を選ぶことは不可能なつくりとなっています。この設問を解くためには、EU加盟国に関する「加盟順」「人口」のような「統計の前提情報」を覚えていることが求められたのです。
一橋大「地理」の記述問題対策では、「背景情報」としておさえておくべき「関連知識」「派生知識」が膨大に存在すると考えてください。
「細かい知識」が直接問われる場合もある
先述のとおり、一橋大「地理」の出題では知識が一問一答式にきかれることはほとんどありません。しかし、だからといって知識が軽視されているというわけではないのです。年度によっては記述式設問にからめて高度な知識が問われる場合もあります。
たとえば、2023年度・大問2・問2では、「ボリビアのウユニ塩原周辺の地下に埋蔵されているレアメタルの鉱種とおもな用途の具体例」が問われました。正解は「リチウム」(鉱種)と「電気自動車の充電式電池」(おもな用途の具体例)ですが、これらは、入試レベルとしてはかなり細かい知識に属します。
「時事ネタ」が頻出
一橋大「地理」では、上述のような「細かい知識」だけでなく、各メディアで盛んに取り上げられている新しい話題が、有名なものからマニアックなものまで幅広く出題されます。以下は、一橋大「地理」の出題における「時事ネタ」の出題例(問題文中に記述問題の指定語句として出てきたケース)です。
- 2021年度・大問2・問1:「訪日外国人」
- 2021年度・大問3・問4:「クローン・タウン」
- 2022年度・大問3・問4:「水素のエネルギー利用に関する2種類の方法」
- 2022年度・大問3・問4:「カーボンニュートラル」「グリーンリカバリー」「地産地消」
上に挙げた話題のうちよく知られているのは「インバウンド」と呼ばれる「訪日外国人」くらいで、それ以外は、地理の学習内容としては相当に専門的です。なお、「クローン・タウン」とは、「目抜き通り沿いに国内外の巨大資本によるチェーン店が立ち並び、地場の個人経営店舗が廃業に追い込まれているという同質的な景観が広がる街」を意味します。
これらの「時事ネタ」に対応するためには、教科書や参考書だけでなく、新聞やニュースなどで情報をキャッチアップすることが必要です。
一橋大「地理」の「難度」
地理入試問題の最高峰
ここまで分析してきたように、一橋大「地理」では、記述問題の要求条件がとても高度で、「初見資料」の読み取りもきわめてハードです。また、問題文が何を求めているのか一読しただけではわからない設問も多く、高度な読解力も求められます。
このような点から、一橋大「地理」の出題はきわめてハイレベルだといえます。地理で高度な入試問題を出す大学にはほかにも東大・京大などがありますが、一橋大の難度が東大・京大を上回っていると考える指導者もいます。社会科学系の大学であることから、一橋大の入試問題からは、合格したら社会科学(法学・経済学・商学など)の学徒となる受験生に対してきわめて高い水準の学力を求めていることがうかがえます。
ハイレベルだが、攻略法は存在する
一橋大の出題には、「知識をストレートに問う」のではなく、「知識にもとづいて考えた結果を問う」という性質があります。その「考えた結果」には、「初見資料から直接読み取れたこと」だけでなく、「資料からは直接には読み取れず、自分で補って考えなければならないこと」まで含まれます。
「自分で補って考える」と聞いて、もしかしたら、「何か奇抜なことを書かなければならないのか」と思った人がいるかもしれません。しかし、心配する必要はありません。一橋大の出題で求められているのは、ゼロから新しいアイディアを提案することではなく、これまでの学習成果を答案にぶつけることです。
一橋大の出題者が受験生に要求しているのは、あくまで「未知の内容を既知の内容に結びつけて答える」ことです。たとえ初めて解くタイプの記述問題であっても、これまでに学んできたことを答案に反映できれば、合格点への到達は十分に可能です。一橋大の過去問や模試は、「いま目の前で解いている問題が、これまで習ってきたどのような内容と関連しているのか」を強く意識しながら解いていってください。
まとめ

一橋大「地理」の特徴は、出題難度の圧倒的な高さです。その一方、頻出テーマとそうでないテーマの違いが歴然としているため、好んで出題されるトピックに絞った対策が立てやすいという特徴もあります。とくに、発展途上国が抱える「現代的課題」がよく問われます。しっかりおさえておきましょう。
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。