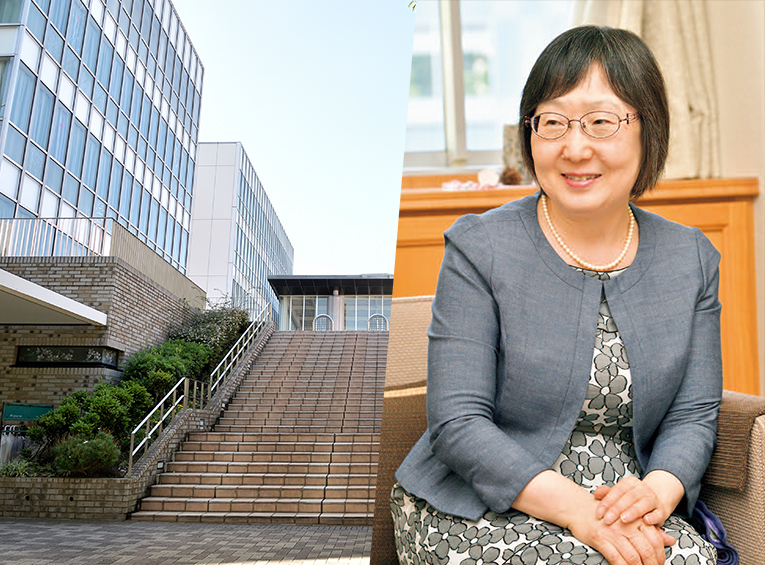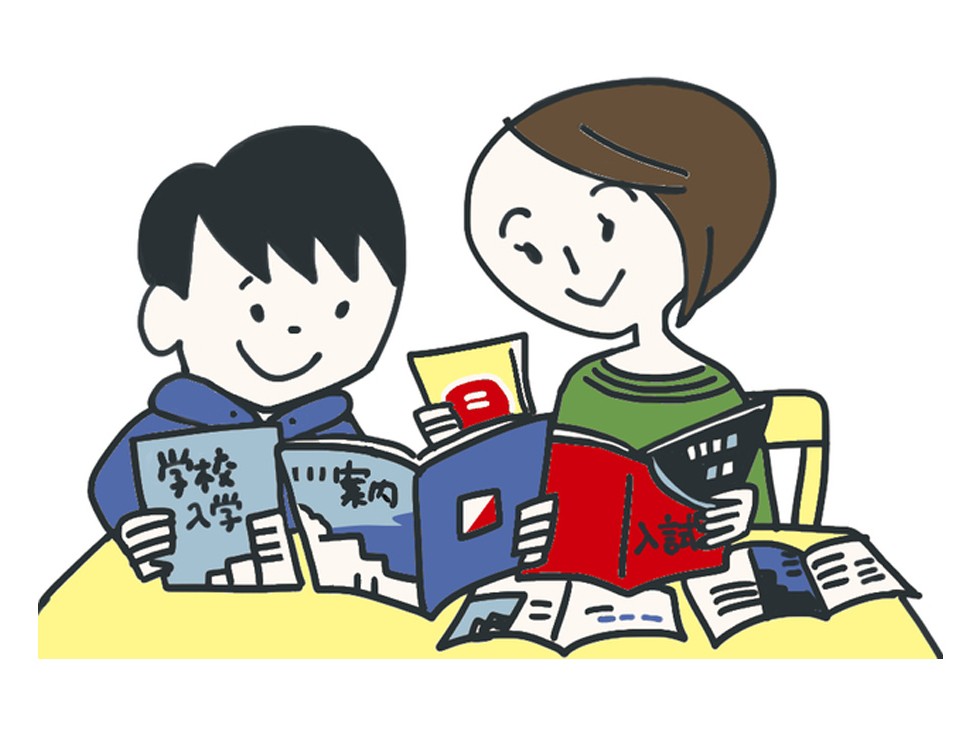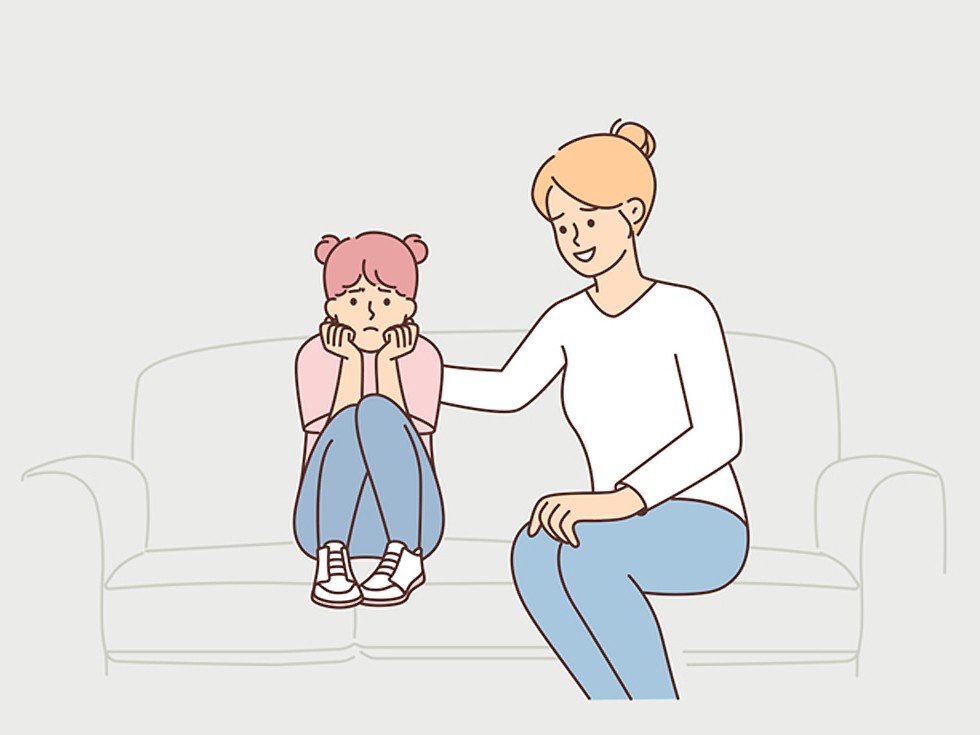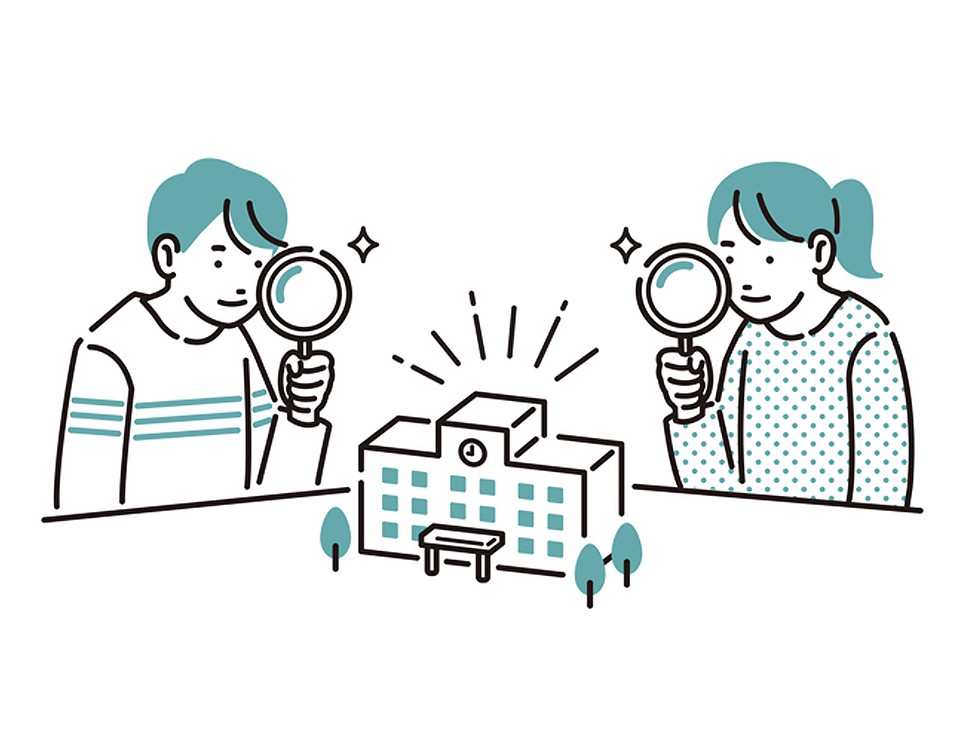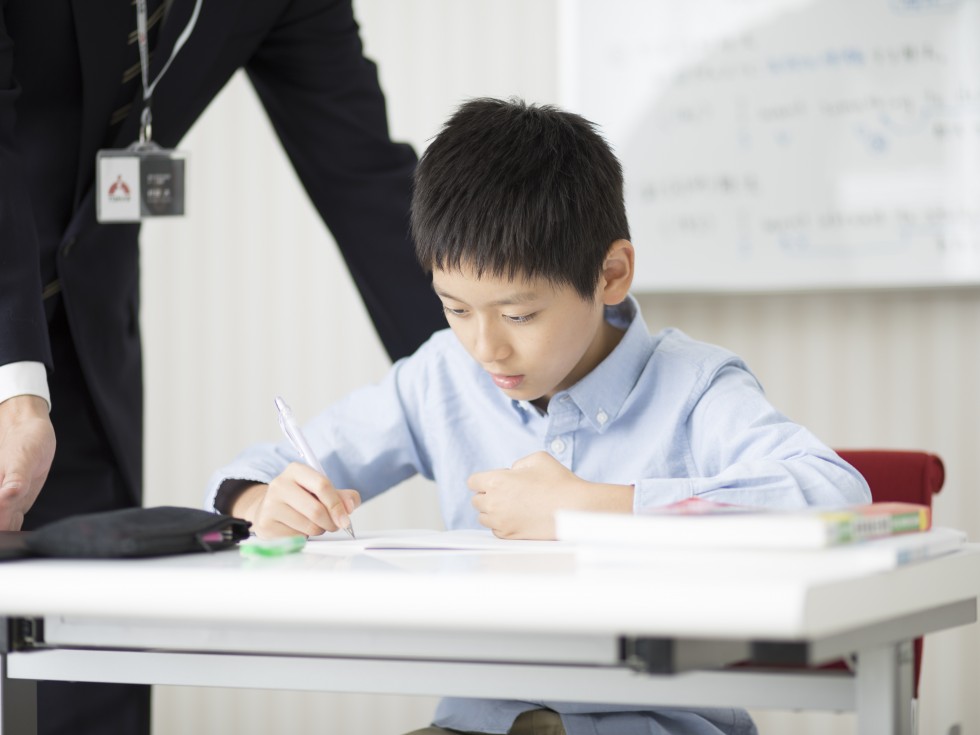
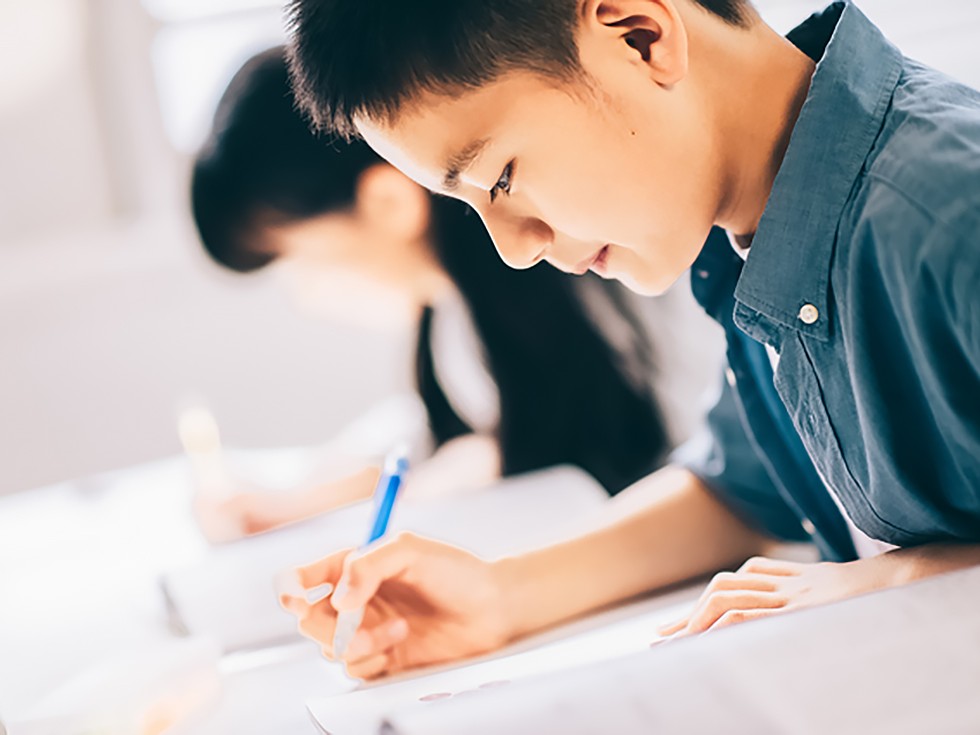
中学受験「国語」で得点するコツ! 「センス」に頼らず得点力をのばすには?
「国語は読解問題だから、読書好きでないと高得点とれないでしょ!? 」
「国語の対策は、知識問題(漢字や言葉)を覚えるくらいしかできないですよね? 」
こんな風に考えてらっしゃいませんか?
残念なことに、国語は受験勉強の中で、勉強が後回しにされがちな教科。これは対策がとりにくいと思われているからですが、実は、知識問題だけでなく、読解問題も含めて正しい対策方法があります。こちらの記事では、「中学受験において国語で問われている力」や、「国語の得点アップのためのコツ」を解説します。
正しい対策法で、国語を得意科目に変え、得点アップを狙っていきましょう。
【 目 次 】
- 「国語が苦手」と感じる人が多い理由
- 1.センスで解くというイメージ
- 2.答えも勉強法も不明瞭であるというイメージ
- 国語という教科の特徴
- 中学受験における国語の特徴
- 1.思考力が問われている
どのような問題が出るのか? - 2.読む力(読解力)が問われている
どのような問題が出るのか?
- 1.思考力が問われている
- 中学受験の国語で得点するコツとは?
- 1.知識:漢字や語句、文法はコツコツ積み重ねる
- 2.読解:文章を理解するポイント箇所に印をいれよう
- 3.選択式問題:選択肢の不適切な箇所を説明できるように
- 4.書き抜き問題:解答条件は答えを探すときのヒント
- 5.記述問題:最終地点を定め、補足する要素を入れていく
- 6.本番での時間配分を考える
- TOMASの中学受験の国語の指導
- 国語を得意教科にしたいならTOMAS
「国語が苦手」と感じる人が多い理由
国語は
- 何を勉強したら良いかわからない
- 記述問題は答えが一つではない
- 読解問題は暗記しても歯が立たず、ぶっつけ本番だから
といった理由から苦手と感じる受験生が多いようです。
加えて「国語にはセンスが必要。センスがない自分にはどうしようもない」と感じている受験生もいるのではないでしょうか。
1.センスで解くというイメージ
そもそも国語は、センスで感覚的に解くものではなく、他教科と同じように論理的に答えを導く教科で、正しい勉強方法で学習すれば得点源にできる教科です。
「国語はセンスが必要」と誤解される大きな理由は、出題されるジャンルによって、成績にバラツキがでてしまいがちなことが挙げられます。出題される文章のジャンルは、物語文、随筆、論説文、……などさまざまあります。お子さんが得意なジャンルであれば得点するけれど、苦手なジャンルだと点数が下がってしまう。このようなケースで、自分が得意なジャンルでなかった=センスがなかった、と考えてしまうのです。
国語では、センスに頼って感覚的に問題を解くのではなく、論理的な思考力、つまり文章のつながりを読み取り、論理的に答えを導く、ということが不可欠です。この論理的な思考力を身につけていけば、さまざまなジャンルの出題にも対応できるようになります。
2.答えも勉強法も不明瞭であるというイメージ
国語では、他教科に比べて、明快な勉強法やコツがないように感じるかもしれません。
また、算数などのように、解き方のプロセスが明確で、一つの正答が導かれる教科と比べて、答え方や解き方も曖昧な印象を持ちやすいかもしれません。
こういった先入観から、国語の勉強を「なんとなく」な気持ちで取り組み、終わらせていないでしょうか。こうなると、自分と相性の良い問題がでればラッキーというような運任せな状態になり、成績が安定しません。
国語においても、得点アップを狙うために押さえておくと良いポイントはありますので、この記事を読んで、身につけていきましょう。
国語という教科の特徴
国語という教科には、ある種の特殊性があり、他教科との明確な違いがあります。
その違いは、学習によって体系的に知識を積み上げたものかどうか、という点です。
具体的には、算数・社会・理科では、大部分が授業で学習して知識を積み上げていく教科なのに対し、国語では、読む/書く/話す/聞くの技能は、日常生活の中で自然に身についたものがほとんどです。つまり、文法や定義、公式といったような形式から学んだわけではなく、生活の中で自然と身についたものと言えます。
日常生活で自然と身についたものだけを武器に、手探りで中学入試の問題を解いていくのは、なかなか困難を伴うものです。入試に備えるには、体系立てた知識(例えば文法や文章の組み立てなど)を改めて学ぶ必要があり、その知識が問題を解くための重要な武器となっていきます。
他教科との共通点
国語は暗記科目ではないから、事前に対策が取れない、と考えている受験生もいますが、そうではありません。他教科と同じように、国語にも覚えていないと解けない問題もあります。代表的なものは漢字やことわざといったような知識問題です。算数で公式や解法パターンを、理科や社会でキーワードや公式、年表などを覚えるのと同様、知識問題は暗記が必要です。
また、国語で必要となる力は、算数で文章題を読む力(読解力)、理科や社会の記述問題で表現する力(表現力)など、他教科においても要となる力です。
そしてなにより、国語は他教科と同様、「センス」ではなく、論理的に考える力が必要な教科です。ポイントを押さえた勉強をして、成績アップを目指すことができます(具体的な勉強法は「中学受験の国語で得点するコツとは? 」の項目で後述します)。
中学受験における国語の特徴
国語の入試問題の構成は、主に読解問題と知識問題から出題されます。このうち、読解問題では、物語文と説明文が一つずつ出題されるのが主流です。
近年の国語の出題傾向としては、受験生の「思考力」と「読解力」を問う問題が多く、志望校の傾向に合わせて、きちんと対策することが大切になります。
ここからは「思考力」と「読解力」について解説します。
1.思考力が問われている
最近の中学入試では、文章を読んで自分の考えを記述させる、これまで学んだ知識をベースに自分の意見を述べさせる、といったような問題が増えており、ただ知識を問うだけでなく、思考力をはかるような出題となっています。
このような問題では、必ずしも一つの正答が決まっているわけではないため、入試の場で、自分の頭で考え、表現することが求められます。このような力は、毎日の積み重ねが必要で、考える(自分の意見を持つ)習慣を身につけ、またそれを表現する(書く)力を鍛えていかなければなりません。
どのような問題が出るのか?
思考力を試される出題の例としては、
- 小論文形式の出題
- 複数資料を関連づけて答えを導く問題
等があります。
近年の出題例
- 2021年のオリンピックソフトボールチーム金メダル獲得の文章を読み、「あなたがソフトボールチーム監督なら、試合にどのような方針で挑み、試合前の選手にどのように伝えるか」を記述(2022; 慶應湘南藤沢)
- ジェーン・スー「貴様いつまで女子でいるつもりだ問題」の文章を読み、参考資料1(小林敏明「故郷喪失の時代」)と参考資料2(橋本健二「階級都市 格差が街を侵食する」)との関連を問う問題(2023; 世田谷学園)
2.読む力(読解力)が問われている
近年の中学入試問題は、国語のみならず、他教科でも問題が長文化しており、問題量自体も増加傾向にあります。さらに選択式問題であっても、選択肢そのものが長文化/複雑化しており、選択肢の内容を理解/吟味する丁寧さや緻密さが求められています。
長文化した問題や選択肢に対応するためには、日頃から時間を区切って文章を読む訓練をすることが大事です。本番では、問題を最初から読み進んで、丁寧にゆっくりと解いていると、時間が足りなくなります。過去問を活用するなどして、本番にどの順番で問題を解くかの戦略を立てておくようにしましょう。
また、国語の出題であるにもかかわらず、教科横断的な内容が出題されるケースもあります。例えば、計算が必要であったり、問題に図表やグラフが示されていて、読み取った内容や分析内容を説明したりするものです。入試本番で驚かないよう、過去問で傾向を把握し十分に対策をしていきましょう。
どのような問題が出るのか?
長文化/複雑化した選択肢が出題された例は以下のようなものがあります。選択肢を諦めずに読み切る集中力を身につけていきましょう。
近年の出題例
・額賀澪「競歩王」次のア〜キはこの作品を読んだ生徒達の感想です。作品の解釈として明らかな間違いを含むものを二つ選び、記号で答えなさい。(2023; 渋谷教育学園渋谷)
ア 八千代は走ることが大好きだったのに、それを諦めるのは辛いことだろう。彼は「走る」代わりに「歩く」ことをしていたわけだけれど、でも蔵前の言葉から考えると、競歩を好きでやっている選手には勝てない。焦ると走りたい気持ちが出てしまうのかもしれない。彼が競歩選手として成長するには「歩く」こと自体を好きになる必要がありそうだ。
以下、選択肢キまで続く
中学受験の国語で得点するコツとは?
1.知識:漢字や語句、文法はコツコツ積み重ねる
知識問題は、入試で必ずといっていいほど出題されるものの、配点が低いという理由で軽視されがちです。が、きちんと覚えてさえいれば得点できるため、落とさずに確実に正解したいところです。
知識問題は、1日に覚える漢字や慣用句、ことわざの数を決め、コツコツと積み重ねていきましょう。算数の計算問題のように、毎日取り組みましょう。
特に慣用句やことわざは、例文にも目を通し、どのように活用するのかも頭に入れてしまいましょう。余力があれば「由来」も調べると、記憶に残りやすくなります。
毎日の暗記の積み重ねに加えて、前に暗記したことが定着しているか、一定期間を空けてチェックしてみましょう(例:その週に覚えたことを翌週に、今月に覚えた内容を翌月にチェック)。反復することで知識の定着が図られます。
また「敬語」は多くの受験生が苦手とする分野です。ぜひご家庭の会話の中で取り入れながら、実践し習得していきましょう。
2.読解:文章を理解するポイント箇所に印をいれよう
国語が苦手なお子さんは、文章の理解が曖昧であることが多いです。問題本文の理解が曖昧なまま問題に取り組んでも、それは論理的に解いているわけではなく、感覚的にしか解けていません。
文章の内容を理解するために、注意して読むポイントがあります。
主なものに
- 指示語の示す内容
- 場面の展開
- 人物の心情の変化
- 段落のつながり
- 要約箇所
があります。これらのポイントを発見したら、本文中に線を引く/線で囲むようにしましょう。印を入れた箇所は、筆者の主張を理解する助けになるため、本文を読み返すときは、冒頭から読み進めるのではなく、印を入れた箇所を重点的に読むと効率的です。
また、説明文の場合は、以下のような言葉に注目することも大切です。
- つまり:要約がまとめられている
- しかし:逆説/反対意見が述べられている
- である/なのだ:断定で筆者の主張が述べられている。
まずは新聞や関心のある分野の本など身近な文章を使って、上記のようなポイントに注目して読む練習を繰り返しましょう。
3.選択式問題:選択肢の不適切な箇所を説明できるように
選択肢の内容を判断するときは、文全体ではなく、要素の単位で適切かどうか判断しましょう。文章としては筋が通っていても、一部分が誤りなことがあるため、要素の単位で判断し、不適切な箇所を見落とさないようにしましょう。判断するときは、不適切箇所に線を引くなど印をつけましょう。効率的に見直しをすることができます。
また、選択肢の中に「必ず」「全く〜ない」とある場合、本文でははっきりと断定していないこともあるため、注意して読みましょう。
最近の長文化している選択式問題では、途中で集中力が切れてしまうお子さんがいます。選択肢の吟味をしないまま、選択肢に「問題文と同じ語句があったから」という理由だけで、解答しないようにしましょう。
4.書き抜き問題:解答条件は答えを探すときのヒント
-
書き抜き問題では、解答条件として例えば以下のような記載があります。
- 条件1:◯文字(以内/程度)で
- 条件2:「(〜〜)な気持ち」と続くように
書き抜きなさい。
解答条件は、本文中から答えを探す時のヒントとなります。まずは答えが書かれてありそうな段落を絞り込み、文字数を手がかりにしつつ、〜〜な気持ちと続けておかしくない表現、を探しましょう。2つの条件に合致する本文中の表現は、多くはないはずです。
5.記述問題:最終地点を定め、補足する要素を入れていく
記述問題では、書き抜き問題と異なり、ある程度表現に自由度があります。但し、何を書いても良いわけではなく、書くべき内容(要素)は決まっています。
解答を作る考え方として、まずは最終地点を定め、その後、最終地点を補足するような詳細情報(要素)を入れていくことをお勧めします。
例えば、心情の変化を問われた場合、最終地点は「嬉しい気持ちから悲しい気持ちになった」、詳細な情報として「〜〜をきっかけとして」と補足していきます。
このように記述内容を組み立てることを積み重ねていくと、模範解答と自分の解答を見比べて、どの要素が抜けているのか、どう修正すれば正答となるのかが理解しやすくなります。
また、記述問題を見直すときには、次の4点を特に注意しましょう。
- 主語と述語が一致しているか。
- 【文末の書き方】「理由を説明しなさい」→「〜〜なため/〜〜だから」
- 【文末の書き方】「気持ちを説明しなさい」→「〜〜な気持ち」
- 【文末の書き方】「どういうことか説明しなさい」→「〜〜ということ」
6.本番での時間配分を考える
どんな試験でも共通することですが、本番の時間配分を戦略的に考えることは重要です。
国語において、余裕のある時間配分にするためには、漢字や語彙などの知識問題は最初に素早く解き、読解問題に時間を残しておくことが基本です。
また、知識問題に比べて、読解問題では得点配分が高いため、読解問題に時間的余裕がないと大量失点につながります。このため、まずは知識問題から解きましょう。さらに知識問題では、覚えていない=いくら考えても正解がでてこない、ケースもあります。このような場合は、割り切ることも重要で、答えを思い出そうとする時間を読解問題に回しましょう。
苦手な国語を完全1対1の対話型個別指導で克服して筑駒中合格を果たした池田さんの合格体験マンガ
TOMASの中学受験の国語の指導
TOMASの授業やカリキュラム
中学受験を視野に入れたとき、塾選びで頭を悩ませる保護者様が多いと思います。当たり前のことですが、お子さんは個性も学力も志望校も、皆さん一人ひとり異なります。
そんなお子さん達を一堂に集めて、指導する集団指導型では、「レベルの高い授業についていけなくなり、モチベーションが下がる」「レベルの低い授業では、物足りなさを感じる」「お子さんの長所を伸ばす環境が整わず、可能性を潰してしまう」といった弊害が生じます。
個別指導塾ではこのような点が解決でき、お子さんそれぞれの学力や個性を理解しながら、学力を伸ばすよう指導します。
個別指導塾であるTOMASでは、次のステップにしたがい、志望校合格を徹底サポートします。
1:夢の志望校を決める
偏差値だけでなく、校風や教育理念、将来の進路、そして、なによりも、夢やあこがれ、わくわくする気持ちを基準に、妥協のない志望校を選びます。
2:合格逆算カリキュラムを作成
志望校に合格するには、合格に必要な力と現在の力の差を埋めていく必要があります。そのために一人ひとり個別に、百人百様の個人別カリキュラムを作成します。カリキュラムは一度作成したらそのまま、ではなく、生徒の成長に合わせて細かな軌道修正を何度も繰り返し、カリキュラムを進化させていく点がTOMASの特徴です。
3: 白板つき個室での完全1対1の個別指導
個別指導塾では、講師1人に対して生徒2〜3人の環境も多くありますが、TOMASでは「生徒1人に講師1人」という環境です。講師は専用のホワイトボードを使い、立って授業を行います。そして、「講師は発問し、生徒が答え、講師が解説をする」この繰り返しで理解度を確認していきます。双方向の対話であるため、議論を通じて思考力を磨く目的もあります。
特に国語は、個別指導に親和性が高い教科です。なぜなら、自分の考えや試験で使った解き方が正しいかどうか、講師に直接見てもらうことで学習効果が期待できます。また、発問を通じて、表現力や思考力を養うことができます。これは個別指導だからこそなせるきめ細やかな指導です。
4: 質の高い教科別の専門講師
受験塾として、各教科、各校の受験ノウハウを持つ優秀な講師陣を確保しています。優秀で多様な講師陣の中から、お子さんに最適な講師をマッチングし、成果が出ない場合は交代も可能です。
5:責任ある担任制で成績を管理
学習効果を上げるためには、指導の質だけでなく、生徒を取り巻く関係者が相互に信頼関係を築くことが重要です。TOMASでは、生徒、保護者、講師、担任の4者が一体となってコミュニケーションをとることを何よりも大切にしています。面談のほか、日常的なコミュニケーションとして電話によるホットラインを設けており、目の前のハードルを一つひとつ乗り越えていきます。
さらに、個別指導塾では入試指導やデータ分析が弱いのでは? というご不安もよく耳にしますが、TOMASでは、変化する受験ノウハウに対応できる講師が揃っていることに加え、例年最新分析報告会を開催しており、データ分析や入試情報についても情報提供し、ご不安を解消します。
TOMAS生の合格実績
今春の2023年度入試では、次のとおりTOMAS生が合格を勝ち得ました。入試国語が難しいといわれる筑駒2名、開成14名、麻布15名、桜蔭4名、雙葉4名、渋谷教育学園幕張29名、渋谷教育学園渋谷10名、聖光学院12名、フェリス女学院3名をはじめ、女子学院10名、駒場東邦22名、栄光学園12名、豊島岡女子学園10名、早稲田15名、慶應義塾中等部14名など、いわゆる難関中学への合格実績を伸ばしています。
難関校を中心に、国語ではかなりの長文が出題されており、一筋縄ではいかない問題も多くあります。TOMASでは完全1対1の指導を通して、読解問題で間違えた理由を明らかにしたり、どう考えれば良かったかを検証したりするなかで、読解力の底上げを図っています。
国語を得意教科にしたいならTOMAS
中学受験では、算数を心配な教科として挙げる方が多いですが、実は国語も配点の高い教科です。配点が高いのはわかっているけれど、国語の解法のコツを知らず、感覚的に解くことに慣れていませんか? また、それが原因で学力が伸び悩んではいませんか?
これまで解説してきたとおり、国語では思考力と読解力の向上がキモになります。完全個別指導塾であるTOMASでは、発問を中心とした授業展開をしており、受験生一人ひとりの理解度に合わせ、効率的に思考力と読解力を伸ばしていきます。我々TOMASと一緒に、苦手を得意に変えていきましょう!
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。


![[体験談]わが子がボーディングスクールへ合格するまで](/schola/common/images/uploads/2020/09/3684775_m-980x735.jpg)