
TOMAS主催入試イベントレポート
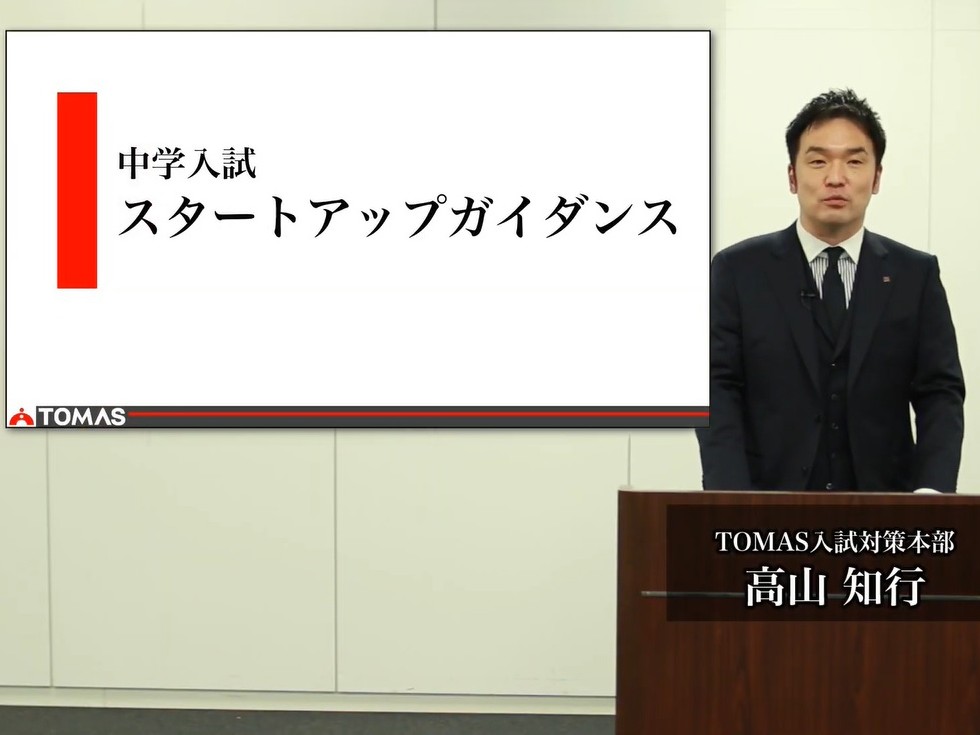
2021年度 中学入試
スタートアップガイダンス
※2020年11月15日公開の動画の採録です。
2020年11月15日にオンライン配信形式で開催された中学入試スタートアップガイダンス。第1部では教育ジャーナリスト、おおたとしまさ氏へのインタビューを通して、中学受験を検討している方、これから受験に向けて準備を始めようとしている方のために、”親はどのように関わっていけばいいのか”などをお伝えしました。第2部ではTOMAS入試対策本部・高山知行より「中学受験で今、何が問われているのか ~〇年生までにやっておきたいこと~」をお伝えしました。本記事では、第2部「中学受験で今、何が問われているのか ~〇年生までにやっておきたいこと~」の内容をお届けします。
中学受験を検討するご家庭が知っておきたいこと
これから中学受験を考えていこうというご家庭、ちょうど受験勉強をスタートしたばかりというご家庭、すでに受験勉強が軌道に乗っているというご家庭など、さまざまな状況があると思います。中学入試で何が問われているか、どんなところに注意して、どんな準備を進めればよいかなどについて、お伝えします。
中学受験はじめの一歩
最初に準備すべきなのは、お子様の個性に合わせた志望校を決めること、志望校合格のための計画を立てることです。
1. 学校を知る
2. 志望校を決める
3. 合格までの計画を立てる
という3ステップで準備を進めましょう。
1. 学校を知る
首都圏にはさまざまな特色を持つ魅力的な学校が多く存在します。学校を知ることはお子様の未来を考えることです。どの学校がわが子に合うのかを考える前にご家庭の方針を整理しましょう。
「男子校? 女子校? 共学校? 大学附属校?」
「校風・理念・教育方針・進学実績・規模・場所・部活についてのこだわりは?」
などさまざまな観点がありますが、ご家庭の方針として、何を優先するのかを整理しておくことが大切です。
もちろん、一番大事なことは受験する本人の気持ちです。
学校のホームページ、オンライン説明会、学校紹介動画などを活用し、親子で一緒に学校について調べましょう。
2. 志望校を決める
ポイントは2つあります。
・志望校は早い段階で決めておくこと
・本当に行きたい学校を第1志望に決めること
「今の成績だと無理」「こんな学校名を言うのは恥ずかしい」などを気にする必要はありません。入試までに時間があればあるほどしっかり準備ができます。本当に行きたい夢の志望校に向けた合格逆算カリキュラムを作り、きちんと実行できれば、手が届かない学校はありません。
3. 合格までの計画を立てる
志望校が決まれば、いつまでに・何を・どのくらいやればよいのかがわかり、具体的な計画を立てられます。志望校を決めないままだと、カリキュラムや方向性があいまいになるおそれがあります。早期に志望校を決めて、計画を立てることで、他の受験生より有利に受験勉強を進めることができます。
また、同じ学校の受験生でも、いつまでに単元学習を終えて、いつ過去問対策に入るかなど、一人ひとりの進み方は違います。そのため、お子様一人ひとりに合わせたカリキュラムの作成が必要です。
入試形式の多様化
入試と聞いてまず思い浮かぶのは国語・算数・理科・社会の4科目入試でしょう。現在も4科目入試が主流ですが、英語入試・適性検査型入試・科目特化型入試など選択肢が増えています。
英語入試は5年前に比べ、4倍以上の学校に導入されており、今後も広がる傾向にあります。出題形式やレベルは学校によってさまざまです。検定試験の級やスコアといった形で一定のガイドラインを示している学校もあります。
適性検査型入試については聞きなれない方もいるかもしれません。たとえば、光塩女子学院中の2020年度入試だと、150枚の紙を使って、3つの部品を作り、できるだけ高い塔を作るという問題が出題されました。紙の枚数や、部品の形、支えられる重さの限界など、読みとるべき条件が複数あって、条件をもとに理科的・算数的な思考が必要とされます。
このように、教科の線引きが難しいのが適性検査型入試の特徴です。
1科目入試は体力的に負担が少ないというメリットから、午後入試として実施されています。問題の難易度や合格ラインは通常の4科目より高いので相当の準備が必要です。ここ数年で新しく設定された午後入試に多くの受験生がチャレンジしている状況からも、注目されている入試方法です。
最近の入試問題の特徴
最近の入試問題の特徴として、次の3つがあげられます。
- 問題の長文化
- 資料の複雑化
- 記述式解答の増加
1つ目は問題の長文化です。ここ数年、算数の問題文が10行を超えるような入試問題が見受けられます。問題の条件やヒントを読み込まないと、問題を解くスタート位置にすらつけません。
また、対話形式で対話の中に問題が組み込まれるという形式の入試問題も見られます。このような問題では話の流れや展開を把握していくことが必要です。
2つ目は資料の複雑化です。複数のグラフ・表・数値から必要な情報を読む力が問われています。
3つ目は記述式解答の増加です。自分の考えをいかに相手にわかりやすく伝えられるかが問われています。
では実際に入試問題を見てみましょう
2019年栄光学園の入試問題、算数の大問2です。
立体の展開図について考える問題です。立体図形の問題は難関校など特定の学校だけでなく、幅広く出題されるようになってきています。
設問1では、正四面体の見取り図と展開図が書かれており、正四面体のどの辺を切れば、問題文にあげられた展開図になるかを図示させるという問題でした。
これまで、立体の切断後の体積や表面積を求めさせる問題は出題がありましたが、見取り図から展開図を考えさせる問題というのはあまり出題が多くありません。このように、取り組んだことがあるようで、あまり経験値を積んでいないタイプの問題が近年の難関校では見受けられます。例で示されたヒントを元に決められた条件で問題を考えていく必要があります。
さらに大問2設問4では
正五角形12面で囲まれた立体の展開図を考えます。
この問題は設問の誘導に乗りながら考えを発展させていく問題です。
単純に面積を求めたり長さを求めたりといった問題ではなく、公式や決められたパターンでは正解にたどり着けません。
ちなみに前半部分は小学校低学年からでも取り組める内容なので実際に作って挑戦してみると立体感覚が磨かれます
これと同じような問題が2007年の桜蔭中でも出題されました。
次は国語の問題をご紹介します。2019年雙葉中で出題されました。
2つの文章を読んで答える意見陳述型の問題です。
2つの文章では「頭のいい人」と「頭の悪い人」が対比されています。
これを読んで、自分自身がどちらのタイプに属するのかを考え、理由とともに答えさせる問題です。明確な正解はなく、自分を客観的に分析し制限時間の中で記述することが要求されています。
解き方を覚えて繰り返し解いていけばよいという考えでは、紹介した2つの入試問題には通用しません。このような新傾向の入試問題は受験生に、知識だけでなく、思考力・表現力・判断力を求めています。知識の量というものはこれまでどおり必要ですが、持っている知識をどう生かしていくのかが重視されています。解決すべき課題を発見し明確にすること、課題解決に向けて論理的に取り組むことが、今の入試問題で求められています。
成績を伸ばすためにもっとも重要な3つの基礎力
最終的には受験生はこのような問題に取り組むことになります。
入試までにまだ十分に時間があるお子さんに向けて、今から準備できることが3点あります。
成績が伸びる生徒とそうでない生徒の差はやはり基礎の部分です。
1つ目が「読む」、2つ目が「書く」、3つ目が「計算する」です。
こういった本当にごくごく当たり前の部分が差になります。
目指していきたいのはこの「読む」「書く」「計算する」の処理を正確に早くできることです。開成・桜蔭といった最難関校に合格した受験生はこういった部分が圧倒的に速く正確に処理できるからです。
この3つは今から誰にでも鍛えることができます。
スタートの位置は個人で差があるかもしれませんが、決して才能だけで決まってしまうものではありません。
1 「読む」力を鍛える
何を読んでほしいかというと、教科書・参考書、本・新聞、グラフ・図、そして問題文です。最近では教科書を正しく読まない生徒が多いことが気になります。学校の先生も教科書をあまり使っていないようです。正しく読むことができるようになれば、物事を正確に把握することにつながります
2 「書く」力を鍛える
何を書いてほしいかというと、文章、図・グラフ、答案、自分の意見です。文章や図・グラフは、ノートに自分で書くということが大切です。たとえば、ふだんの計算練習や漢字練習などで字を雑に書いたりノートに自分で図をかかずにテキストの図に書き込んだりしていませんか。図形で言えば正方形を正しくかけているか。高学年であれば立方体をかけているか。意外とこれができていません。
3 「計算する」力を鍛える
算数が苦手という受験生の大半は小3生レベルの計算ぐらいから計算力不足が見受けられます。いくら問題の解き方がわかっていても計算の答えが合わなければ正解になりません。計算は正しくミスなく素早く。さらに、暗算できるように訓練します。何度も反復練習して鍛えているかどうかで計算力は大きく変わります。今まで5分かかっていたことが1分でできるようになっただけでも大きな変化につながります。
入試問題は基礎だけではもちろん解けません。しかし、入試で求められている力をこれから身につけていくために、まず基礎が重要です。できれば低学年のうちに基礎を身につけておきましょう。遅くても本格的に問題演習へ入る小5生の夏前までには「読む」「書く」「計算する」といったことで成績の足を引っ張られるような状況は避けましょう。
ひょっとすると、今までおろそかにしていたなぁと思い当たる点があるのではないでしょうか。もしそうだとしても大丈夫。今から改善できます。あらためて普段の取り組みを見直してみてください。
「基礎」と「応用」のバランスが重要
「読む」「書く」「計算する」の次の段階としては、問題演習です。
学力を効果的に伸ばしていくためには、基礎と応用にバランスよく取り組むことが必要です。伸び悩んでいる受験生は、基礎と応用のバランスがくずれています。もっと基礎的な部分の理解を深めることが優先の課題であるのに、難しい応用問題ばかりに取り組んでいた受験生や、基礎の部分に時間や量をかけすぎていて必要な量の応用問題に取り組めていなかった受験生など、一人ひとりを見ていくと、成績が伸びない理由がさまざまなところに存在します。
TOMASではこういった部分も見逃さず学習アドバイスを行っています。
必ずしも難しいことをたくさんやることが学力向上につながるというわけではありません。
基礎の上に適正な量の応用を取り入れていけば焦らずとも成績はついていきます。
TOMASからのメッセージ
お子さん1人ひとりに夢の志望校があると思います。私たちTOMASは、志望校合格だけではなくお子様の進学後の成長イメージまで視野に入れ、日々の指導に取り組んでいます。
今年はコロナ禍ということもありライフスタイルも大きく変化することになりました。
そのような環境の中、今年の受験生はできることに取り組み、志望校の合格に向けてがんばっています。
数年後、今度はお子さんが中学受験の主役になるときがやってきます。夢の第一志望校への合格に向けて一緒に進んでいきましょう。
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。








