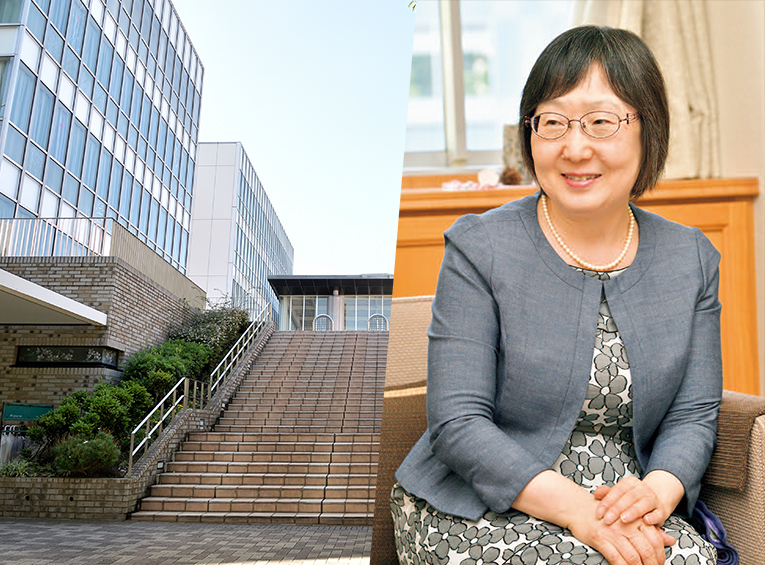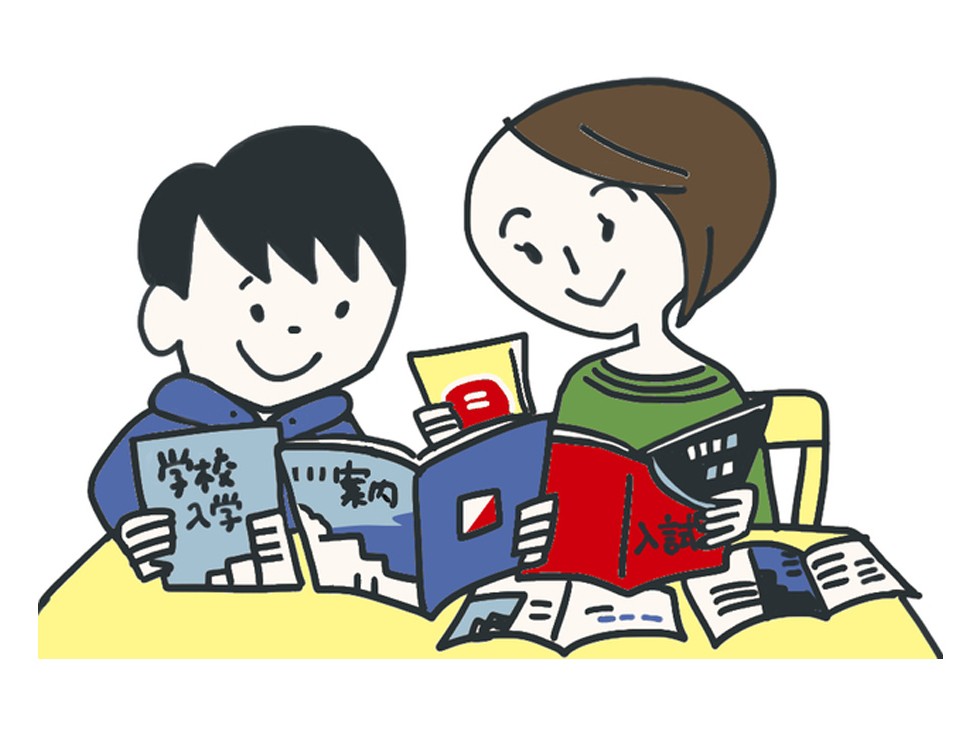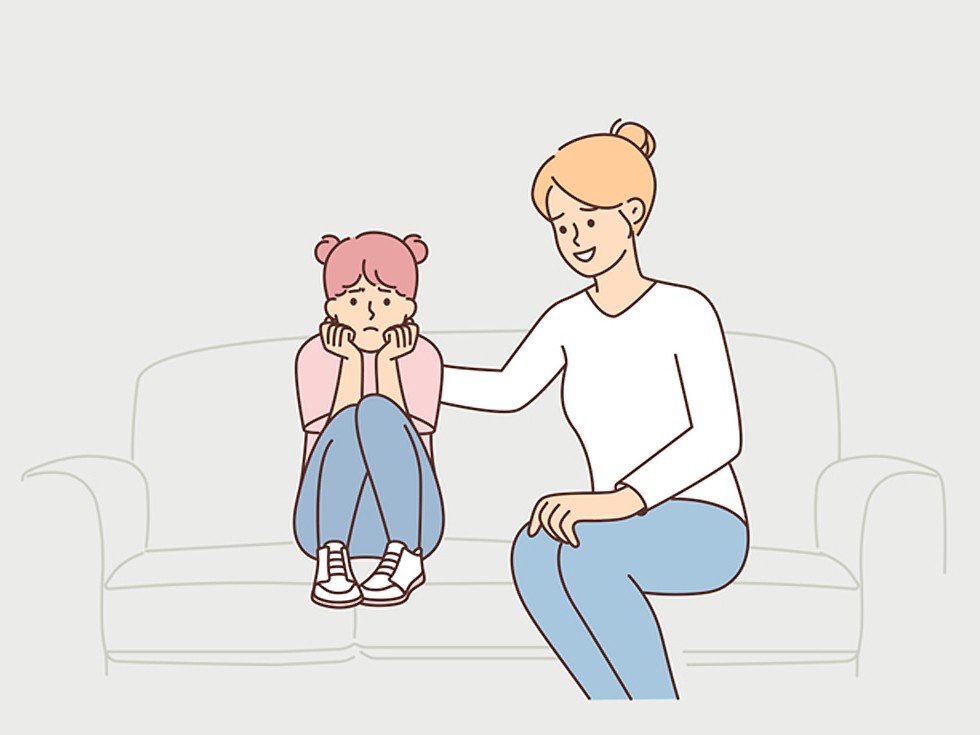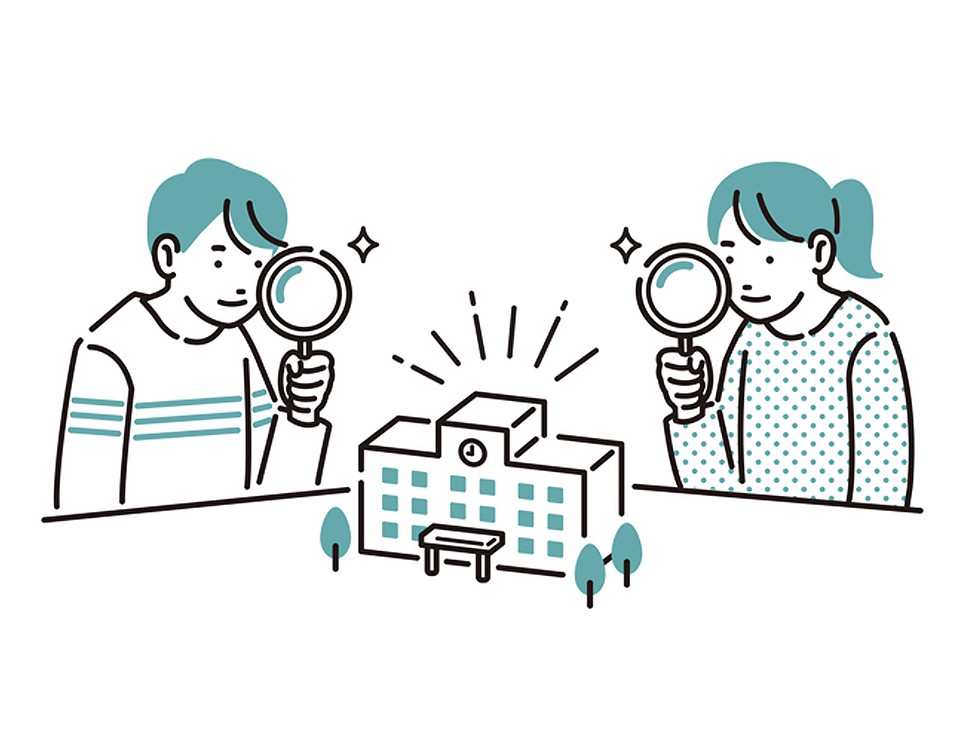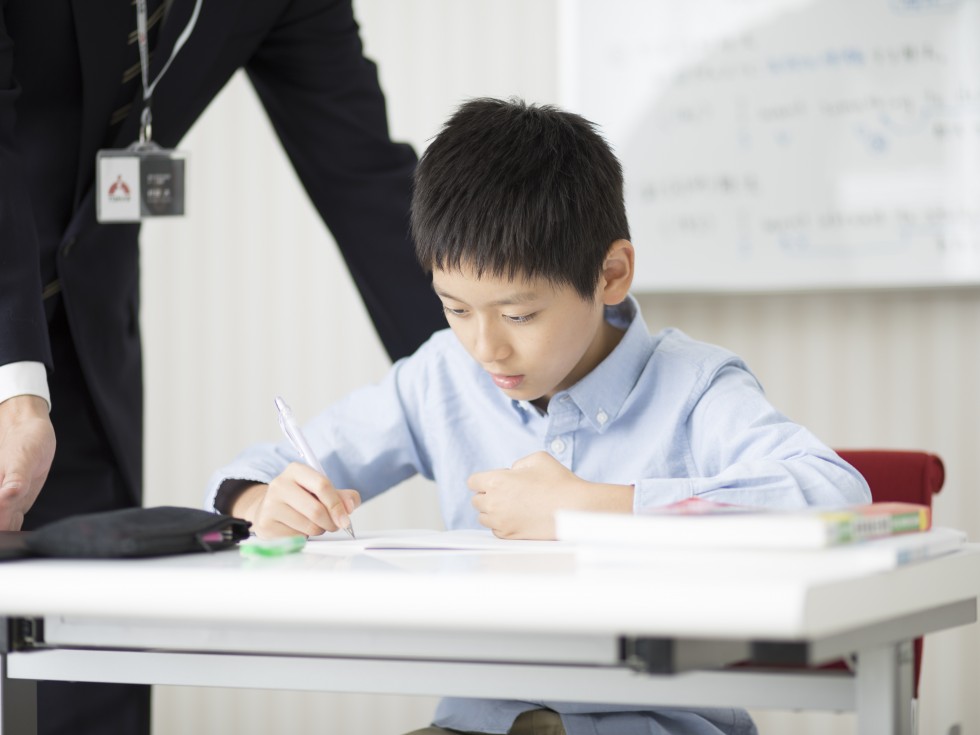
最難関校合格を勝ち取る 中学受験の「理科」勉強法
Science Study Tips for Top Junior High School Entrance Exams
最難関校受験生であれば、多くの子どもが受験学年までに理科用語や暗記事項はひと通り覚えています。しかし、そういう受験生であっても、「記憶したことを活用して問題を解くこと」「これまで見たことがない科学的事象を考察すること」「長い問題文や複雑な図表から、設問の要求に応じて必要な情報を読み取ること」などは苦手だというケースがよく見られます。一方、最難関校の入試問題は、受験生のそのような弱点を突き、試験という現場での対応力を測ります。合格を勝ち取るためには、このような厳しい出題でも手堅く得点できなければなりません。
以下では、最難関校入試の理科で1点でも多くもぎ取るための実践的な勉強法をご紹介いたします。
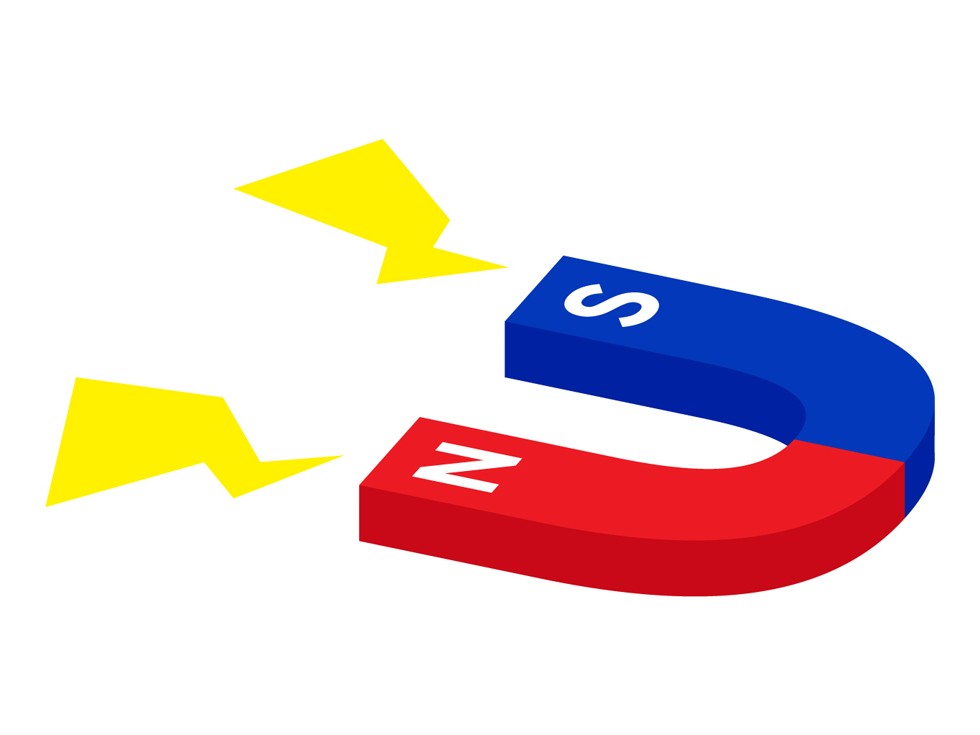
【中学受験の「理科」勉強法①】入試問題の「出題意図」と「学習環境」
powered by Spec. TOMAS
以下では、受験対策の大前提として、最難関校の入試問題が受験生に何を求めているのかという点、および、理科を学ぶためにはどのような環境が必要かという点についてお話しいたします。
中学入試の現状
「知識の先にあるもの」が求められる
近年の最難関校入試問題では、「知識の活用力」が試されます。「知識の活用力」とは、「既知の知識を使い、新しい科学的事象を論理的に説明する力」のことです。もちろん、知識自体を問うという従来型の出題もまだ多いものの、「知識の先にあるもの」まで求める傾向は確実に強まっています。
その最たる例が、麻布中の入試問題です。麻布中は、単元的な内容から大きく離れた融合問題を好む傾向にあります。麻布中の入試問題では、受験生がこれまで見たことも聞いたこともない初見資料が出てきます。受験生には、50分という短い試験時間内で高度な初見資料を処理することが求められます。
もっとも、このような麻布中の出題傾向は最難関校の入試問題の中でも際立って個性的な事例であり、入試問題全般の傾向を代表するものではありません。しかし、麻布中の出題に見られるように、近年の最難関校の中学入試が膨大な問題文読解量と解答記述量を要求していることはたしかです。
科学的事象の原理・法則を踏まえ、論理的に説明することが求められる
では、以上のような傾向に対応するためには、どのように勉強していくべきでしょうか。
受験理科の勉強において重要なのは、知識を丸暗記することではなく、科学的事象の原理・法則を理解することです。最難関校の入試では、さまざまな科学的事象を論理的に説明する力が受験生に求められるからです。
たとえば、「熱気球」を例にとりましょう。熱気球が上昇する理由は、「気球内の空気が温められるから」です。しかし、これだけでは、経験的に実感できる現象を述べているにすぎません。
入試問題を解くためには、この段階からさらに一歩踏み込む必要があります。すなわち、原理・法則に注目して、熱気球が上昇する理由を論理的に説明できなければならないのです。この科学的事象が起きる理由を論理的に説明するとすれば、たとえば「温められた気球内の空気の体積が膨張して密度の小さくなった空気が上昇し、熱気球全体が持ち上がるから」などとなります。
特定の科学的事象に関する原理・法則の理解は、ほかの事象にも応用可能です。たとえば、上で取り上げた「物の温まり方」の考え方は、「対流」という単元の知識につながります。あるいは、「浮力」という単元や、地学分野の「気象」という単元における「風の吹き方」という項目も、「物の温まり方」の考え方から理解が深まります。最難関校の入試問題が解けるかどうかは、ひとえに、このような根源的理解の有無にかかっているのです。
理科を学ぶための環境
「科学的体験」の機会を用意する
子どもが理科への興味を抱けるかどうかは、子どもがたくさんの科学的事象に触れることができる環境を、大人たちがどこまで用意できるかにかかっています。子どもには、科学的事象に触れる体験、つまり「科学的体験」を、低学年のうちからたくさん積ませましょう。
おススメできる「科学的体験」は、「磁石で遊んでみる」ことです。
子どもたちが理科を学習するうえで高い壁となりやすいのは、「目に見えない現象」を理解することです。磁石において「目に見えない現象」に該当するのは「磁力」です。「磁力」は目に見えないため、多くの子どもが、「N極とS極は引き合う」「N極とN極、S極とS極は反発し合う」のように、磁力がはたらいた結果だけを丸暗記してしまいます。しかし、たとえば、磁石の近くに置かれたクリップが磁石に引っ張られていく様子を実際に観察すれば、「磁力」というものが作用していること、さらには「磁界」というものが存在していることが、たとえ目では観察できなくても、だんだん感覚としてつかめていくのです。
このような「科学的体験」には、机上の学習としてではなく、遊びの一環として、楽しみながら取り組んでいきましょう。
重要なのは、出された答えではなく、答えを考えた過程
大人は、知識をたくさんもっている子どもをほめる傾向にあります。もちろん、知識が多いこと自体はとても望ましいことです。しかし、物事をたくさん覚えているという点だけをほめてしまうと、子どもを、「勉強では、答えさえ覚えてしまえばよい」という誤った認識に導きかません。理科の学力の礎は、答えそのものではなく、「なぜその答えが出てくるのだろう」という疑問をもつことと、その疑問を解決するためにいろいろと試してみることにあります。試行錯誤の体験とひもづいた答えこそ、ずっと忘れない生きた知識として定着していくのです。
「科学的体験」は、科学館や博物館へ行くこと、あるいは理科室で実験を行うことのように大がかりなイベントである必要はありません。先ほど述べた「磁石を使った実験・観察」のように、身近な出来事で十分です。大人のみなさんは、子どもに答えを教え込むことではなく、子どもたちが抱く「なぜこうなるのだろう」という素朴な疑問を見逃さないこと、子どもたちがその疑問を体験から解決していくことに配慮してください。子どもの成長をうながすのは、周囲の大人による温かい視線なのです。
まとめ
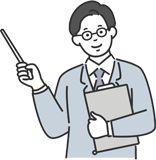
最難関校の入試では、断片的な知識ではなく、科学的現象に関する論理的な思考力が問われます。そのような力は、机上の学習よりもむしろ、日常生活で科学的現象に触れた体験によって深く養われていきます。お子さんにはぜひ、低学年のうちからさまざまな経験を積ませてください。
■夢の志望校合格に導く 低学年からの難関校対策個別指導塾[スペックTOMAS]
https://www.tomas.co.jp/spec/
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。


![[体験談]わが子がボーディングスクールへ合格するまで](/schola/common/images/uploads/2020/09/3684775_m-980x735.jpg)