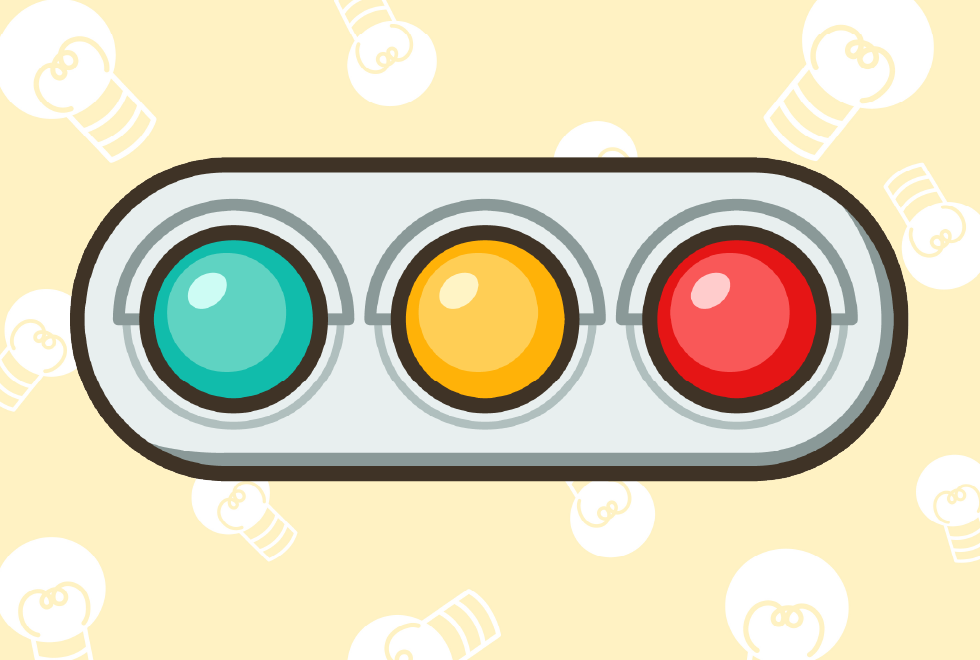公開模試が、“後悔”模試になった場合の併願校の決め方を考える
師走間近となり、6年生は過去問演習で一喜一憂している頃かとお察しいたします。
もし、公開模試の偏差値を見て、“後悔”模試となったとしたら、そこは華麗にスルー。あまり考え過ぎないことが大切です。
秋から晩秋にかけての時期というのは成績が上がりづらいことが多いので、親子の焦りは相当なものになってしまうのは「あるある」なことです。
なぜならば、本番を見据えて頑張り出す子たちが増えてくるので、いわば、全員が本気を出して頑張っている状態。それゆえ、相対的なものである偏差値を上げるのは、なかなかに大変というのは事実としてあるのですが、だからと言って、あきらめてしまう必要は全くないわけです。
第1志望校はそのままに、日々のタスクを淡々と
6年生は9月から12月に月1回で、合計4回の公開模試を受ける子が多数派です。その際の個人の偏差値の上下の差は平均7〜8といわれています。塾の先生は誤差を多めに見積もって併願校の偏差値を上下10で考えましょうとおっしゃることが多いです。
つまり、平均偏差値が50であれば、実際の受験校を偏差値40〜60の間で考えましょうということなのですが、これは、当日のコンディション、出題傾向などで簡単に上がったり、下がったりするのが偏差値というものだからです。
もちろん熱望校であれば、差が10以上であってもひるむことなく受けてよいですし、塾側も併願校さえしっかりしているならば、第1志望校受験を積極的に後押ししてくれると思います。
なぜならば、受験はどんなに早くても1月がスタートです(帰国入試を除く)。東京・神奈川受験ですと、最終模試からは2カ月も時間がある。受験本番中の日々の中であっても学力が急上昇する子どもは稀ではありません。
実際に塾の先生方にうかがうと、12月の最終模試が終了してから本番までの間に実力がつく子は沢山いるそうで、模試での偏差値はあくまで目安。やはり、受験は最後の最後まで結果がわからないものですし、「この学校で学びたい!」という強い思いが合格を引き寄せる原動力であるのは間違いないです。
第1志望校は大切です。そこを目指して頑張っているといっても過言ではないですし、どんな学校であろうと、受験しなければ合格はありません。
そういう意味でも“後悔”模試に必要以上に引っ張られることなく、今、やっているであろう日々のタスクを淡々とやり続けるほうが合格に近付きます。
原点=わが家の教育方針に立ち戻って併願校を再吟味
このように、子どもには今までどおり第1志望校を目指して頑張ってもらえばよいのですが、親の任務は、併願校をきちんと考えることです。
第1志望校に行ける子は3〜5人に1人と言われています。大変厳しい世界であるのも事実です。
それゆえ、最終的に併願校を決めるこの時期に、今一度、原点に立ち戻ってください。
「わが子をどんな環境で育てたいのか?」
中学受験を選んだということは、様々な理由があってのことでしょうが、わが子に良い環境を与えてあげたいという気持ちが大きくあるかと思います。
良い環境というのは人によって違いますが、12歳から18歳までという、人生で最も多感な時期に差し掛かるわが子に居心地の良い場所を選びたいというのは、まさに親心。
現実問題としては入学してみないとわからないことも多く、ある意味「賭け」ではあるのですが、受験候補校がわが子の長所を伸ばしてくれるであろう学校かどうかを確認するのは、思う以上に大事なことなのです。
一般論ではありますが、1月校、第1志望校、併願校、押さえ校、さらに午後受験校なども考えながら、8校ほどに願書を出すのが最近の傾向です。
まさにパズルのように組み合わせていく作業になりがちですし、願書提出や入学金の支払いなどの事務手続きにも神経を使いますので、親にとっては重責になりますが、その前にしっかりとわが家の主たる教育方針を確認して、それが各受験校の教育理念と合致しているかのすり合わせは必須です。
大抵のご家庭では第1志望校は揺るぎがないのですが、志望順位が下がるにつれて親の情報収集にかける手間は軽くなりがちです。
例年、本番の受験会場で行われた学校説明会で、初めてその学校の校長先生の話を聞いたという方もおられますし、受験本番時に行っただけの学校に入学することになって悩み出す人は後を絶ちません。
実際に通うのはお子さんなので、わが子が気に入らなければ、併願校であればあるほど、合格しても進学への期待値は下がってしまいます。
そういうことがないように、少なくとも受験本番前までの段階で、できればお子さんと一緒に学校見学に行くことをお勧めしています(「アポイントさえ取ってくれたら校内見学を許可する」という学校も多いですし、もしNGであるならば、在校生の通学風景を見るだけでも雰囲気は掴めます)。
さらに、もっと大事なことは親の態度です。
もちろん、「ここは第2志望校で、ここは押さえ校」という受験校の順位付けがあるのは当然ですし、目指す第1志望校に合格するために応援していくという姿勢は必要です。
また、本番期間中はタイトなスケジュールになりますので、慌てないためにも志望順位も含めたシミュレーションは必須です。しかし、それは心の中だけです。子どもに向かっては受験校をランク付けすることなく、こう伝えてあげてください。
「どこもいい学校。どこに行くにしても、きっと楽しいよ」と。
こう思えたならば親も安心できるので、逆に親子で自信を持って第1志望校にも立ち向かえるというものです。
さあ、時間はまだまだたっぷりあります。“後悔”模試に引っ張られている場合ではないです。
「家族で頑張ってきて楽しかったね!」と思えるように、出来ることを出来る範囲でやっていきましょう!
TOMAS全校で無料受験相談を承っています
「志望校に向けて何から始めてよいかわからない」「足を引っ張っている科目がある」「塾・予備校に通っているが成果が出ない」など、学習面でお困りのことはありませんか? 進学個別指導TOMASならではの視点で、つまずきの原因を分析し、課題を解決する具体策を提案します。まずはお気軽にご相談ください。
鳥居先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。