

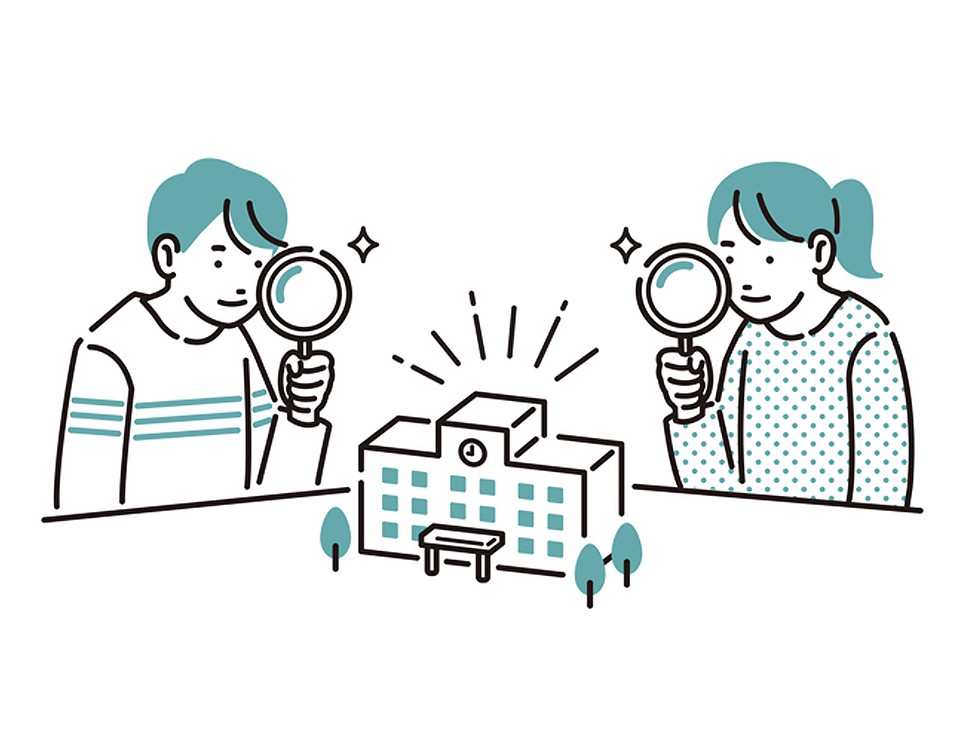
中高一貫校の大学合格実績を考える
毎年、春は、東京大学をはじめとする難関大学の高校別合格者数が発表されるシーズンです。今年も東京大学の合格者数のトップ10のうち8校を私立高校が占めたことからもわかるように、今現在は難関大学への進学には中高一貫校のほうに軍配が上がっています。
このことも大いに影響して、中学受験ブームが続いているのですが、実際、1人でも「東大合格者」を出した中高一貫校は人気になりやすく、翌年の中学入試の倍率が上がる傾向があります。
中学受験を目指すご家庭に話をうかがうと「東大に合格させるだけの教育を受けられる学校」というイメージを持たれるようで、「出口は高ければ高いほど良い」とおっしゃる保護者も珍しくはありません。
この考え方自体は否定しませんし、「大学受験は団体戦」という側面も確かにあるのが現実です。
つまり、「朱に交われば赤くなる」ではありませんが、高みを目指す集団の中で暮らしていると、そのことが自然になり、大学受験に関しても仲間同士で切磋琢磨し合えるので、結果として気付くと自分も難関大学合格を目指していたというケースはとても多いのです。
ゆえに、塾や学校関係者だけではなく保護者の皆さんも、メディアが発表する高校別・難関大学合格者ランキングに注目している方は少なくないという実状があります。
このようなことから、各ご家庭では各中高一貫校が発表する「進学先」あるいは「合格大学」をホームページ上で比較し、志望校選択の参考にされていると思いますが、ここでは発表数字のより具体的な読み取り方を考えてみたいと思います。
TOMASの中学受験指導について詳しく知りたい!
資料請求はこちらから
過去数年間の推移をみる
学校によっては過去3年、あるいは5年の累計数字だけを載せているケースがあります。学校の自信のなさの表れで、そのような発表の仕方をするのだと思うのですが、これだけだと、その学校の今現在の実績を把握することが困難になります。
学校の良さは大学合格者数の多さだけではありませんので、累計数字しかないからといって、その学校の教育の是非を語ることはできませんが、「出口」が気になるご家庭は少なくとも、過去数年間の推移がわかるような発表をしている学校のほうが、よりフィットすると考えています。
その際に現役か浪人かの数字も参考になるかと思います。浪人してでも自分の第一志望を曲げない生徒が多い、あるいはほとんどが現役で合格しているなどの「校風」が表から読み取れることもあります。
国公立大学志望者が多いとか、私立大学が圧倒的に多いなどの傾向も明白になるので、将来設計への判断材料にもなるでしょう。
海外大学を視野に入れているご家庭では、卒業生の海外大学への合格実績は非常に役立つので、注目してみてください。
また、学年によって進学実績に違いが出るのは当然のことなのですが、どういう層の大学(例えば「MARCH層」が多いなど)を目指している学校なのかの傾向は掴めるので、志望校選択の参考になります。
意外と大切なのが「合格者数なのか、進学者数なのか」という発表方法です。
合格者だけの場合、1人の子が複数の大学に合格しているケースであっても、数字上ではカウントしていることも考えられるため、進学者で発表している学校のほうが現在の立ち位置は明確です。
大学名と同時に学部・学科をみる
学校によっては進学者の学部・学科を発表しているケースがあります。
今は、同じ大学でも学部・学科によって難易度はかなり違いますし、保護者世代の偏差値表とは大きく変わっている学部・学科も多いです。
「資格系に力を入れている」「医学部に強い」なども理解できるので、卒業生がどういう学部・学科を選択しているのかも注目しましょう。
また、その学年の文系・理系者数を公表している学校も多いので、理系に力を入れている学校なのだなとか、どちらかに偏ることなくバランス良く教育されているのだなということも把握することができます。
どこがボリュームゾーンか、最下位はどこに行ったか
人は不思議なもので、ついつい「東大」をはじめとした難関大学への数字に気を取られがちになるのですが、実は気にするべきは最上位層の進学先ではありません。合格実績の表から読み取るべきはむしろ「ボリュームゾーン」です。
その高校から合格している数が一番多いのはどの大学なのか、という視点で見ることは大切です。
中高一貫校の生徒は歴代の実績を把握しているため、学年の何番にいれば、この大学は確実という肌感覚を持つケースは多いのですが、表からうかがい知ることも可能です。
学年の真ん中あたりの成績を取れていれば、この層の大学に行けるのだなという目安になるので、トップ層よりもむしろボリュームゾーンを把握することをお勧めします。
さらに、可能であれば学校説明会などを利用して、「最下位層の子の進学先」を聞いてみてください。意外と先生方は正直に伝えてくれます。「評定平均がいくつで〇〇大学合格」などと教えてくれるので、学校選びの際の一つの目安にすることも可能です。
関連記事「学校説明会で何を見るかを考える」を読む
合格者の入試方法を把握する
実は一番、重要視すべきことは入試方法の把握と言えるかもしれません。
ご承知のように、今までの大学入試は「一般選抜」と呼ばれるペーパーテストの入学試験が主要な入試制度でした。
しかし、今や主流派は「総合型選抜」または「学校推薦型選抜」による入試です。今現在の数字で言えば、私立大学では約6割、国公立大学でも2~3割の学生が「総合型選抜」「学校推薦型選抜」での入学者となっています。
総合型選抜は昔のAO入試と捉えるとわかりやすいかと思いますが、従来の一般入試とは全く異なる入試方法であるのは確かで、今後もこの入試方法は増え続けると見られています。
総合型選抜は「大学の求めている学生像」に合っているか否か、つまり、学ぶ目標や意志が明確かどうかを評価される入試制度なので、生徒の適正などを考慮しつつ、学力も担保した上での幅広い指導力が必要な入試とも言えるのです。
もちろん、一番は生徒のやる気次第にはなりますが、学校によっては総合型選抜入試に力を入れて指導している場合もあります。
未来は誰にもわかりませんが、今後も、主流派になる入試制度ということは間違いないでしょう。高偏差値帯の中高一貫校では今も一般選抜の率が高いのですが、ご家庭が目指す学校が大学受験において、どの入試形態を重視しているのかを把握しておくのは無駄ではありません。
以上、簡単ではありますが、大学合格実績の表の捉え方を解説してみました。
先述したように、中高一貫校は意外とオープンです。学校説明会などの個別ブースでは可能な限り、どんな質問にも懇切丁寧に答えてくれる傾向があるので、気になることがあれば、「ホームページではこう書いてあったのですが、これはどうなのでしょう?」などと、いろいろと質問して、疑問を解決していくとその学校のことがより深く理解できると思います。
まずは、ホームページ上で、大学合格実績に関しても、じっくりとその学校の目指している教育を読み解いてみてください。ご参考になれば幸いです。
TOMAS全校で無料受験相談を承っています
「志望校に向けて何から始めてよいかわからない」「足を引っ張っている科目がある」「塾・予備校に通っているが成果が出ない」など、学習面でお困りのことはありませんか? 進学個別指導TOMASならではの視点で、つまずきの原因を分析し、課題を解決する具体策を提案します。まずはお気軽にご相談ください。
鳥居先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。











