

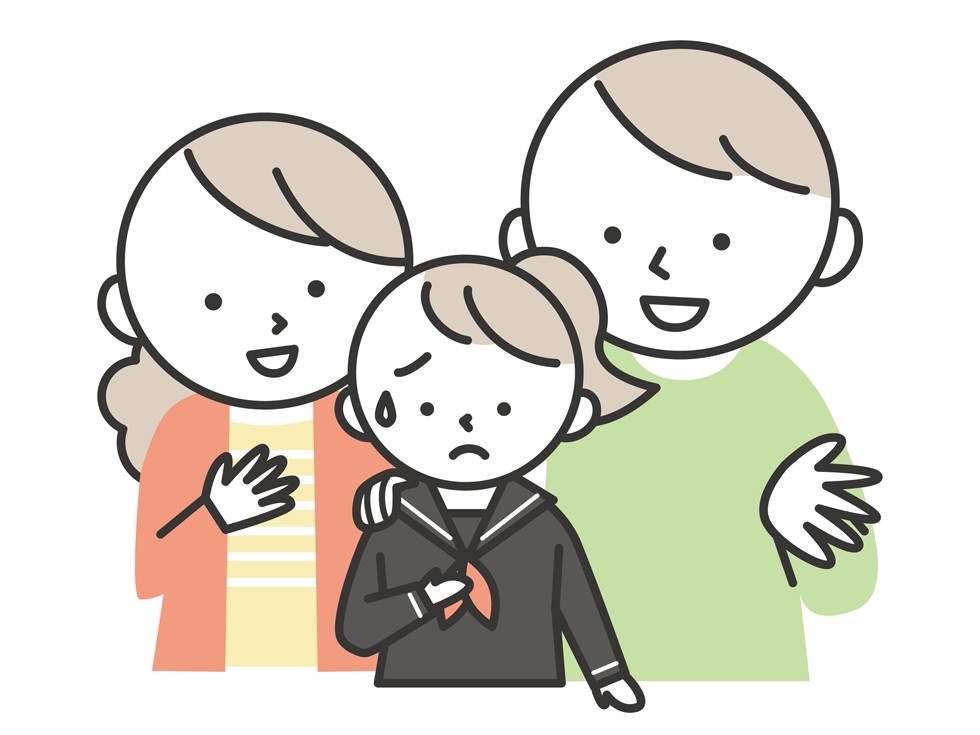
「リベンジ」を考える
首都圏では埼玉県の私立入試を皮切りに、今年も本格的な中学受験シーズンを迎えています。
「首都圏模試センター」の試算では、2025年の1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)の私立・国立の中学受験者数は推定52,300人。過去3番目に多くなる予測で、小学6年生の5人に1人が中学受験に挑む計算になります。
しかしながら、現在、中学受験における第1志望校進学者は3割前後とも言われており、非常に厳しい戦いを強いられているのが現実です。加えて、一昔前のような「記念受験(※1)」を選択するご家庭は激減しており、できるだけ早期に決着をつけるという「短期決戦入試(※2)」が主流です。
※1:記念受験=合格する見込みのない学校を受験すること。
※2:短期決戦入試=通学可能であるにもかかわらず、東京・神奈川入試をせずに埼玉・千葉入試のみで終了すること。あるいは、2月1日から約1週間にわたって繰り広げられる東京・神奈川入試でも受験校を絞って、2月1日・2日、あるいは3日までに受験を終了すること。
これは何を意味しているのかと言えば、多くの子どもたちが「不合格」という現実を突き付けられるということ。そして、そのほとんどが僅差の「不合格」だということです。
中学受験は、まだ12歳という子どもが受ける入試のため、仮に同じ学校の受験生が再び同じように入試をすれば、合格者の半数が入れ替わるとも言われるもの。本当に何が起こるかわからないのが中学受験の怖いところでもあるのです。
関連記事「年末年始、あえて不合格をシミュレーションしてみる」を読む
親にできるのは「まさかは起き得る」を前提にしておくことになりますが、実際に「不合格」の烙印を押される精神的ダメージは想像以上になるでしょう。
しかも、このダメージは大抵の場合、子どもよりも親のほうにくるもの。
本番の期間中であれば一刻も早く、親子で気持ちを切り替え、次の本番を迎えなければなりません。
もし、次を控えているにもかかわらず、つらすぎて立ち直れず、次の一手も考えられないとなった場合は、なるべく早く塾に相談してください。多くの塾の先生が「我々は本番の時の親子のメンタルケアのために存在していると言っても過言ではない」とおっしゃいます。こういう時こそ「餅は餅屋」。プロに頼り、冷静さを取り戻しましょう。「合格」は平常心があってこそです。
それはそれとして、実は本当の問題は、「受験の後」です。泣こうが笑おうが、結果が出た後のほうが重要という意味です。
残念な気持ちを親がずっと引きずるのは危険
受験の結果がたとえ残念な場合であったとしても、多くの子どもたちは「結果」を自分なりに受け止め、春の門出に思いを馳せながら残りの小学校生活を楽しみます。
子どもは自分の力で前を向こうとするのですが、親がその結果をいつまでも引きずるケースは後を絶ちません。
第1志望校への思いが強すぎる親や、進学先の中学校に満足できない親が陥りがちなのですが、これが本当に問題だと感じています。子どもの成長に害しか与えないからです。
特に、お子さんに向かって「リベンジ」を言ってしまいそうになる親御さんは気を付けてください。
「リベンジ」、つまり「中学受験は意に沿わない結果だけど、大学受験では難関大学に入るために頑張りましょう」という意味ですが、これを親が口にしたご家庭で、本当の意味で「リベンジ」できたケースを聞いたことがないからです。
子どもは親が口にするリベンジが「親のためのリベンジ」ということを見抜くのだと思います。これは、子どもの心に刺さらないどころか、マイナスにしかなりません。子どもは自分の中学受験に費やしてきた時間や努力はすべて無駄だったと親に査定されたと解釈し、さらには親の期待に応えられなかった自分を卑下し、自分の力で勝ち取った「合格切符」を全否定されたと感じてしまいがちです。
本来ならば、ワクワクするであろう中学という新たな環境が、「価値がないもの」と無意識にでも刷り込まれる危険性があるのです。
「良いところ探し」で春に想いを馳せよう
親が良かれと思って言葉にする「リベンジ」かもしれませんが、私に言わせれば「百害あって一利なし」。「リベンジ」があるとするならば、それは子ども自身が決めることです。しかも、このリベンジは大学の難易度とは比例しません。
豊島岡の校長先生は「たとえ第2・第3志望の子であったとしても、『この学校で本当に良かった』と思って卒業していく環境を整える」と明言されていますが、その真意は、「毎日が楽しい」と思える子どもは、自分でやりたいことを自由に見つけて、自らの進路を切り拓いていくからという意味でもあります。
この力を育てる時期が中高時代ということなのですが、そもそも、中学受験は親の立場から見れば「子どもに合った環境」を用意するためにあるもの。本来であれば、受験校のすべてが「わが子の成長にとってプラスになる」という判断のもとに選んだ学び舎のはずです。
その中で、様々な人々や出来事に触れ、いかに充実した日々を送るのかが大事であって、それを陰で支えていくのが親の役割なのです。この環境を整えてこそ、子ども自身がどんな人生を歩むのかをじっくりと考えることにつながります。
そうであるならば、入り口の段階から否定や未来への過剰な期待の言葉を投げかけるよりも、中学受験で得た「知識」「頑張り」「あきらめない心」「コツコツと続けた努力」「本番の重圧に耐え抜いた力」などなどの数々の“勲章”があることを認め、来るべく春に想いを馳せるほうが、楽しい未来に近付きます。
過去に、様々な「リベンジを決意した母」を見てきましたが、入学する学校の「良いところ探し」をするように努め、さらに「子どもの人生と私の人生は別物」と悟ったお母さんほど、そのお子さんの成人後の人生が本当の意味で「リベンジしたね!?」というほどに輝くものになったよなぁという実感を持っております。
さあ、時は東京・神奈川決戦直前。「どの学校に決まろうとも、私はわが子の一番の応援団長であり続ける!」と心に誓う準備はできましたか。
ご家庭が一生懸命に選んで、お子さんが掴み取った進学先が待っています。誇りと自信を持って、突き進むのみです。頑張れ、中学受験生の母!
TOMAS全校で無料受験相談を承っています
「志望校に向けて何から始めてよいかわからない」「足を引っ張っている科目がある」「塾・予備校に通っているが成果が出ない」など、学習面でお困りのことはありませんか? 進学個別指導TOMASならではの視点で、つまずきの原因を分析し、課題を解決する具体策を提案します。まずはお気軽にご相談ください。
鳥居先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。











