

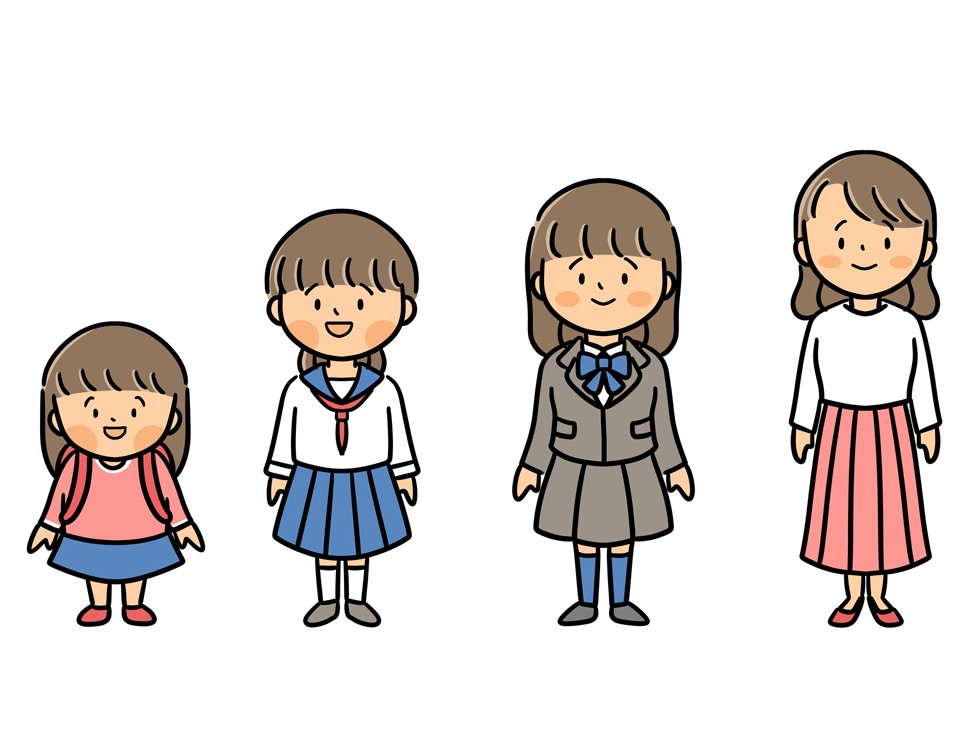
中高一貫校の本当の良さを考える
今年(2024年)の首都圏での私立・国立中学校の受験者総数は52,400人で過去2番目の数字となり、受験率は過去最高の18.12%を記録(首都圏模試センター調べ)。首都圏を中心に中学受験ブームが続いているということが証明された結果となりました。
この人気の理由には、中高一貫校の①大学進学を意識したシラバス(授業計画)、②好調な大学合格実績、③高校受験がないために生じるゆとりある学校生活、④多くの部・委員会活動を通して中学生のうちから高校生との交流が可能、⑤ICTを含めた充実した設備や施設、⑥語学留学をはじめとする豊富なカリキュラム、⑦面倒見の良い補習制度、放課後の校内塾の開設などが挙げられます。
なかでも、⑥の豊富なカリキュラムには目を見張るものがあります。
最近では、どの学校もグローバル教育に力を入れていますので、ネイティブの授業や海外研修はもはや、当たり前。海外提携校への留学や、海外大学進学への道筋が整っている学校も多いです。
さらに、近年は高大連携が進んでいますから、在学中に大学の講義を受講できる学校、逆に大学教授が出張授業に来る学校など、中高生のうちから、様々な分野で専門家のワークショップを体験することが可能です。
またさらに、学問領域だけにとどまらず、企業や団体と連携しながら、実際に商品開発などを手がけ、実社会を体感させているという学校も少なくありません。
特に私立の中高一貫校では、一般的な公立中学校にはない、上記のような魅力的なプログラムが多数用意されていることが多くあります。このようなことが評価され、わが子に幅広い学びを体験させたいと願う親たちから支持されているというわけです。
もちろん、これらはすべて重要な事柄なのですが、今回はあえて別の角度から、中高一貫校の本当の良さを綴ってみようと思います。
変わることのない高い志、理念の素晴らしさ
私はもう20年以上、中学受験の取材をしていますが、個人的には私学に入るということは、目には見えない、その学校オリジナルの文化という空気を吸うことだと思っています。この空気が、やがて、その子の人生を包み込んでいくように思えてならないのです。
つまり、12歳から18歳までの子どもから大人になるまでの時期に吸う空気が、人格形成に強い影響を与えていくということなのですね。
中学受験はとかく偏差値に縛られ、数字が上のほうが良い学校とばかりに、それにこだわる人たちが大勢いる世界です。
しかし、長年、この世界を観察していると、数字ほど当てにならないものはないというのが本音です。
例えば、数字の代表格である偏差値。これは申すまでもなく、母集団の中で、今現在どの位置にいるのかという目安に過ぎません。
当然、いつも同じではありませんが、それは学校の現在地を示す数字に至っても同じことです。
学校ランキングを示す数字は10年どころか、たった数年で激しく上下しているのが常なのです。高偏差値の学校が10年後も高偏差値を維持しているかは誰にも分かりませんし、逆も真なりです。
しかし、変わらないこともあります。それが「理念」です。
教育は、ある意味、「未来への祈り」でもあると思っているのですが、特に私学は創設者の「こういう子に育てたい!」という高い志のもとに開校された教育機関です。
その志が連綿と受け継がれているのが私学です。
ある人気仏教校の校長先生がおっしゃっていました。
「たった1回限りの人生を幸せに生きていく人を育てたい」と。
また、熱狂的ファンが大勢いる女子校の校長先生はこうおっしゃいました。
「生徒たちには卒業しても、ずっと幸せでいてほしい」と。
このようにおっしゃる学校のトップは本当に多く、彼らの思いの源泉は同じです。表現方法に違いはあれど、すべての学校の理念は「人は幸せに生きなければならない」に通じています。
この「幸せに生きる」方法には答えがあり、それが「他者貢献」です。
私は、先述しましたように、もう長いあいだ、多くの私立中高一貫校にお邪魔してきましたが、その泉から湧き出る信念には共通したものを感じます。
いわく「人は一人では生きていけない。
しかし、誰かの何かの役に立つ生き方をしていれば、それだけで人は幸せになれる生き物なのだ。
ゆえに、他者への感謝を忘れず、社会に貢献せよ。
そのために学生時代は体を動かし、勉強しなければならない。
若人よ、学びなさい、経験しなさい、そして、失敗しなさい」
私立中高一貫校が体力・知力、そして心の教育に一生懸命な理由はここにあります。先に挙げた①から⑦の事柄に日々努力しているのも、この理念あってのことなのです。
TOMASの中学受験指導について詳しく知りたい!
資料請求はこちらから
いずれ花開く時が来る教育方法
多くの学校で感心することがあります。
男子校・女子校・共学校、宗教校・無宗教校、大学附属校・進学校と様々な学校がありますが、その学び舎の多くに「大らかさ」を感じるのです。
つまり、焦っていないってことです。これが、子どもたちの成長曲線を熟知している“匠の技”なのだと解釈します。
どうも根底に「人は一生、勉強で、一生、成長し続けるもの」という共通認識があるようです。
実際、「今、わかる必要はない。でも、この教育でいずれ花開く時が来る」と大らかに包み込んでいる姿を目撃することは多いです。
生徒たちから抜群の信頼を得ている校長先生はこうおっしゃっていました。
「本校には、生徒の一生をみる覚悟があります」と。
子どもを大人になるまで育てるには、それ相応の覚悟が必要です。
時には、投げ出したくなることもあるでしょう。でも、その時に、共にわが子を育ててくれると思える学校という存在があるならば、私たち親はそれだけで救われますし、もちろん、子どもにとっても一生ものの、かけがえのない学び舎となるでしょう。
親御さんたち、学校に出向いて、そこに流れる空気を感じて来てください。
どの学校が、わが子が幸せに生きる礎となり得るのか。ポイントは、わが子にとって、呼吸しやすいのはどの学校かという視点で観察することです。
大切な事ほど、目には見えないものです。
それゆえ、学校選択は悩ましく、難しいのですが、中学受験は選べる受験。積極的に見学に行って、選んでください。
わが子がわが子のままでいても、温かくくるまれるかのように感じる学校に出会えるかもしれませんよ。
ちょうど、各学校の行事や説明会もスタートした頃合いです。
さあ、いろんな学校に出向いて、それぞれの泉質の効能を確かめに行きましょう。
関連記事「学校説明会で何を見るかを考える」を読む
TOMAS全校で無料受験相談を承っています
「志望校に向けて何から始めてよいかわからない」「足を引っ張っている科目がある」「塾・予備校に通っているが成果が出ない」など、学習面でお困りのことはありませんか? 進学個別指導TOMASならではの視点で、つまずきの原因を分析し、課題を解決する具体策を提案します。まずはお気軽にご相談ください。
鳥居先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。











