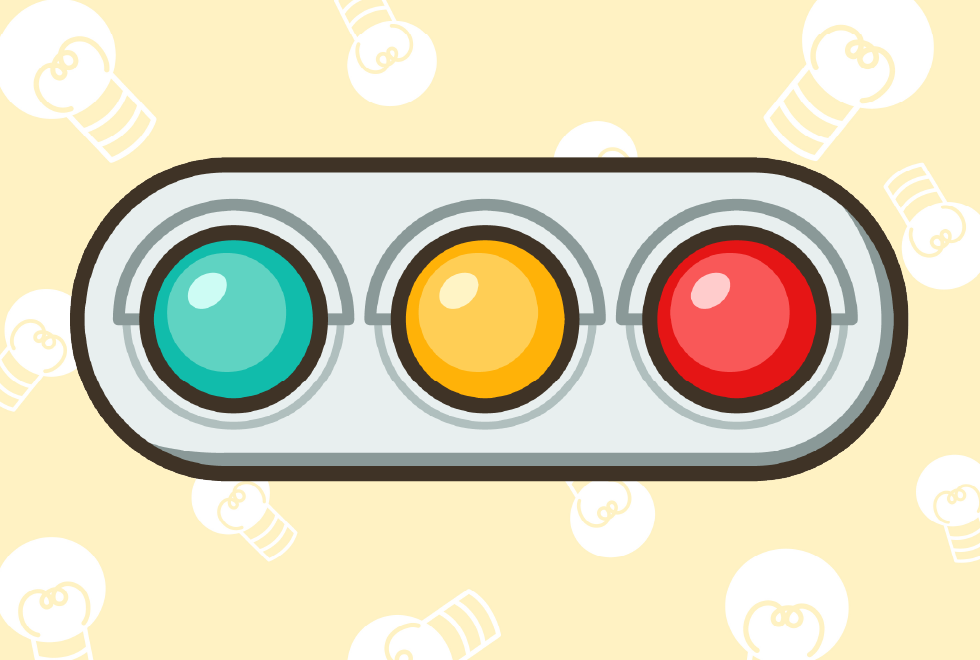「新5年生の学習方法」を考える
この「学年の進級」ですが、特に新5年生のご家庭では、4年生までとは全く違うということに戸惑いを隠せない方もおられるのではないでしょうか。
新5年生は、学習の難度や授業の進度がこれまでと全く違う
これは、学習の難度が増すとともに、授業の進度が速くなることに原因があります。
新しい単元が出てきたり、宿題も多くなったりして、親子ともども消化不良を感じて、悩み出す時期でもあるのです。
こうなると、「子どもにやる気が見られない」→「成績が伸び悩んでいる」→「これでは、とても合格には程遠い」という“負のスパイラル”に陥り、お母さんの方が焦ってしまいます。よくあるケースです。
そして、お母さんは子どもに向かって、こう言います。
「宿題くらい、ちゃんとやりなさい!(じゃないと合格できないわよ!)」
この宿題ですが、進学塾では大量に出されることのほうがむしろ普通です。
「出されたものは完璧に!」という気持ちを持つ親御さんの中には、学習時間を増やすことで、この問題を解決しようとする方がおられます。
しかし、このやり方は「百害あって一利なし」になりかねません。
中学受験は、いかに子どもの「やる気」というモチベーションを保つかにかかっていると言っても、過言ではないからです。
どんなに優秀な子でも、得意・不得意にバラつきが出るのが普通
受験というものは、多くの学校で合格ラインを6割超としています。
つまり満点は必要なく、100点満点だとすれば60点以上取れば合格なのです。
しかも、これは4科(または2科、または3科)の得点合計で決められます。
基本的に、中学受験では足切りを行いませんので、1教科で0点という極端なケースでなければ、総得点が高い受験生から合格を出していくシステムなのです。
どんなに優秀な子どもであっても、科目によって得意・不得意にバラつきが出るのが普通です。
不得意科目は誰もができるという問題を落とさないということを重視し、得意科目は積極的に高得点を狙っていくという“作戦”を持つことが大事になります。
つまり、宿題もそうですが、すべてを完璧に仕上げる必要はないのです。
受験勉強は「優先順位の高い物からやる」のが鉄則
受験には“戦略”が必要で、これは親の出番と言ってもいいでしょう。
子どもは学校にも行かなければなりませんし、たいてい中学受験塾に通っていますので、そこでの物理的な時間も必要になります。
それにプラスして家庭学習の時間を確保しないといけないわけですが、完璧にやろうと思うと、時間はいくらあっても足りません。
そこで、親が考えなければならないことは、「取捨選択」なのです。
受験勉強は、宿題も含めて「優先順位の高いものからやる」ことが鉄則です。
その単元の基礎が理解できていないのであれば、そこをしっかりと補強しなければ、発展問題をやろうとしても応用できないことは明白でしょう。
特に、新5年生になり、新しい単元を次々と学んでいく時に必要になることは「量」よりも「質」という考え方になると思います。
基本的問題の「復習」をして、類題を解き、それが解けたら基礎は定着、その知識を応用問題にまで使えるようにする、ということが目標になります。
ここで、筆者が取材した多くの塾の先生方が推している方法をお伝えしましょう。
まず、授業の中で、テキストに「〇△×」を子ども自身が付けていきます。
「〇」は「類題が出たとしても解ける自信あり」、
「△」は「理解はしたつもりだが、〇ほどの確信は持てない」、
「×」は「全く理解できない」。
そして、自宅学習の時に、やるべき優先順位のトップを「△」の問題にしてみるというものです。
子ども自身が時間をかけてもいいので、ゆっくりと「そっか、こういうことか!」と納得するまで、「△」の問題を考えるということが、“後伸び”を助けると言われています。
さらに、子どもが「わかった!」と言ってくれた時に、お母さんが「お母さんにも教えて」と声をかけて、我が子に先生になってもらうと、なお良いのだそうです。
「子ども自身に知識が定着して、さらに母に教えてあげたという優越感が加わり、やる気アップに繋がるから」ということが先生方のお勧めする理由です。
さらに、気分を良くして、充実感を持って一日を終えるために、時間があって、なおかつ本人がやりたいと言うならば、「〇」問題を復習してみても良いでしょう。
そこで、「『×』問題をやらなくて良いのか?」というご質問が出るでしょう。
しかし、今の時期では優先順位が高くありません。
新5年生は、この時期に受験勉強のリズムにうまく乗ることが大切
中学受験塾の多くはスパイラル(らせん)方式と呼ばれる方法を取っており、入試までに何度も同じテーマを学習できるようにしているからです。
同じことを何回も繰り返す中で、理解を深めるというこの学習方法、これが6年生の夏休み前まで続いていきます。
そして、6年生の夏に総復習の時期を迎え、実戦形式で過去問などを集中的に取り組み出すのが、6年生の秋から本番直前までなのです。
特に、新5年生は塾に行く日数もテストの回数も、今までとは比べ物にならないくらいに増え、新しい単元を次々と教わる日々になっていきます。
つまり、親子で大混乱になりやすいのがこの時期なのです。
だからこそ、この時期に受験勉強のリズムにうまく乗る(=勉強することが苦にならない)ことが、受験生活の中で何よりも大切なことになります。
新5年生のお母さんは、「今は基礎固めに集中」「完璧は必要ない」「量より質」ということに注視してみてくださいね。
鳥居先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。