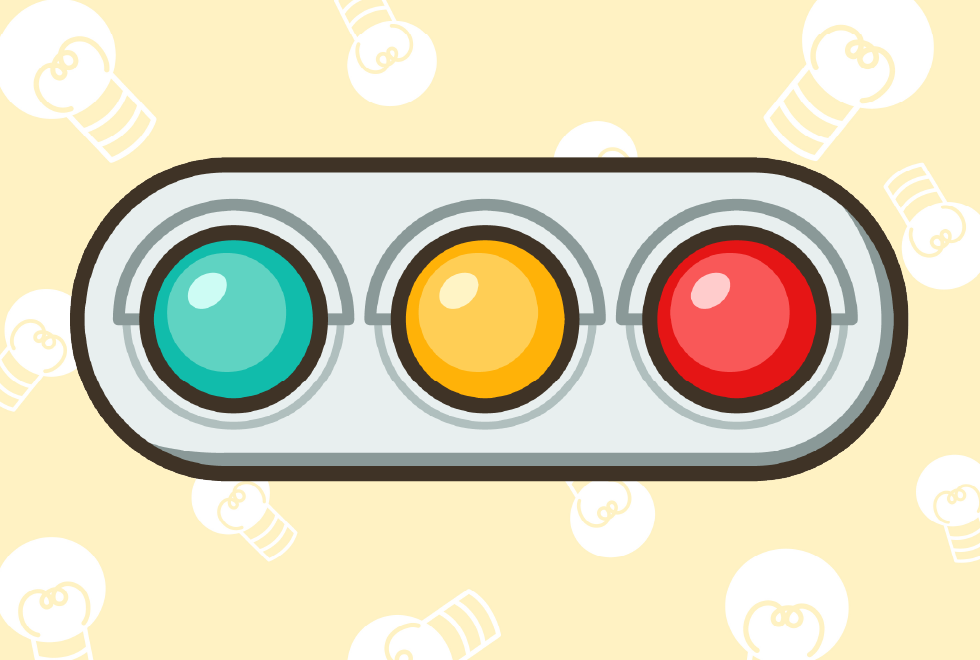宿題・勉強を始めない子には、取りかかりのハードルを下げる工夫が大事
取りかかれば半分終わったようなもの。とにかく大変なのは取りかかること
子どもを叱りたくないのに、どうしても叱ってしまう。
こういう悩みを持っている親御さんはたくさんいます。
叱る原因はいろいろありますが、中でも多いのは子どもの宿題や勉強に関することです。
先日も、ある講演の後でスタッフのみなさんとこの話題で盛り上がりました。
そこでは、次のような声がたくさん出たのです。
「『宿題をやりなさい』と言うと、『今やろうと思ってたのに。もうやる気なくなった』と答える。こっちも腹が立つので、『嘘つき』と言いたくなる」
「いつまでたっても宿題を始めない。散々叱られてから泣きながらやり始める。毎日この繰り返し」
「『いつやるの?』と聞くと、『後でやる』と答える。ところが、いつまで待っても始めない」
「何時間もだらだらしてからやっと始める。始めればあっという間に終わるのに……。だったらさっさとやって、後でのんびりすればいいのにと思う」
みなさんの話を聞いていて、あらためて思ったのは、「やはり、取りかかるのが大変なのだ。取りかかりのハードルを下げる工夫が大事だ」ということです。
そこで、今回は取りかかりのハードルを下げる工夫を2つ紹介したいと思います。
子どもは音楽の影響を受けやすい
1つめは、音楽への条件反射を活用する方法です。
私が小学校の先生だったとき、家庭訪問で訪れたある家でお母さんと話をしていると、突然ラジカセから音楽が聞こえてきました。
すると、子どもが急いで勉強を始めたのです。
私が驚いていると、その子のお母さんが言いました。
「タイマーをセットして、毎日決めた時間に同じ音楽が流れるようにして、その音楽が終わるまでに勉強を開始すると決めてあるんです。しばらく続けていたら条件反射みたいになって、がみがみ言わなくても済むようになりました」
勉強を始めたら音楽は流さないのですが、とにかく取りかかりのきっかけとして活用しているということでした。
私は「すばらしいアイデアだな」と思いました。
確かに、子どもは音楽の影響を受けやすいところがあります。
学校でもそれを活用していることがけっこうあります。
例えば、昼休みに、「クシコス・ポスト」「天国と地獄」「道化師のギャロップ」「剣の舞」などのアップテンポな曲がかかったりします。
こういった曲を聞くと、外で元気に走り回りたくなります。
下校時刻になると、「蛍の光」や「家路」など、さみしげな曲がかかります。
これを聞くと帰りたくなりますよね。
もちろん、これらは曲の調子の影響が大きいのですが、一定期間にわたって毎日同じ時間に同じ曲を聞いて同じ行動をしていると、条件反射のようになってくるのかもしれません。
「自分で選んだ曲だから守らなければ」という気持ちが働く
この経験について、私は講演でもよく話してきました。
すると、それを聞いたある親御さんが実践してくれました。
その家では、1カ月ごとに曲を変えます。
月の終わりになると、来月はどの曲にするかを親子で相談します。
子どもは「え~と、どの曲にしようかな……」といろいろ考えて、毎回30分くらいかけて選曲します。
すると、「せっかく自分が一生懸命考えて選んだ曲だから守らなければ」という気持ちが働いて、勉強に着実に取りかかれるようになりました。
親が一方的に「この曲が終わるまでに勉強開始だよ」と押しつけるのではなく、「自分で選んだ曲だから」という気持ちが大事なのでしょう。
ある50代の私の知人は、自宅の書斎で仕事を始めるとき、映画「ロッキー」のテーマ曲を聴くそうです。
仕事のやる気が出ないときも、この曲を聞くとスイッチが入ると言っています。
TOMASの中学受験指導について詳しく知りたい!
資料請求はこちらから
ウォーミングアップ法で、その後の取り組みをスムーズに
2つめの工夫はウォーミングアップ法です。
例えば、あるお母さんは、大きい付箋紙に次のような簡単な計算問題を5問書きます。
加減乗除のどれか1つに絞ることもありますし、混ぜることもあります。
5×8 7×3 6×9 3×4 8×8
72÷9 3×8 8+5 13-7 2×8
そして、その付箋紙を、子どもがその日にやる問題集のページの一番上に貼っておきます。
非常に簡単な問題なので、取りかかりの抵抗が少なく、子どもはさっと取り組んでくれるそうです。
あっという間に終わって、お母さんが丸つけをします。
1問20点です。
当然、いつも100点を取ることができます。
こんな簡単な問題でも、子どもはやはりうれしくてけっこう喜びます。
そして、これがウォーミングアップになって、その後の問題集への取り組みもスムーズになるのです。
このウォーミングアップ法をおこなう前は、なかなか問題集に取りかかれなくて、ぐずぐずしている時間が長かったのですが、今はそういうことがなくなったそうです。
リトルサクセスによって線条体が活性化すると、スイッチが入る
脳科学によると、このウォーミングアップ法は、やる気にさせるための方法として、理にかなっているようです。
脳の中には「線条体」という部位があって、ここがやる気を司っているところです。
そして、この線条体が活性化するのは、リトルサクセスでちょっとした達成感を味わったときだそうです。
つまり、子どもは、簡単な計算問題をやって、しかも100点満点を取ることで、ちょっとした達成感を味わうことができるのです。
これでスイッチがオンになり、次の問題集にも取り組めるようになるというのです。
わが子に合う方法を編み出そう
以上、2つの方法をご紹介しました。
とにかく大事なのは、叱って済ませるのではなく、子どもが宿題や勉強に取りかかれるような、具体的な工夫を考えることです。
今回紹介した2つのほかにも、「取りあえず準備方式」「取りあえず1問方式」「お支度ボード」「模擬時計」「家庭内時間割」「ストップウォッチ&タイマー活用法」などの方法もあります。
ぜひ、わが家のわが子の実情に合わせた方法を編み出してください。
TOMAS全校で無料受験相談を承っています
「志望校に向けて何から始めてよいかわからない」「足を引っ張っている科目がある」「塾・予備校に通っているが成果が出ない」など、学習面でお困りのことはありませんか? 進学個別指導TOMASならではの視点で、つまずきの原因を分析し、課題を解決する具体策を提案します。まずはお気軽にご相談ください。
親野先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。