
最難関校合格を勝ち取る 中学受験の「算数」勉強法
Math Study Tips for Top Junior High School Entrance Exams
中学入試において最も得点差が開きやすい教科は、何といっても算数。最難関校の算数には、一見しただけではいったいどこから手をつけたらよいのかわからない難問が続出しています。
このカテゴリでは、最難関校の算数対策として必要な勉強法をじっくり説明していきます。

【中学受験の「算数」勉強法①】「算数が苦手」な原因はココにある
powered by Spec. TOMAS
算数が苦手な原因は、学年によって多少変わるものの、おおまかには以下の6つに分類できます。とくに、最難関校受験に大きくかかわるのは「原因④」と「原因⑤」です。
| 原因① | 計算力不足 |
|---|---|
| 原因② | 解法の理解不足 |
| 原因③ | 問題文の読解力不足 |
| 原因④ | 表現力不足 |
| 原因⑤ | 演習量不足 |
| 原因⑥ | 特定分野の理解不足 |
以下、順番にお話ししていきます。
原因①計算力不足
四則計算が苦手だと、頭の中で考えきれない
「計算力不足」のケースは、おもに2つあります。
1つ目は、3年生までに習う整数範囲の四則計算がうまく処理できないというケースです。4年生からは、「単元学習」という、入試問題を解くうえで必要となる単元ごとの網羅的な勉強が始まります。その際、たとえば「2ケタ×1ケタ」「3ケタ×1ケタ」「2ケタ÷1ケタ」などの基本的な計算が苦手なままだった子は、頭の中で考えきれなくなってしまいます。そうなることを防ぐためには、3年生までに整数範囲の基本的な計算方法をマスターし、計算力を強化しておくことが必要です。
小数・分数が苦手でフリーズしてしまう
2つ目は、小数・分数の計算が苦手だというケースです。単に計算が遅いというケースだけでなく、小数・分数で割り算などがからむ問題だとまったく手が動かなくなるというケースもあります。小数・分数という考え方は、それまでに習ってきた整数とは異なる新たな概念です。そのため、多くの子どもが、最初はこの考え方になじめず、もがき苦しんでしまいます。
小数・分数の計算には慣れが肝心です。計算は、「うまくできる」だけでなく、「手足のように使いこなせる」必要もあります。計算問題の演習をルーティン化し、小数・分数を縦横無尽に駆使できるレベルに到達していきましょう。
原因②解法の理解不足
抽象的な問題文から具体的なイメージが描けない
算数では、学年が上がるにつれ、出題される問題文の抽象度も上がっていきます。その結果、どの解法を使えばよいのかが問題文から読み取れず、そのまま算数が苦手になっていく、というケースが生じがちです。
そうなることを防ぐため、低学年のうちから問題文の抽象的な内容を具体的な内容に置き換えて読む習慣、別の言い方では、問題文の「情景」をイメージしながら読む習慣をつけていきましょう。算数の勉強では、問題文中の算数用語を、日常的によく使う言葉に一つひとつ置き換えながら具体的なイメージとともに考えていくことが必要です。
原因③問題文の読解力不足
数字だけ見て解こうとしてしまう
「読解力」と聞くと、「国語の話ではないのに、なぜここに出てくるのか?」と不思議に思う方がいるかもしれません。しかし、算数でも問題文の読み取りが必要ですから、読解力はとても大切なのです。
問題文の読み取りが苦手な子には、1・2年生の段階から悪癖が身についてしまっています。その悪癖とは、問題文をしっかり読まず、出てくる数字だけを拾って解いてしまう、という姿勢です。そうなることを防ぐためには、1・2年生のうちから、数字を追って読むだけではなく、問題文全体を正しく読むという習慣をつけていきましょう。
習慣づけとしてもう1つ大切なのは、問題文を分析的に読むことです。これは、たとえば、「Aさんが支払った金額」を答えるべきなのか、「Bさんが支払った金額」を答えるべきなのか、などに注意する読み方を意味します。このように、問題文に与えられた条件に気づくという能力も読解力に含まれる、と考えてください。
「音読」は、読解力向上に効果あり
読解力を鍛えるための有効な方法が2つあります。1つ目は、問題文中の重要な箇所に下線を引くことです。2つ目は、問題文を「音読」することです。
受験生の中には、問題文中の重要な箇所を読み飛ばしてしまう子がいます。しかし、このように「目を滑らせてしまう」子でも、問題文を自分で音読すると、それまでわからなかった箇所が理解できたり、出した答えの間違いに気づいたりするのです。
試験本番で音読することはできませんが、音読に慣れてくると、頭の中で「音読」する方法、すなわち「黙読」が身についていきます。音読は、黙読のきっかけとして重要なのです。
最難関校の入試問題攻略に必要なのは、「読んで」「解いて」「照らし合わせる」こと
読解力関連で最後に取り上げたいテーマは、最難関校入試問題の特徴に関するお話です。
たとえば、最難関校である開成中の入試問題には、大問が3題、もしくは4題しかありません。そのため、大問の最初に書かれてある問題文、およびそこにぶら下がっている小問1問目の設問文が正しく読み取れないと、それ以降の小問も総崩れとなり、1題分丸ごと「全滅」してしまいます。
このような致命的エラーを防ぐためには、問題文を読んで解いた結果が問題文の条件と合っているかどうかを、問題文にもう1度戻って照らし合わせるというプロセスが必要です。誤読を回避し、合格の可能性を高めていきましょう。
原因④表現力不足
「図式化」の能力欠如
算数における「表現力」とは、問題文から読み取った内容を図や式などとして適切に表せる能力を意味します。しかし、多くの受験生は図や式をかかず、問題文中の情報を頭の中だけで処理してしまう傾向にあります。
最難関校の入試問題を解くには、問題文中の情報を図や式に置き換え、「図形」や「数」をイメージとしてとらえるという「図式化」の能力が必要です。低学年のうちから、問題文を見てカチャカチャ手を動かしながら図や式をたくさんかくことによって、「図形」や「数」のイメージをおさえていきましょう。「表現力」は、このイメージによって築かれていきます。
原因⑤演習量不足
苦手分野から逃げてしまう
「言わずもがな」というお話ではありますが、意外に多いのは、そもそも勉強量が足りていないというケースです。
受験生の中には、「ここは苦手だから、ここまでしか勉強したくない」と言って、苦手分野の学習から逃げ回っている子がたくさんいます。このような、「苦手分野の放置」が招く「演習量不足」は命取りです。中学受験は、たとえ得意な箇所で高得点がとれたとしても、苦手な箇所で得点できなかったら不合格になってしまうからです。
苦手分野の勉強に対してやる気を起こすことは、とても大変です。そこで、最初から大きすぎる目標は立てず、細分化した目標を少しずつ達成していくという方法をとりましょう。勉強量を確保するためには、このように、できなかったことを一歩一歩できるようにしていくという「スモールステップ」が有効です。
原因⑥特定分野の理解不足
すべての分野が苦手だとは限らない
中学受験の算数には、「計算」「図形」「文章題」などの分野が含まれます。これらの分野に関する好き・キライには受験生個々人で濃淡があり、それらは得意・不得意の状態に直接つながっていきます。
たとえば、受験生の中には、「図形は好きだけど、文章題はキライでやりたくない」という子がいます。こういう子は、問題文の分量が少ないため1・2文だけ読めばよい図形問題は喜んで解きます。一方、文章題は、「問題文が長いから、読みたくない」と言って放棄してしまいます。6年生から「過去問演習」に入ると、こういう子はますます増えていきます。このような子は、読解力にかかわる部分が弱いのです。「原因③」に示した「問題文の分析」「問題文の音読」を実践し、読解力向上を図りましょう。
反対に、「文章題は好きだけど、図形は苦手だ」という受験生もいます。このような子の場合には、「図形の見方がわからない」「平面図から立体図がイメージできない」などの症状が見られます。この原因は、図形を視覚的にとらえることができないという「図形の感覚」不足です。
この「図形の感覚」を、4年生から始まる「単元学習」と並行して鍛えていくことは非常に困難です。まだ時間的余裕がある2年生後半~3年生の時期までに、たとえば算数パズルなどで三角形や四角形のような基本図形に触れることによって「図形の感覚」を磨いていきましょう。
まとめ
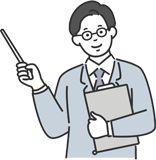
最難関校の算数において得点力を左右するのは、「図式化の能力」と「圧倒的な問題演習量」です。低学年のうちからじっくり時間をかけて図形に慣れ親しみ、勉強量も確保していきましょう。
■夢の志望校合格に導く 低学年からの難関中学・難関校対策個別指導塾[スペックTOMAS]
https://www.tomas.co.jp/spec/
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。








