
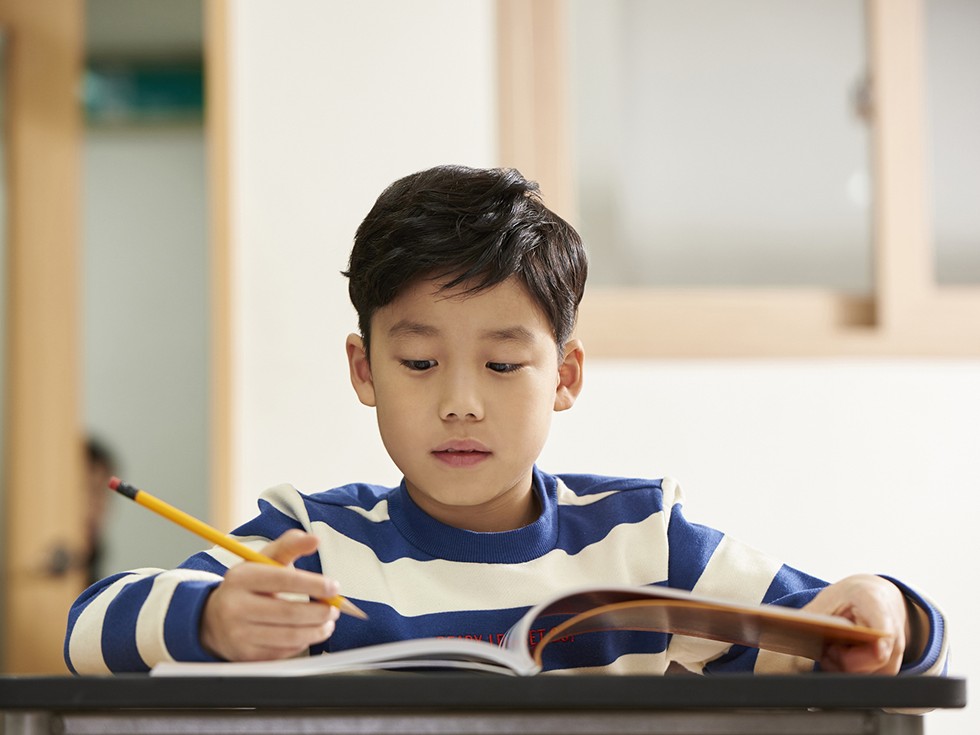
【中学受験】小3で始めること、やることって何?
中学受験の準備を始めるのは、受験本番までのスケジュールや子どもの特性から見て、小学3年生がベストといわれます。本人が進学塾に通うだけでなく、家族全体でさまざまな面から協力する必要があるからです。なぜ小3から中学受験を始めるのか、その際、どのようなことに注意したらいいのかを考えます。
中学受験は小3の2月から始めるのがベスト
小学校の新学期といえば「4月」ですが、進学塾は2カ月前倒しの「2月」から新学期が始まるのが一般的です。それには先取り学習や、子どもの発達、生活面などさまざまな理由があります。
中学受験において、小3とはどんな時期?
小3になると自分でできることが増え、小1・2年のときのように保護者が手取り足取りかかわらなくてもすむ場面が出てきます。学校以外にも、習い事や友達と遊ぶ場面が増えて、視野も広くなるこの時期は、中学受験の準備に取り掛かるのにふさわしく、小3は中学受験に最適なスタートラインといえます。
なぜ小3の2月のタイミングなの?
では、なぜ「2月」なのでしょうか。小学校の新学期は「4月」ですが、中学受験を目指す進学塾の多くはそれよりも2カ月早い「2月」から始まるのが一般的です。小3も終わりにさしかかる2月に「新4年生」としてスタートするのです。
実質的に受験勉強は4年生から始まるのですが、進学塾という新しい環境に慣れるまでには時間が必要です。準備段階として小3の終わりが最適なタイミングなのです。
小3から中学受験を始めるメリットは?
勉強が難しくなってくる小3で、中学受験の勉強を始めるのはメリットがたくさんあります。算数なら割り算、小数や分数といった新しい計算方法や概念が出てきます。国語なら新出漢字は200字となり、抽象的な言葉を使った長文、ことわざや慣用句も出てきます。これらは中学校以降の勉強の土台にもなる基礎・基本です。小3でのつまずきを発見し、取りこぼさないためにも小3から中学受験を始める意味があるのです。
小3から中学受験を始めるデメリットは?
発達の個人差が大きいのが小3の子どもたちです。いわゆる「9歳の壁」と呼ばれる年齢にあたります。体は大きく成長し、自己肯定感を持ち始める時期でもありますが、反面、他者との差を感じ、劣等感や不安を抱くようになってきます。
また、友達関係が深まるのと同時に、人間関係のトラブルも起きがちになります。中学受験の勉強や進学塾に通う場面においても、こうしたリスクがあることを心に留めておきましょう。
中学受験のために小3から取り組めること
小3の子どもの特徴は「知的好奇心」が旺盛なことです。物事と自分との間に距離を置いて見ることができるようになり、自分のことも客観的にとらえられるようになります。この時期の中学受験の始め方は、子どもの知的好奇心を上手に利用し、勉強への興味や関心、意欲を高めることにあります。具体的な方法をまとめました。
最初は学校の宿題に、家庭学習を加える
進学塾に通い始める前の段階として、学校の宿題に加えて家庭でできるドリルなどを解いて、学習時間を増やす準備を始めてみましょう。学習系の習い事でもいいのですが、送迎や費用面などを考えると負担が大きいものです。それよりも、基礎・基本の定着も兼ねて、家庭で教材を解いてみるのが効果的です。お子さんのこれまでの理解度も把握できます。
勉強と遊びを切り替えられるように生活をシフト
通塾が始まると、塾で勉強する時間のほかに「塾の宿題」をこなす時間も必要になり、勉強時間が増えていきます。それまでの学校の宿題と遊びの生活から、進学塾に通う生活モードへの切り替えは、本人も保護者も努力を要します。
そのプレ段階として、小3の2月までに勉強の習慣をつけておきたいものです。夕食前後のゲームや、朝にテレビを見る時間を短くしていく必要があります。ただし、遊びを無理に中断させるのはストレスの元になります。「〇時までに宿題を終わらせる」などの区切りを示して、集中しメリハリをつけながら勉強する経験が大事です。
暗記や調べ方の工夫は楽しく
中学受験では、問題を解くための土台となる知識が豊富に必要です。小3からは生活科に代わって新たに「社会科」「理科」が始まり、覚える内容も増えてきます。
都道府県名などを覚えるにはポスタータイプの教材を、トイレなど目につきやすいところに貼っておくといいでしょう。ダイニングに貼っておくと、ニュースが流れたときなどに家族で共通の話題にでき、印象に残りやすくなります。
また、家族の手の届くところにあえて紙の辞典や電子辞書を置いておくと、「調べて確かめる」習慣が身につきます。スマートフォンでインターネット検索をするなら、動画サイトやSNSなどほかのコンテンツに興味が移らないように気をつけましょう。
不安やストレスを軽くする「ほめ」を忘れずに
自立心が芽生えてきて、保護者との距離も少しずつできてくるのが小3の時期です。これまでは親に学校であったことを毎日話してくれたのに、「いつも通りだよ」などとそっけない返事をしたり、秘密にして話してくれない子も出てきます。
保護者としては、接し方に戸惑ったり、悩んだりすることも増えますが、この時期の子どもは不安やストレスから自己肯定感が低くなりがち。少しでもできたことに対して、保護者が具体的にほめれば(「次の塾の日までに宿題が終わってすごいね」など)、子どもは自信を回復していくでしょう。
小3からの中学受験を保護者はどうサポートすればいい?
新4年生として通塾が始まると、保護者もその生活に適応していかなければなりません。中学受験をするかどうかの最終判断は「子どもの気持ちに任せたい」という保護者も多いと思います。その判断をするうえでも、勉強をすることが学校を選び、将来の夢の実現につながるということを、子どもが意識できる環境を整えていきたいものです。
生活面では「習慣化」がポイント
小3にもなると「歯磨き」が自分一人ででき、「習慣化」している子どもも少なくないでしょう。中学受験の勉強でも、保護者や先生からいわれてではなく、自分から進んでやろうとする力が求められます。
そのため、生活面においては勉強を習慣化することを目標に過ごすのがおすすめです。行動を習慣化するコツには諸説ありますが「短時間から始める」「決まった時間にする」「成果を目に見える形にする」など、無理なく継続するのがポイントです。
勉強面は「楽しむ」から「基礎・基本の定着」へ
小学校低学年では、進学塾であっても勉強することに楽しさを感じさせ、興味や関心を高める工夫をしています。ですが、小3の2月から始まる「新4年生」では、学習内容の基礎・基本をしっかり身につけることが狙いになります。
先取りや発展的な内容を学ぶ進学塾での勉強も、土台となるのは基礎・基本です。これが身についていないと、だんだんと進学塾の内容についていけなくなってしまいます。つまずきを発見したら、その単元だけをやり直すのではなく、つまずきの原因となっている内容をたどって、学び直す意識が必要です。
保護者も中学受験に向けて心の準備をスタート
中学受験を経験した家族の中には、「子どもが行きたいというから、試しに塾に通わせてみた」という、軽い動機から始めたご家庭も少なくありません。きっかけは何であれ、実際に中学受験に挑戦するなら保護者も子どもと同じように、準備を進める必要があります。
働き方や生活スタイルの見直しも
学校生活と塾生活を両立させるには、保護者のサポートが必須です。最初のころは送迎も必要ですし、塾の宿題を一緒に見てあげる時間も必要でしょう。塾のある日とない日の過ごし方や、ほかの習い事との調整などで保護者は一気に忙しくなります。
学童保育が小3までで終わる地域では、そもそも放課後の子どもの過ごし方をどうするかが課題となります。場合によっては、保護者が勤務時間を調整するなど、働き方の見直しを迫られることも。数年後に来る本格的な受験生活をイメージして、環境を整え、家族で話し合える「時間のゆとり」も、小3の時点ならまだたっぷりあります。
人や社会、自然にふれる直接体験も大事にしたい
コンピューターの普及にともない、デジタルメディアを通じた疑似体験や間接的な体験が、私たちの生活の多くを占めるようになっています。
ですが、中学受験では知識やその活用力を問うペーパーテスト型の入試のほか、ディスカッションやグループワークなどを取り入れたコミュニケーション型の入試が始まっています。こうした時に強みを発揮できるのは、それを実際に経験している受験生です。
塾での勉強も大切ですが、家族以外の人と会って話をする、学校や塾以外のコミュニティに参加して同年代の子どもと話をする、家事の手伝いをして生活のスキルを知っておく、自然を五感で感じられる場所に行く、など「直接体験」の場をなくさないようにするのが、中学受験で保護者ができる環境づくりともいえるのです。
まとめ
中学受験をするのに、「小3では早すぎる」と考えるか、「小4のプレ段階として早めに準備しておく」と考えるかは保護者次第です。かつては小4、小5からでも十分間に合うとされた時代もありましたが、社会情勢の変化や子どもの特性などから考えると、現時点では小3がベストタイミングといえるでしょう。
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。








