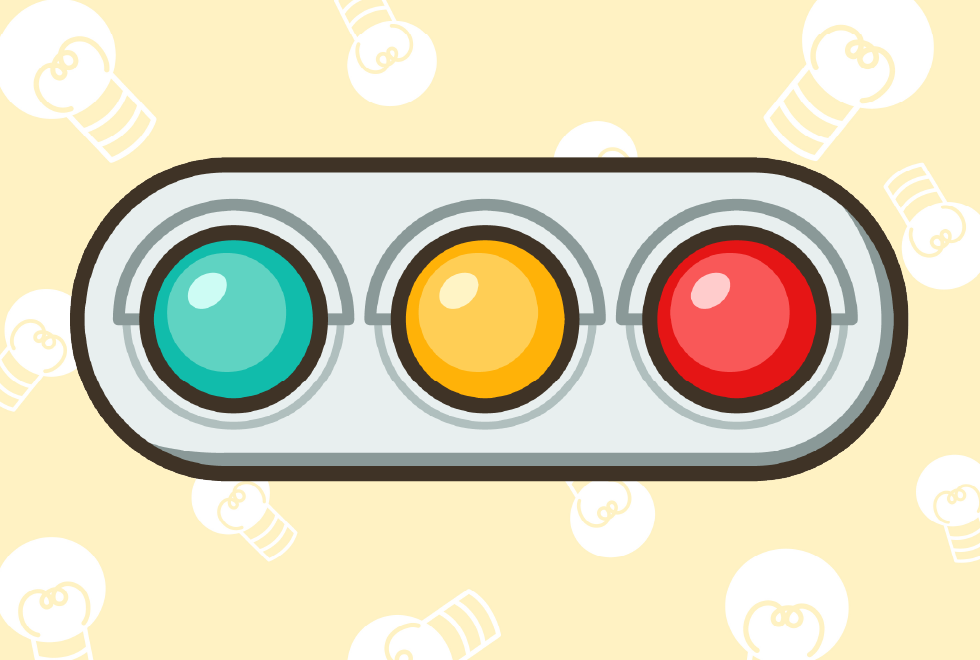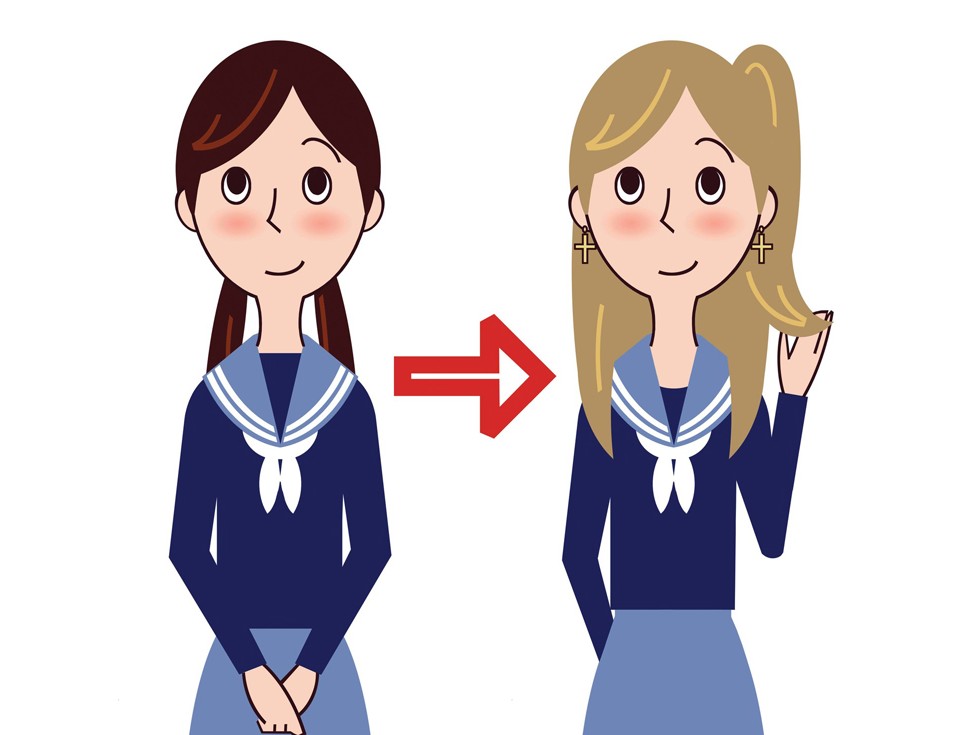
中高一貫校の校則を考える
中高一貫校を「校則」という切り口で見る
最近よく耳にする言葉に、「ブラック校則」というものがあります。
これは、「理不尽さや不可解さに満ち溢れている校則」という意味で使われている言葉です。
例えば、地毛が茶色い人でも校則に合わせて黒に染めることを強要される、下着の色を「白一色」と定められる、「丸刈り」を強いられる、といったことに代表されます。
その目的が、子どもたちへの教育的意義というよりも、子どもたちを管理するためにあるとして、物議を醸しているのです。
要は、ブラック校則は「合理性のない人権侵害」ではないのか? という議論です。
この議論は置いておくとして、「校則」というものにフォーカスするならば、中高一貫校を別の切り口で見ることができます。
校則のない学校と、校則がしっかり機能している学校
中高一貫校は、その教育理念に従って生徒を指導・教育していますが、校則から見た場合、「全くない学校」「存在はするが、事実上ないに等しい学校」「存在はするが、ペナルティは厳しくない学校」「厳格に機能している学校」に分かれます。
校則がない学校としては、麻布、筑波大学附属駒場、灘、和光、自由の森学園、明星学園などが有名です。
校則がないというよりも、明文化された校則がないのです。
例えば、麻布には校則のようなものとして、「麻布3禁」というものが存在しています。それは ①鉄下駄禁止、②麻雀禁止、③出前禁止を指すそうです。
鉄下駄を履いて来るほうが大変な気がしますが、要するに「外から律されるのではなく、自分の中に揺るぎない基準を作りなさい」ということで、校則を敢えて作っていないのだと聞いています。
校則がない学校は、「自由な校風」で知られています。
一方で、カトリック校などを中心に、校則がしっかりと機能している学校も数多く存在しています。
例えば、スカート丈、傘の色、髪ゴムの色、髪型などに指定がある場合や、学校帰りの寄り道が禁止されているなどということがあります。
一見、厳しい校則のようですが、そこには各校独自の深い思いがあるのです。
子どもたちは、校則についてどう思っているのか?
校則が厳しい学校に取材をすると、校則については、主に次の2点を重要視していることが分かります。
- 集団生活の中で教育を平等に受けるためには、ある程度のルールが必要
- 品格を保つため
もう少し長く説明するならば、スポーツにルールがあるように、校内でもある程度のルールがあったほうが、円滑に物事が進み、落ち着いた環境下で教育ができるということでしょう。
さらに、身だしなみの乱れが生活の乱れに繋がるということを熟知されているので、それを防ぐ意味合いがあるのだと思われます。
私は、「今時の子」が本当はどう思っているのかと、色々な学校で、直接、生徒たちに話を聞いて回ってみました。
すると、どの学校でも受験を経て入学している、つまり、自分で選んで入学しているために、それぞれに校則も含めた“学校愛”を語ってくれる子が多い、という印象を持ちました。
自由な校風の学校では、「学校が自分たちを信頼してくれているのが分かるので、ありがたいし、学校が大好きだ。その自由の火を消さないためにも、自主規制をかける」という答えは多く見られます。
また一方で、校則が厳しめの学校の生徒さんの多くはこう答えてくれます。
「校則があった方が逆に守られている気がする。みんなが同じ条件で暮らしているので、ある意味、平等。余計なこと(例えば、明日着て行く服をどうしよう、髪飾りは何にしようといったこと)に悩まされずに済むので、慣れると毎日が平和で穏やかで居心地が良い」
私は、“校則が山のようにある学校”の男子生徒さんのこの言葉で、思わず吹き出してしまいました。
「校則は多いだけで、取り締まりは厳しくない。てゆーか、取り締まられたことがないっす」
すべての校則がごくごく常識的なことなので、守るまでもなく、結果的に、ごく自然に守っているということらしく、意識したこともないということでした。
校則は何のために必要かを、家族で話し合ってみる
中高一貫校の魅力は、何といっても、自分で選んで行けることです。
それぞれのご家庭が、我が家の教育方針、我が子の個性を鑑みて、決めることができるのです。
自由と義務、自主性と自己責任、多様性と画一性などをどのように考えるのかによっても、選択肢は変わってきます。
「ルールは何のためにあるのか?」
「校則は必要か?」
この2つの議題を家族で話し合うだけでも、ご家庭のプラスになります。
親から見れば、自分たちが教育に何を求めているのかがはっきりしますし、子どもにとっても、「社会を自身で考える」というきっかけになるでしょう。
中学受験の勉強は「なぜ?」を知り、考えることです。
思えば、それは、子どもの未来にとって、とても贅沢で素晴らしい経験です。
その意味でも、この機会に、一度、ご家庭で「校則」について話し合ってみることをお勧めします。
鳥居先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。