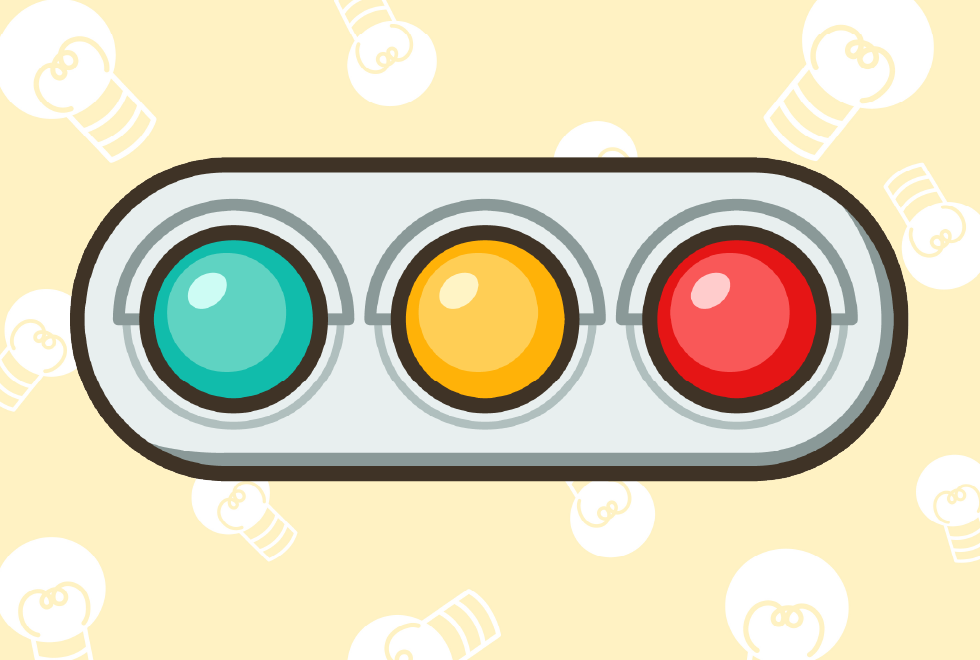読書好きなこどもにするためには?読書嫌いな子は受験に不利?
国語は“はっきりと書かれていない答え”を問われる教科
天候もおだやかで、食べ物もおいしい季節です。
冬期講習などの追い込みを前に、体調を整えたり、基本的な学力を伸ばしたりするにはよい時期です。
そこで、改めてこの時期の学習への取り組み方について、考えてみたいと思います。
中学受験で対策が難しいと感じる教科のひとつが、「国語」ではないでしょうか。
漢字の書き取りなどは別として、読解問題などは、筆者や登場人物の考えや感情などが言葉ではっきりと書かれているわけではなく、とても抽象的です。
そこから出題者の意図を汲み取って、答えを出す能力が必要になります。
そんな抽象的なことを考えるのは苦手、という子どもはたくさんいますね。
その力を育てる対策のひとつとして挙げられるのが、「読書」です。
では、読書がきらいな子は受験に不利なのでしょうか?
わが子を読書好きにするには、どうしたらいいのでしょうか?
読書好きは、読み解くことができ、言いたいことが書ける
では、読書好きな子は、受験に有利になるのでしょうか。
本を読むのが好きな子は、その楽しみを覚え、たくさんの本を読んできていますね。
そうすると、その本の筆者の言いたいことを読み取りながら理解する、「読解力」をつける訓練になっているはずです。
また、本を読み慣れていれば、黙読のスピードがついていますから、試験の時に余裕を生み出します。
さらに、多くの文章に触れてきた子どもは、語彙も豊富で、様々な言い回しに慣れています。
問題を読み、理解し、答えを書く時に、それらの基礎力は大変有利に働くと思います。
きちんと読み解くことができ、言いたいことが書ければ、どの教科でも得点しやすくなるのです。
読書嫌いが受験に不利と思い込むことが、不利な状況を生み出す
このように言われると、「わが子は読書が嫌い! あまり本を読まない!」と、頭を抱え込む親もいらっしゃるのではないでしょうか。
中には、読書好きにしたいと思って、幼いころからさんざん読み聞かせをしてきたにもかかわらず、子どもは本を読まない、というケースも少なくありません。
では、読書嫌いは受験に不利なのでしょうか?
いいえ、そうとは言い切れません。
もちろん、好きに越したことはありませんが、嫌いだからと言って、受験に不利であるということは言えないと思います。
一番の問題は、「そう思い込むこと」です。
本を読んできてないから国語力が低く、受験には不利だと思い込むことが、不利な状況を生み出すのです。
読書が好きでも、国語の成績に反映しないというケースもあります。
要は、問題を読み、理解し、答えを書くことができればいいのです。
ところが、読書嫌いの子の多くは、問題を読み、理解することが苦手です。
文章を読み慣れていないので、長文などに対する嫌悪感を持っているのかも知れません。
この時期に必要なのは、その苦手意識を克服することです。
読み書きの能力の基礎は、「聞くこと」「話すこと」から生まれる
私たちの読み書きの能力の基礎は、「聞くこと」と「話すこと」から生まれます。
読むことが苦手なら、聞くことから始めましょう。
つまり、問題文の音読です。
音読は、自分の声を聴く読書法です。
まずは、あまり構えずに、問題文を音読させましょう。
そして、親のほうから、この問題文は何を問うているのかを問いかけます。
「この問題は、何をせよと言っているのかな?」という具合です。
子どもは、親の問いに答えて話すことで、問題文を理解し始めます。
この時、子どもの問題文の捉え方が違うと思っても、「違う」と言わずに、「なるほど。ではもう一度読んでみてごらん」と、再度音読を促します。
何度か読むうちに、子どもはその出題の意図を理解します。
この過程では否定語を使わず、2回3回と読んで理解が進んできたら、「そうです。よくできました!」と認めてあげてください。
次第に、文章を読むことへの苦手意識がなくなっていきます。
間違った問題を見直す時も同じです。
何を問われたと思い、どう答えたらよいと思ったのかを、親を相手に言葉にして説明させるのです。
この時も、親は「そうじゃないでしょ」とは言わず、「もう一度読んでみようか」と音読を促します。
この作業の目的は、「苦手意識の克服」です。
中には、耳から聞くだけより目で追ったほうが理解しやすい、という子もいます。
そういう場合には、音読しながら問題文に線を引いたり、印をつけたりする方法もあるので、その子にあった方法を探してみてください。
読書好きは人生を豊かにする
最後に、やはり子どもを読書好きにしたいと思ったら、親が読書をする姿を見せることが一番です。
そして、子どもを図書館や本屋に誘ってみましょう。
たまたま手にした本がきっかけで、読書が好きになる例はいくらでもあります。
読書が好きでなくても受験は乗り切れます。
しかし、人生を豊かにするという意味では、読書好きであることは決して損ではないと思います。
今からでも遅くはありません。
ぜひ、わが子を読書好きにしてみてはいかがでしょうか?
菅原先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。