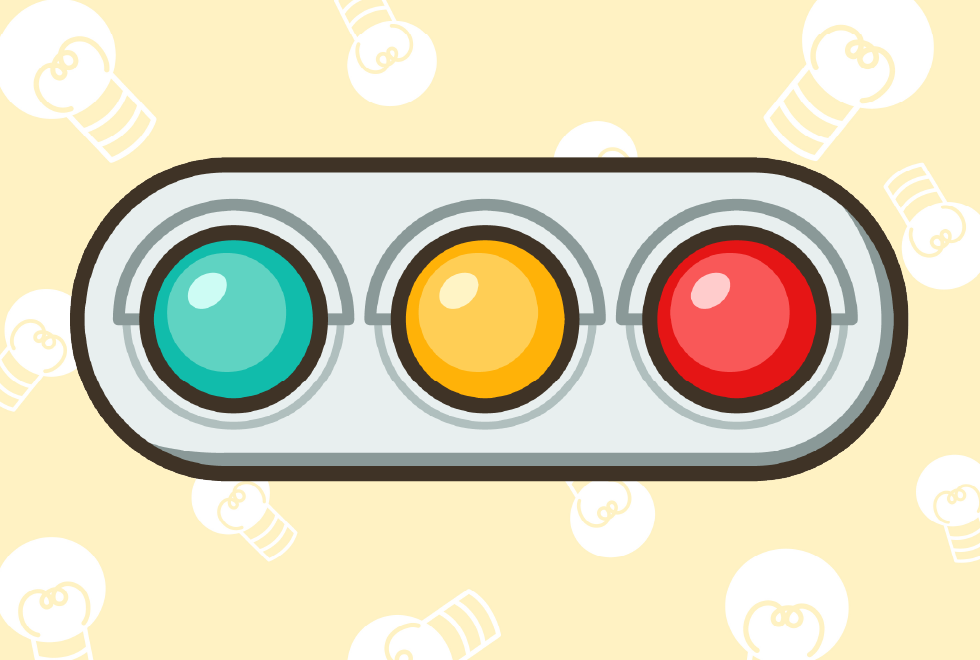ワーキングメモリーを鍛えるのはなぜ大事?
ワーキングメモリーが脳科学・教育学・心理学などの分野で注目されています。
ワーキングメモリーとは、思考・判断・行動・作業・学習などに必要な複数の情報を、頭の中に一時的にとどめながら処理する能力のことです。
イメージ的にいえば、何か作業するときの作業台のようなものです。
例えば、工作などで物を作るときに、作業台の上に必要な物を用意して、あれをやったりこれをやったりしながら、だんだん一つの物を作りあげていきます。
ワーキングメモリーとは、この作業台のようなものです。
作業台が広ければ広いほど、より多くの必要な物をすぐ使える状態で広げておくことができ、複雑な作業も可能になり、作業の能率が上がります。
逆に、作業台が狭いと複雑な作業がやりづらく、能率も上がりません。
勉強ではワーキングメモリーが大事
例えば、国語の学習において文章を読んで理解し、自分の経験と照らし合わせて考えたり、それを文章にまとめたりする作業にもこのワーキングメモリーを活用しています。
算数・数学で、問題やグラフを読み取って式を作ったり、計算したりするのにも使います。
私が4年生の子どもたちに算数を教えていたときのことです。
785÷29などという大きな数どうしの割り算を筆算するときは、785の中に29がいくつ入るかを求めます。
それを知るためには29を概数の30にして、まず78の中に30がいくつ入るかを考えます。
78の中には2つ入るので、仮の商として2という数字を8の上に書きます。
次に29と2を掛けて、答えの58を78の下に書き、それから引き算をしますね。
その後も、また仮の商を立てたり掛けたり引いたりという複雑な過程があるわけですが、ワーキングメモリーの容量が少ない子は、やっている途中で今何をやっているのかがわからなくなってしまうのです。
大人でも、複雑な思考や仕事をしているとき、途中で自分が何をやっているのかわからなくなってしまうことがあると思います。
日常生活でも大事なワーキングメモリー
日常生活においても、やるべきことを忘れずにちゃんとやったり、人にいわれたことを覚えておいて行動したり、人と会話をしたりするなど、あらゆる場面でワーキングメモリーを使っています。
そして、この能力が高いほど、複雑で高度な思考や行動が可能になります。
ですから、学力を上げるためにも、仕事や生活の質を上げるためにも、ワーキングメモリーを鍛える必要があるのです。
ワーキングメモリーを鍛える方法とは?
ワーキングメモリーを鍛えるにはどうしたらいいのでしょうか。
それについては下記の方法がお薦めです。
▼間違い探し
例えば、「右の絵と左の絵をくらべて、違っているところを5つ見つけましょう」というような間違い探しクイズです。
間違い探しをしているときは、片方の絵を見てそれを一時的な記憶にとどめながら、もう片方の絵を見ることになります。これがワーキングメモリーを鍛えるのに有効です。
▼逆さ言葉
「れいぞうこ」の逆さ言葉は「こうぞいれ」です。
「あいすは れいぞうこの なか」という文に逆さ言葉を取り入れると、「すいあは こうぞいれの かな」とすることができます。
逆さ言葉を作ったり解いたりするには、言葉を一時的に頭の中で記憶してから逆さにします。遊びながら自然に訓練することができます。
▼トランプの「神経衰弱」ゲーム
トランプ遊びの「神経衰弱」も有効です。
このゲームでは、自分や相手が開けたカードを覚えておく必要があります。
たくさん覚えれば覚えるほど、同じ数字のカードを開けて取ることができるわけです。
▼会話・おしゃべり
人と会話するためには、相手が話したことを覚えておいて、それに反応する必要があります。
また、相手の話を聞きながら、自分のいいたいことを考える必要もあります。
このとき、頭はフル回転していて、ワーキングメモリーが向上します。
▼暗算
筆算ならば紙に書きながら計算していきますが、暗算では全てを頭の中でやらなくてはなりません。
繰り上がりの数や途中の計算の答えなども覚えておく必要があり、暗算している間ワーキングメモリーが働いているというわけです。
▼十分な睡眠時間
適切な睡眠時間の確保も大切です。
2019年に発表された、カリフォルニア大学、ミシガン大学、アメリカ国立神経障害・脳卒中研究所の研究によると、睡眠不足が脳のワーキングメモリーを減らすことがわかったということです。
これは私たちの経験からもいえることではないでしょうか。寝不足のときにはうまく頭が働きません。
▼料理や家事
料理や家事をしているときは、さまざまな作業を効率よく行う必要があります。
ゴールのイメージを想像しながら、作業手順を考えて段取りよく進めることで、ワーキングメモリーが鍛えられます。
▼運動
紙上敬太准教授(中京大学)の研究で、ワーキングメモリーは運動によって向上するという結果が得られています。
▼瞑想
2019年に報告されたニューヨーク大学の研究で、瞑想によってワーキングメモリーの機能が向上することがわかりました。
このように、いろいろな方法があります。
大事なことをもう一度繰り返しますが、子どもにとっても大人にとっても、ワーキングメモリーの向上は人生の質を高める上で欠かせないものです。
ぜひ、親子で楽しみながら取り組んでみてください。
TOMAS全校で無料受験相談を承っています
「志望校に向けて何から始めてよいかわからない」「足を引っ張っている科目がある」「塾・予備校に通っているが成果が出ない」など、学習面でお困りのことはありませんか? 進学個別指導TOMASならではの視点で、つまずきの原因を分析し、課題を解決する具体策を提案します。まずはお気軽にご相談ください。
親野先生 記事一覧
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。