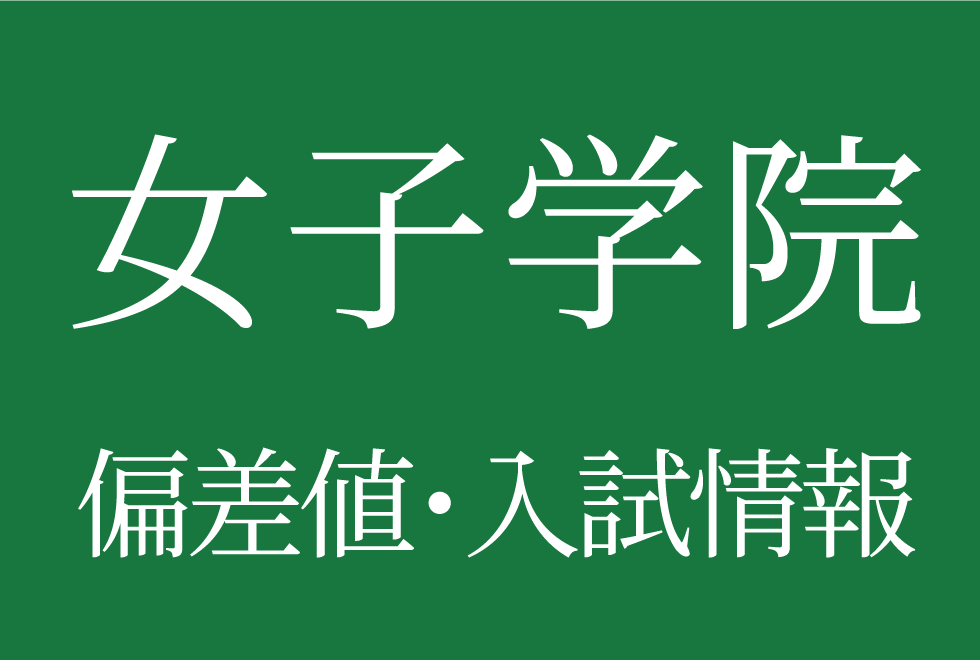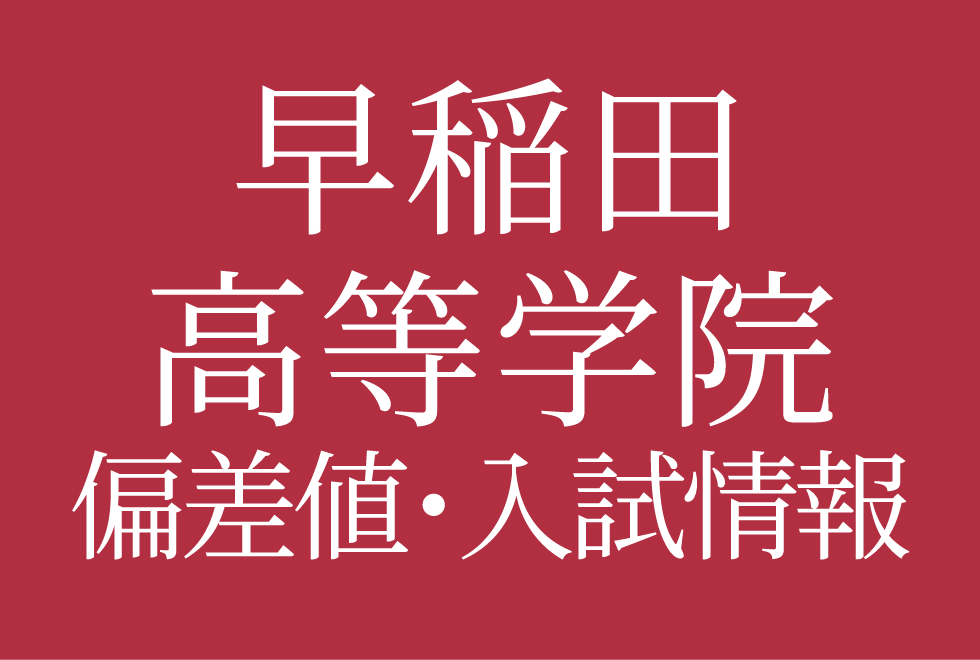さきよみ中学受験

忘れていない? 災害時の備えや教訓
東北地方に甚大な被害をもたらした東日本大震災から10年が経ちました。
当時、首都圏の中学・高校に通っていた生徒たちも大きな影響を受けました。
ですが、震災の後、学校の防災意識が高まり、また、困難ななかでも積極的に学ぼうとする生徒たちの自主的な動きがあったことも忘れてはなりません。
被災地以外の都市部では、防災意識が薄れがちです。学校の防災体制を確認するだけでなく、通学ルートの確認や家族との連絡方法など、非常時の約束事を改めて確認しておきたいものです。
その時、首都圏の私立中高では
三陸沖を震源とする大地震の揺れは、被災地から離れた首都圏にも伝わりました。
地震の発生は午後3時前だったため、校内にいた生徒、下校中の生徒など、それぞれの活動をしていた生徒たちはさまざまな状況に巻き込まれ、学校は混乱しました。
スマートフォンやSNSが今ほどに普及する以前のことですから、携帯電話の通話もメール回線もつながりにくくなり、保護者は子どもの安否を確認できず、不安な時間を過ごさなければなりませんでした。
私立中高一貫校は通学範囲が広いため、帰宅困難になった生徒も多くいました。
通学途中の駅まで保護者が迎えに行くのに何時間もかかったり、行き違いになってしまったりしたケースもあったといいます。
また、自ら判断して学校へ引き返し、翌日まで過ごした生徒もいました。
学校では教職員が安否確認に奔走し、献身的に生徒の安全を確保しました。校内にとどまった上級生が校内で炊き出しをし、おにぎりを作って下級生たちに食べさせた都内の女子校もありました。
教訓を教育活動に活かす
これらの経験を教訓として、震災以降、水や食料、毛布などの備蓄を増やしたり、避難経路などを見直したり、学校説明会でも積極的に災害時の対応について説明する私立中高一貫校が増えました。
緊急連絡用に携帯電話の持参を認めるようになった学校や、ホームページだけでなく、ツイッターのようなSNSでの情報発信を行うようになった学校もあります。
教育活動の面でも、教科や総合的な学習の時間を使って防災について考えたり、被災地支援につながるボランティア活動を行ったり、また、募金を長く続ける学校も数多く見られました。
被災地以外で薄れる関心や備え
東日本大震災以降も、熊本や北海道での地震をはじめ、台風や集中豪雨、豪雪などの災害が続くなか、人々の防災意識は高まったかというと、むしろ記憶の風化が進んでいると言わざるをえないようです。
日本赤十字社は、2020年12月に、災害の記憶と防災意識の変化に関するアンケート調査を実施しました。対象は東日本大震災の被災地(岩手・宮城・福島)に住んでいるか、住んだことがある人100人と、その他の主要都市(東京・愛知・大阪・福岡)に住んでいる人400人です。
調査の結果から、被災地に住む人と、その他の都市に住む人とでは、災害意識や取り組みに開きがあることがわかりました。
例えば、「自分が今日、災害に遭うかもしれない」と考える頻度について、「月に1度以上」と答えた人は、被災地で55%だったのに対し、主要都市部では38%と差があることが明らかになりました。
災害に対する家庭での「備え」は、被災地で「十分とは言えないが、一応の備えはしている」が最多で65%を占めたのに対し、都市部では45%が「いつかはやらなければと思っているが、まだ備えはできていない」と答えています。
もし今、災害が起こってしまったら、被災地以外の都市では2人に1人が備えなしで災害を迎えてしまうことが調査結果からうかがえるのです。
防災の意識を家族でも高めよう
自然災害に慣れていない首都圏では、公共交通機関が止まると通学や通勤経路が寸断され、身動きが取りにくくなります。
都内で大震災が発生した場合は、震度によっては主要な幹線道路で交通規制が実施されるため、車での送り迎えは困難になります。
この対策として、東京私立中学高等学校協会は、「登下校緊急避難校ネットワーク」を2013年に立ち上げています。
これは、登下校中に大きな地震が発生し、公共交通機関が止まって学校や自宅にたどりつけなくなった場合に、近くの私立小中高校に避難すれば、所在と安否を在籍校に連絡するというシステムです。
こうした緊急時の学校の対応を確認し、家族の連絡方法を決めておくことも大切です。
災害が起こったとき、最終的には家族一人ひとりが、命を守る行動を自分で判断し、行動できる力が求められます。
震災を知らない世代が学齢期を迎えるなか、通学の安全を学校だけに任せるのではなく、家庭でもいざという場合に備えておく必要があるでしょう。災害から身を守る力を育ててあげたいものです。
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。