
最難関校合格を勝ち取る 中学受験の「国語」勉強法
National Language Study Tips for Top Junior High School Entrance Exams
国語は、「勉強しなくてもできる」「勉強しても伸びない」「中学受験で差がつくのは算数だから、そこまで懸命に対策しなくてもよい」など、多くの誤解にさらされている教科です。
まず、知識分野である「語彙」は暗記が必要ですから、意識的に勉強しなければできるようになりません。「勉強しなくてもできる」は間違いです。
また、国語の読解問題には体系的な「読み方」と「解き方」がありますから、語彙と同じように意識的に勉強していけば得点力は必ず伸びます。「勉強しても伸びない」も間違いです。
さらには、最難関校受験生は算数の対策を完璧に仕上げてくる一方、国語の対策で油断している子もいるので、国語で高得点をとることができればとても有利です。したがって、「そこまで懸命に対策しなくてもよい」も大きな誤解なのです。
ここでは、最難関校合格に近づく国語の勉強法を取り上げます。
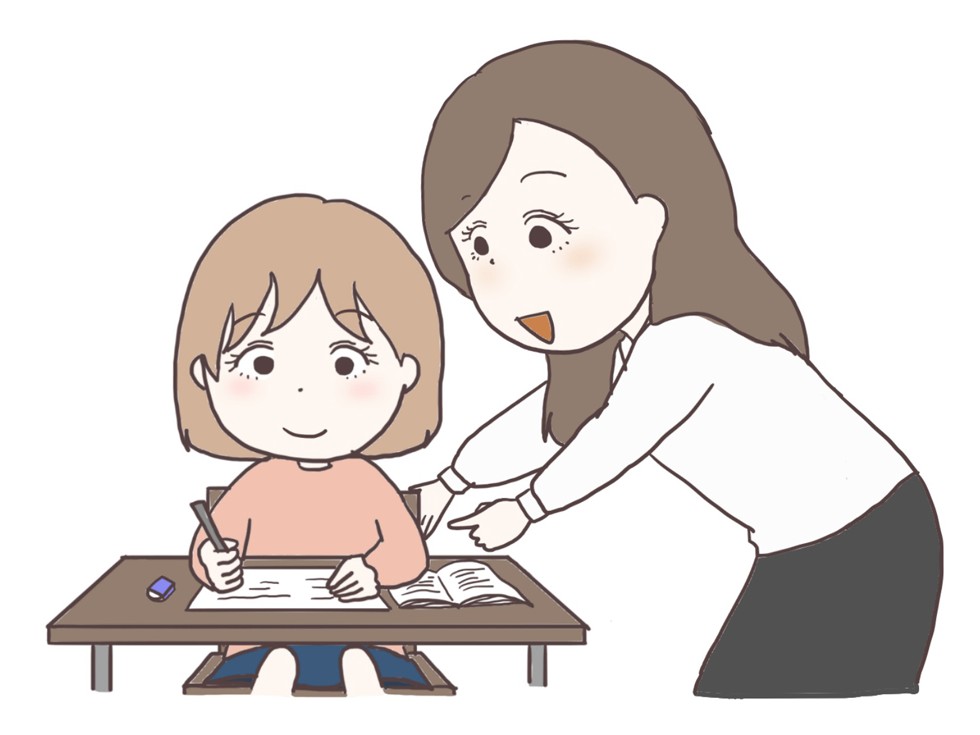
【中学受験の「国語」勉強法⑥】合格点をとるために必要な「設問形式別対策」の方法
powered by Spec. TOMAS
ここからは、中学受験国語の読解問題を構成するおもな設問形式を取り上げ、実践的な対策をお話しいたします。頻出形式は、以下の4通りです。
| 設問形式① | 選択肢問題 |
|---|---|
| 設問形式② | 抜き出し問題 |
| 設問形式③ | 空所補充問題 |
| 設問形式④ | 記述問題 |
設問形式①選択肢問題
選択肢は、自分で答えを考えるまで見てはならない
「選択肢問題」は、本文内容を言い換えているいくつかの選択肢の中から、本文内容が正しく反映されている選択肢を答える、という設問形式です。
「選択肢問題」を解く場合に大切なのは、選択肢を見比べる前に、本文内容を根拠としながら、自分である程度まで文章形式の解答をつくっておくことです。何も考えていない状態でいきなり選択肢を読んでしまうと、どれを選べばよいのかに迷ってしまいます。「選択肢問題」は、自分が用意した解答案と問題で示された選択肢とを照らし合わせて正解を検討するという方針で解いていきましょう。
選択肢は、1箇所でも誤りを含んでいたら不正解
1問の「選択肢問題」に含まれる選択肢は、だいたい4個か5個です。多くの場合、この中の2個程度の選択肢に「明らかにありえない」という内容が混ざり、残りの選択肢に、本文内容に近い(が誤っている)選択肢と、本文内容と合っている正解の選択肢が紛れています。
「明らかにありえない」選択肢と「明らかにこれしかない」選択肢は、すぐに見つかります。一方、「本文内容に近い(が、誤っている)」選択肢と、「本文内容に合っている」選択肢は、見た目が似ているため、なかなかすぐには区別できません。そのような微妙な選択肢どうしは、じっくり時間をかけて比較検討する必要があります。
その際の判断基準は、本文内容と一致しているかどうかです。選択肢に含まれる言葉のたった1つでも本文内容と一致していなければ、その選択肢は不正解だと判断しましょう。
選択肢は、パーツごとにスパスパ切り分ける
「選択肢問題」を解くうえで応用の利くテクニックがあります。それは、1個分が長い選択肢をいくつかのパーツに切り分けるという方法です。
それぞれの選択肢は文のつくりが似ているので、なんとなく見ているだけでは、どの選択肢も同じように思えます。しかし、それでは出題者の思うツボです。選択肢どうしは、一言一句とも漏らさず正確に吟味していく必要があります。選択肢はパーツごとにスラッシュ(/)で切り、ほかの選択肢と「どこが同じか」「どこが違うか」をていねいに照らし合わせていきましょう。
「選択肢の区切りをどこに入れるか」については、あまり神経質に考える必要はなく、ある程度機械的に処理してしまってかまいません。前半と後半、読点(、)の前後など、見た目としてわかりやすい箇所に入れていきましょう。
選択肢の間違い箇所は、目印をつけてチェック
問題演習では、選択肢と本文内容の対応を見きわめ、誤りの選択肢を見つけたら、その間違い箇所に目印をつけていってください。慣れないうちは、自分が目印をつけた間違い箇所と、出題者がワナとして仕掛けた間違い箇所を照らし合わせても、双方はなかなか一致しません。しかし、問題演習を重ねて実力がついていくと、その2つはだんだん重なっていきます。
設問形式②抜き出し問題
「抜き出し問題」に潜む「魔力」
受験生には、「抜き出し問題」が好きだという子がたくさんいます。「抜き出し問題」は、記述問題などと比べると正解の客観性が高く、正解が見つかったときの喜びは絶大です。それは、算数の難問が解けたときの高揚感に似ています。多くの子どもが、その達成感を味わいたがります。そのため、「抜き出し問題」で答えが見つからないとそのまま粘り、解答時間をロスしてしまうというケースが多発するのです。
「抜き出し問題」では「文末」に着目
「抜き出し問題」には、たとえば傍線部と正解箇所が離れているという意地悪な設問も出てきます。このような設問は解くのに時間を要しますが、ちゃんと「抜け道」は存在します。それは、問われ方次第では答えの形がある程度予想できるという点です。
たとえば、「理由」を答えさせる設問ではしばしば、正解箇所の「文末」が「から」「ので」「ため」などの形で終わっているケースが見られます。問題演習ではこれらの大ヒントを見逃さず、目ざとくチェックしていきましょう。
字数カウントは「後ろ」から
「抜き出し問題」で時間がかかるのは、正解箇所の字数が設問の条件に合っているかどうかを確認する作業です。その際には、「文末」に注目して後ろから数えていくという方法を徹底しましょう。
たとえば、「35字以内で抜き出し、始めと終わりの5字を書きなさい」という、長めの字数を切り取らせる設問があるとします。ここでかなりの時間を要するのが、この35字分を正確にカウントすることです。このタイプの設問でどこからどこまでを抜き出すのか判断する際には、やみくもに頭から数えるのは悪手です。前からあてずっぽうに数えてしまうと、「あれっ、合わないぞ。じゃあ、ここから数えてみよう。でも、これも合わないな……」など、何度も数え直すことによる時間のロスが生じてしまいます。
ここで必要なのは、先ほどお話ししたとおり、冒頭からではなく後ろから前に向かってカウントしていくことです。こうすることによって、対象箇所の切り取りでミスする可能性は大きく下がっていきます。
抜き出した箇所は、5字ずつスラッシュを入れてカウント
「選択肢問題」の項目では、目印を入れることが大切だとお話ししました。その方法は、「抜き出し問題」にも応用可能です。この設問形式でも、目印としてスラッシュ(/)を使いましょう。
先ほど取り上げた「35字以内」のような長めの字数を答えさせる設問では、抜き出し対象となっている箇所に5字ずつスラッシュを入れていくとうまくいきます。
それには2つの理由があります。1つは、5、10、15、20、……のような5の倍数はカウントしやすいからです。
もう1つは、解き終わったあとの見直しが楽だからです。中学受験の世界でよくいわれる時間配分の方法は、いったんすべての大問を解いたら、試験終了までの残り時間の5分程度を見直しにあてるというやり方です。しかし、正しく書けているかどうかを点検する場合に、本文中に自分が解いた痕跡を何も残していなかったとしたら、抜き出した箇所を思い出しながら探すこととなり、時間のロスが生じてしまいます。そうならないよう、どこからどこまでを抜き出したかという視覚的な目印としてスラッシュをフル活用してください。
設問形式③空所補充問題
答えのヒントは空所の前後にあり
本文中の空所に適する内容を穴埋めさせるという「空所補充問題」の形式には、接続語のような語句を入れさせるパターンと、ある程度長めの文を入れさせるパターンがあります。
「空所補充問題」は、空所の前に書かれている内容と、空所のあとに書かれている内容がどのような関係にあるのかを把握しながら解いていきましょう。ここでの「関係」とは、「最難関校合格を勝ち取る 中学受験の『国語』勉強法_ぜひ知っておきたい『論説文』『評論文』の『読み方』」の記事でお話しした「同等関係」「対比関係」「逆接関係」などをさします。
ここまでにずっと「明確な根拠にもとづいて設問を解く」ことの重要性を説明してきました。問題作成者は、「空所補充問題」の解答根拠を空所の前後に置きます。そのため、「答えのヒントを拾うために空所の前後を見る」というメソッドはとても合理的なのです。
設問形式④記述問題
「何ですか」と「なぜですか」を問う形式が主流
実際に答案を書かせるという「記述問題」には、おもな設問形式が2つあります。
1つ目は「内容説明問題」で、「何ですか/どういうことですか」を尋ねるスタイルです。この設問形式では、「言い換え」の力が試されます。よくあるのは、「具体的な表現を抽象化して言い換えさせる」というパターンです。ある物事を別の似た何かにたとえる言葉を「比喩(ひゆ)表現」といいますが、このパターンでは、その「ある物事」が何をさしているのか答えさせる設問がよく出ます。なお、「抽象的な表現を具体化して言い換えさせる」という逆パターンは、さほど多くありません。
2つ目は「理由説明問題」で、「なぜですか/どうしてですか」を尋ねるスタイルです。最難関校では、バリエーションとして「どう考えますか」を問うという「思考力系」のパターンも見られ、国語だけでなく社会の記述問題にも出てきます。
「記述問題」を解く際の大前提があります。それは、設問形式に合わせて文末表現を使い分けるということです。「内容説明問題」は「何/どういうこと」を尋ねますから、文末は「○○ということ」などで締めるのが一般的です。一方、「なぜ/どうして」を尋ねる「理由説明問題」であれば、文末には「△△だから」などを用いることとなります。
答案は「幹」+「枝葉」でまとめる
最難関校の「記述問題」では、50~100字のように指定字数の多い解答が求められます。たとえば、「このときの登場人物の気持ちを60字以内で説明しなさい」という「心情説明問題」の設問に対して、「くやしい気持ち」「ほこらしい気持ち」などひと言しか書かなかったら、点数は当然つきません。だからといって、「60字以内」という指定字数に近い分量で書きさえすれば丸がつくかというと、そういうわけでもありません。解答に必要な要素が入っていなければ、高得点はとれないからです。
記述答案には、解答要素として「幹」と「枝葉」を盛り込むよう心がけてください。「幹」は解答の軸となる部分です。「枝葉」はその「幹」を説明する部分であり、くわしい内容や理由などを表します。先ほど挙げた「心情説明問題」に即していえば、「悔しい気持ち」「ほこらしい気持ち」が「幹」にあたります。また、「枝葉」として考えられるのは、たとえば「大人に自分の考えを理解してもらえなかったことからくる(くやしい気持ち)」「親友が学校の先生にほめられ、まるで自分のことのように(ほこらしい気持ち)」などです。答案作成においては、「幹」を絶対にはずさず書き、「枝葉」で字数のバランスを調整していきましょう。理想的な答案作成は、「幹」であらかたの字数を確保しつつ「枝葉」で調整するという方法です。
解答根拠は1箇所とは限らない
「記述問題」の中には、最終段落に出てくる表現をそのまま抜き出し、文末だけ整えて書けば正解できるというタイプの問題もあります。低学年向けの教材に載っている問題は、だいたいこのパターンです。
しかし、最難関校の入試ではそんな易しい問題は出ません。最難関校の記述答案では、本文中に散らばっている複数の解答根拠を1つにまとめて書くことが求められます。最初のうちは、多くの受験生がこのパターンに苦戦します。しかし、「解答根拠の見つけ方」と「表現の整え方」がわかってくると、だんだんうまく書けるようになっていくのです。
過去問集に載っている答案例を分析して気づくこと
最難関校に出てくるような難しい「記述問題」でなかなか点数がとれない受験生におススメの勉強法は、過去問集に掲載されている記述答案例の研究です。
ここまでに何度も申し上げてきたように、国語における解答根拠は、基本的にすべて本文に書かれています。いくつかの答案例に目を通していくと、多くの答案例が本文の表現を下敷きとしていることに気づきます。このような答案例を解説とともに読み込むことによって、本文のどの箇所が答案の中に引っ張られてきているかがわかってきます。それがわかる状態に達したら、どの学校でも通用する記述力が身についていると自信を持ってもらってかまいません。
まとめ

「解答根拠はすべて本文にある」……この原則は、たとえ最難関校の入試問題であっても例外なく当てはまります。問題演習では、自分の主観を差しはさまず客観的に読んでいく姿勢を追求しましょう。
■夢の志望校合格に導く 低学年からの難関校対策個別指導塾[スペックTOMAS]
https://www.tomas.co.jp/spec/
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。








