
最難関校合格を勝ち取る 中学受験の「国語」勉強法
National Language Study Tips for Top Junior High School Entrance Exams
国語は、「勉強しなくてもできる」「勉強しても伸びない」「中学受験で差がつくのは算数だから、そこまで懸命に対策しなくてもよい」など、多くの誤解にさらされている教科です。
まず、知識分野である「語彙」は暗記が必要ですから、意識的に勉強しなければできるようになりません。「勉強しなくてもできる」は間違いです。
また、国語の読解問題には体系的な「読み方」と「解き方」がありますから、語彙と同じように意識的に勉強していけば得点力は必ず伸びます。「勉強しても伸びない」も間違いです。
さらには、最難関校受験生は算数の対策を完璧に仕上げてくる一方、国語の対策で油断している子もいるので、国語で高得点をとることができればとても有利です。したがって、「そこまで懸命に対策しなくてもよい」も大きな誤解なのです。
ここでは、最難関校合格に近づく国語の勉強法を取り上げます。
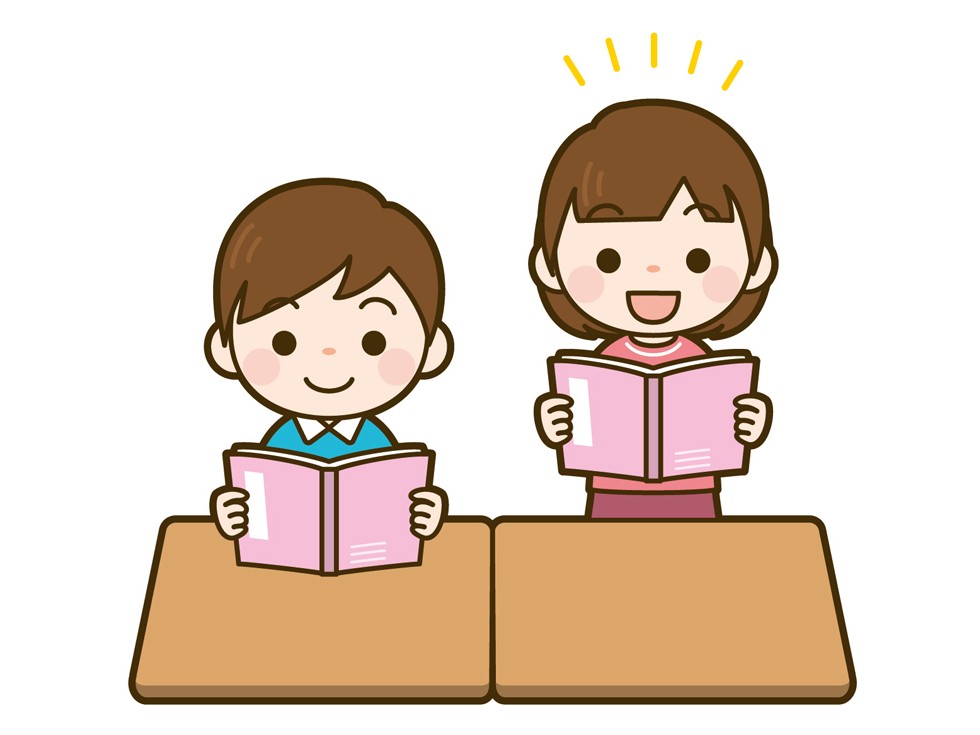
【中学受験の「国語」勉強法⑤】ぜひ知っておきたい「物語文」の「読み方」
powered by Spec. TOMAS
ストーリーのつかみ方
「物語文」には「セオリー」がある
筆者が感じたことを自由に表現していく文章は「文学的文章」と呼ばれ、おもに「物語文」「随筆」「詩」などをさします。以下では、このうち「物語文」にフォーカスしてお話しします。
中学受験では、多くの学校が「物語文」を出題しています。たとえば、麻布中の出題は、例年「物語文」1題のみです。
「物語文」にも、「論説文」「評論文」と同じく読み方のコツがあります。それは、文章のストーリー展開をつかむことです。
ストーリー展開を把握するためにおさえる必要があるのは、「登場人物とその心情」「時代背景」「出来事」「出来事の結果として起きた、登場人物の心情変化」などの要素です。「物語文」には、だいたいこのような要素にもとづいてストーリーが展開されていくという「セオリー」があります。
もしこの「セオリー」がなかったら、「物語文」は成立しません。たとえば、「太郎くんと花子さんが学校の帰り道をいっしょに歩き、2人とも何事もなく家に着いた」という、何の出来事も起こらないストーリーの文章は、入試問題には不向きです。もし入試問題をつくるのであれば、文章のストーリーには、起伏が必要です。たとえば「太郎くんと花子さんが学校の帰り道をいっしょに歩いていたら、捨て猫を見つけた。その捨て猫をどうしようかと話したら、それぞれの考えが違っていたため、ちょっとしたケンカが起きてしまった。2人とも少し落ち着いてから話し合いを再開してから、太郎くんが捨て猫を家に持ち帰ることに決まり、太郎くんは親にここまでの経緯を話すこととなった」などです。ここで読み取るべきポイントは、「捨て猫を発見した」という「出来事」と、その出来事の結果、2人の気持ちがどういう状態に移っていったかという「出来事の結果として起きた、登場人物の心情変化」です。
このようなポイントをとらえる際に大切なのは、「あくまでも客観的にとらえる」という姿勢です。「猫が好きだから」「ペットを飼ってみたいから」などという受験生自身の主観を差しはさんではなりません。「物語文」の設問には、本文から読み取れる最大公約数的な内容にもとづいて答えていく必要があります。
「場面」をおさえながら読む
「最難関校合格を勝ち取る 中学受験の『国語』勉強法_ぜひ知っておきたい『論説文』『評論文』の『読み方』」の記事で述べたとおり、「論説文」「評論文」の読み取りで「段落」がポイントになるのと同様、「物語文」でポイントとなるのは「場面」の読み取りです。入試では、たとえば「場面を3つに分けたときに、3番目の場面はどこから始まりますか」などという設問が出てきます。
「場面」の中でとくにしっかり読み取るべき情報は、「時間の変化」と「場所の変化」です。先ほどの例に即すると、「時間の変化」としては、「帰り道で捨て猫を見つけた」ことから「太郎くんが捨て猫を家に持ち帰った」ことへ移ったことなどがわかります。また、「場所の変化」としては、「帰り道」から「太郎くんの家」へ移ったことなどがあります。「物語文」の読解では、このような時間や場所などの情報の「ズレ」に注目しましょう。
問題を解く姿勢
「回想場面」では時間軸がズレる
以下では、「物語文」の入試問題を解く際に意識してほしい内容をお話しします。
上の項目では、「物語文」において「場面」設定を読み取ることの重要性を説きました。その「場面」の中でもとりわけ特徴的で、また読解問題でポイントとなる特殊な状況設定が2つあります。それは「回想場面」と「風景描写」です。
「回想場面」は、ストーリー展開の時間軸からズレている場面をさします。「物語文」では、たとえば「海辺に行って潮風のにおいをかいだ」などの場面から、「小さいころに親と海水浴に行った」などの場面にいきなり飛ぶこともあります。しかし、多くの子どもは「物語文」にそのような展開があることを知らないため、「いきなり話が変わっちゃった。どうして?」とうろたえ、全体のストーリー展開を見失ってしまいます。しかし、読解演習を重ねていくと、「何か話が変わったぞ、これは昔の話なのだろうな」というように、「回想場面」を正確に読み取れるようになっていきます。このように、「物語文」の読解演習では「経験値」を高めることが肝心です。
「風景描写」では、隠された「心情」をおさえる
「物語文」には、登場人物の心情が風景に投影されている場面がたびたび出てきます。これが「風景描写」です。
たとえば、「登場人物の決心がぐらついている」という場面では、「しだれ柳が風に揺れていた」などという表現がよく用いられます。しかし、トレーニングを積んでいない小学生は、こういう表現を「柳が揺れているってどういうこと? わかんない」と無視してしまうのです。
そのような「既読スルー」を防ぐためには、「物語文の中で、筆者は、心情を直接的には表現せず、周囲の物や人に託して表現する場合がある」ということを読解演習によって理解し、表現技法の知識として蓄えていく必要があります。つまり、ここでも「経験値」を高めることが肝心なのです。こういう読み方を知っていれば、次に似たような内容の文章が出てきた場合でも、「風景描写」を一発で見抜けます。
「物語文」には「根拠」がない?
入試問題に臨む姿勢の大前提は、「明確な根拠にもとづいて解く」ことです。しかし、「物語文」の一部には、解答根拠が特定できない設問も含まれます。「これは、筆者に直接確認しなければ答えられないだろうな」というあいまいな設問も出ていて、こういう点が、子どもたちに国語を「難しい」と感じさせてしまう障壁となっています。
しかし、実際の最難関校入試では、こういう「グレーゾーン」の設問もしばしば出てきます。その対策としては、自分で経験したことがない種類の心情変化や他者の思考過程などを、志望校の「過去問演習」を通じて理解していくしかありません。
まとめ

学習の初期段階にある受験生は、「物語文」の記述に込められた筆者の意図を読み取ることに苦労します。ここで取り上げた「時間・場所に関する情報の『ズレ』」「回想場面」「風景描写」などを読解演習で確認し、「物語文」の約束ごとに慣れていきましょう。
■夢の志望校合格に導く 低学年からの難関校対策個別指導塾[スペックTOMAS]
https://www.tomas.co.jp/spec/
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。








