
最難関校合格を勝ち取る 中学受験の「国語」勉強法
National Language Study Tips for Top Junior High School Entrance Exams
国語は、「勉強しなくてもできる」「勉強しても伸びない」「中学受験で差がつくのは算数だから、そこまで懸命に対策しなくてもよい」など、多くの誤解にさらされている教科です。
まず、知識分野である「語彙」は暗記が必要ですから、意識的に勉強しなければできるようになりません。「勉強しなくてもできる」は間違いです。
また、国語の読解問題には体系的な「読み方」と「解き方」がありますから、語彙と同じように意識的に勉強していけば得点力は必ず伸びます。「勉強しても伸びない」も間違いです。
さらには、最難関校受験生は算数の対策を完璧に仕上げてくる一方、国語の対策で油断している子もいるので、国語で高得点をとることができればとても有利です。したがって、「そこまで懸命に対策しなくてもよい」も大きな誤解なのです。
ここでは、最難関校合格に近づく国語の勉強法を取り上げます。
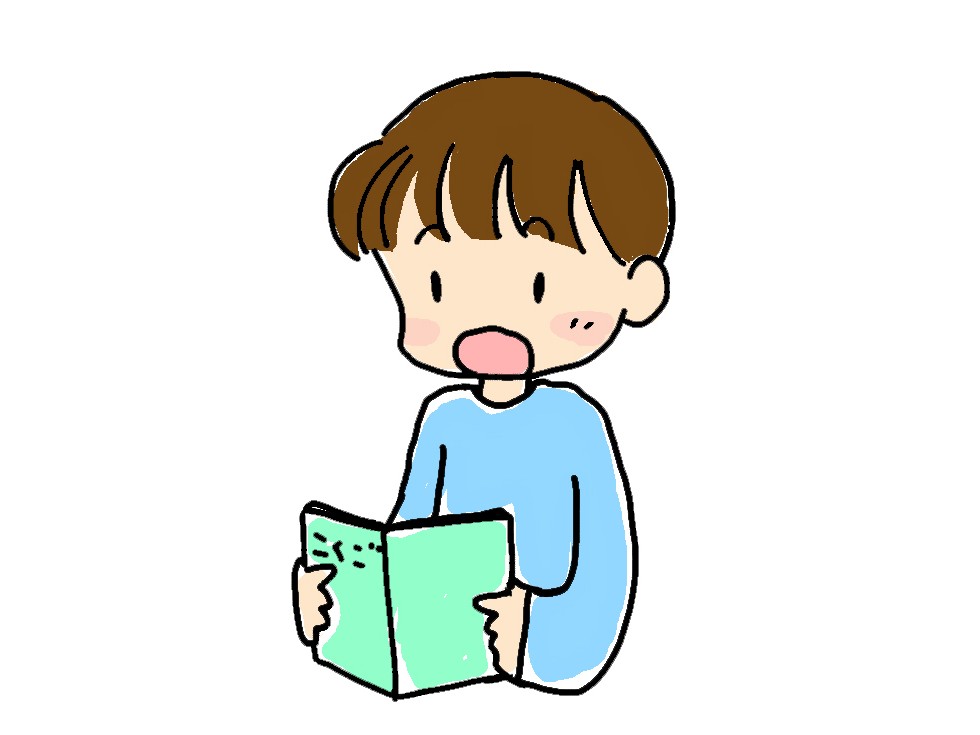
【中学受験の「国語」勉強法④】ぜひ知っておきたい「論説文」「評論文」の「読み方」
powered by Spec. TOMAS
文章の流れと、文どうしの関係
“「一般論」の否定☞筆者独自の意見”という流れが頻出
ここでお話しする「論説文」「評論文」は、筆者が自分の意見・見解・考え・主張などを述べるために書かれる文章であり、「説明的文章」とも呼ばれます。「説明的文章」には、小学生にとっては見慣れないテーマや聞き慣れない言葉がたくさん出てきます。そのため、多くの受験生が「苦手だなあ」「いやだなあ」という苦手意識を抱いています。
しかし、そんな難しい文章にも、攻略のコツがあります。それは、文章の展開パターンをつかむことです。
筆者は、自分が言いたいことを伝えるために文章上でさまざまな技巧を凝らします。そのような表現上の工夫として高頻度で用いられるのは、「一般論」を否定することによって筆者が独自の意見を述べる、という型です。
この展開パターンでは、「世の中ではよく~だといわれている」のような「一般論」の後ろに、「しかし、私は……だと考える」のような「筆者独自の意見」が続きます。ここでは、「しかし」という「逆接」の「接続語」を使って、世の中の常識や慣例とは異なる視点を示しているのです。
このような文章展開が出てきたら、「一般論」と「筆者独自の意見」がそれぞれどこに置かれているのかをしっかりと把握しましょう。「客観的に読む」とは、まさにこういうことです。
文どうしの「同等関係」「対比関係」「逆接関係」をおさえる
「論説文」「評論文」では、上で述べた「一般論」と「筆者独自の意見」のような文章全体の流れだけでなく、文と文の間のつながりまで読み取る必要があります。そのような文どうしの関係の典型例が「同等関係」「対比関係」「逆接関係」です。以下、それぞれを説明します。これらの関係を見つけたら、本文中に目印を入れていきましょう。
| 関係の名称 | 意味 | 使われる目的 |
|---|---|---|
| 同等関係 | 前後で同じ内容が繰り返されている文どうしの関係 | 筆者が自分の考えに説得力を持たせる。 ☞そのために、似たような内容の文を何度も反復する。 |
| 対比関係 | 前後で比較対象が示されている文どうしの関係 | 筆者が自分の考えを強調する。 ☞そのために、自分の考えとはまったく異なる意見・見解を引き合いに出すこともある。 |
| 逆接関係 | 前後で反対の内容が表されている文どうしの関係 | 筆者が後ろの文で重要な内容を述べようとする。 ☞文と文の間に、「しかし」など、逆接の接続詞を用いることが多い。 |
もっとも、低学年の小学生がこのような抽象的な内容をすぐに理解することは困難です。そこで、これらの関係を身近な具体例に置き換えて考えてみましょう。
たとえば「逆接関係」を理解するとしたら、「太郎くんは、この前の算数のテストで60点をとった。でも、僕はそのテストで90点をとった」のような例文を考えてみるのです。この例文により、「僕」は、「でも」という逆接の接続語を使って、「自分が90点をとった」ということを強調(あるいは自慢)しています。低学年のうちは、文どうしの関係をこのような簡単な例によって理解できるだけで十分です。
また、本文中の目印は、「同等関係」「対比関係」「逆接関係」などの接続語だけでなく、「これ」「それ」「あれ」「どれ」などの「指示語」にも入れましょう。このようなちょっとした工夫次第で、設問は格段に解きやすくなっていきます。
文意のとらえ方
「段落」ごとに文意をおさえる
「論説文」「評論文」の文章で筆者が読者に伝えようとしている内容、つまり「文意」は、文どうしの関係からだけでなく、段落どうしの関係からも読み取れます。たとえば、日本文化について述べている文章に日本文化のすばらしさを伝えている内容、あるいは日本文化と対照的な外国文化を取り上げている内容が含まれているとしたら、それぞれの内容を段落ごとにとらえていきましょう。
このように、段落単位で文意をおさえることに慣れていくと、設問できかれている内容との対応箇所をつかみ、双方を照らし合わせながら解答する姿勢が身についていきます。このやり方を習得しておかないと、文章を最初から最後までもう1回読み直さなければならなくなるため、きわめて非効率的です。モタモタしているうちに時間をロスしてしまうと、後ろの大問にまったく手がつかないなど、大失点につながる可能性が生じます。
だからこそ、模試や過去問を解く際には、時間配分を強く意識しましょう。国語における時間配分の常道は、漢字などの知識問題をさっさと済ませ、「論説文」「評論文」の読解問題になるべく多くの時間をかけることです。
まとめ

「論説文」「評論文」の筆者は、自分が言いたいことを読者に伝えるため、文章にさまざまな工夫を凝らします。入試問題は、著者の考え・主張などが含まれる箇所を中心につくられます。問題演習では、「同等関係」「対比関係」「逆接関係」など、筆者が文章に仕掛けた表現技巧を1つひとつ正確におさえていきましょう。
■夢の志望校合格に導く 低学年からの難関校対策個別指導塾[スペックTOMAS]
https://www.tomas.co.jp/spec/
オススメ記事
記事一覧
お近くのTOMASを見学してみませんか?
マンツーマン授業のようすや教室の雰囲気を見学してみませんか?
校舎見学はいつでも大歓迎。お近くの校舎をお気軽にのぞいてみてくださいね。








