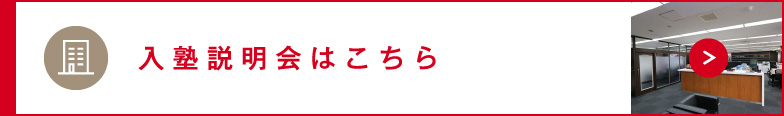親の関わりが増えている時代。一番よくないのは勉強への口出し
近年、医学部受験において保護者が関わるケースはデータ上でも増えています。しかし、子どもにとって一番よくないのは、勉強そのものへの口出しです。言えば言うほど成績が下がうと思った方がよく、保護者はあくまで補助的な役割に徹することが大切です。保護者が勉強の細かい部分に介入するのではなく、それ以外の情報面などを支えることがコツです。
効果的なサポートとは、勉強以外の情報やお世話
具体的には、どんなサポートが望ましいのでしょうか? 例えば、入試日程をまとめた表や出願書類を整理して渡すなどが効果的です。さらに、塾の送迎や、塾から帰宅した後に温かい食事を準備する、お風呂を沸かしておくなど、生活面での配慮も子どもにとってありがたい支援となります。保護者は「忍耐」を持ち、受験の主体はあくまで子どもであることを尊重しながら支えることで、入試が終わった後に「ありがとう」と感謝される関係を築くことができます。
模試の結果は、とにかくポジティブにとらえて
模擬試験は、あくまで現在の学力を確認するものであり、結果が悪くても伸びしろと捉えることが重要です。「今できていなくても、まだ入試まで時間がある」と前向きに声をかけることで、子どもに安心感を与えられます。一方で、成績が良すぎる場合も油断の原因になるため、模試の結果に一喜一憂せず、分析して苦手を潰していくことが大切です。必要に応じて1日オフを作るなど、メリハリをつけることも効果的です。
萩原校長談、親子間トラブルの実例
親子間のトラブルでは、志望校選びに関するものがよくあります。子どもが第1志望校を変えようとした際、保護者が反対することで衝突するケースです。最終的にどの医大に入学するかはご縁による部分も多いため、「子どもがそうしたいなら応援する」という姿勢が望ましいです。
また、起床時間など細かい行動に口を出すことでトラブルになることもあります。必要がないときは指摘しても子どものモチベーションを下げるだけの結果になることがあるため、注意が必要です。
医学部受験をめぐる世代間の違い――現在は難化傾向に
保護者の世代と比べると、医師を志す子どもが増えており、医学部受験は難化しています。過去の経験則に頼らず、今の入試制度や受験の環境を正しく理解することが大切です。保護者は最新情報をもとに、冷静に子どもを見守り、サポートしていくことが求められます。
まとめ
・勉強への口出しより、環境や情報面でのサポートを重視しましょう。
・子どもが受験の主役であることを忘れず、保護者は“応援団”として前向きに支えましょう。
・過去の価値観にとらわれず、今の入試制度や難易度を理解した上で、冷静に見守ることが重要です。







![[授業料などのお問い合わせ]0120-65-1359](/medic//img/header/tel.svg)